選択したカテゴリーの記事一覧
- 2025.11.30 [PR]
- 2025.06.05 ゲームレビューIndex
- 2020.01.05 BUSTAFELLOWS(バスタフェロウズ)の感想
- 2020.01.05 バスタフェロウズ攻略方法 BUSTAFELLOWS
- 2019.12.17 華アワセ いろは編と全編の考察と感想1(主題)
- 2017.06.17 閃の軌跡3、発売前の考察
- 2017.06.17 仁王(九州編)_感想
- 2017.06.01 三国無双7・感想
- 2017.06.01 ホライゾンゼロドーン感想
- 2016.12.14 FF15クリア&やりこみ後感想
- 2016.09.20 ペルソナ5 感想
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
上からオススメ順です
主観多々。世界観重視。
厨二ファンタジーと美男美女が好き。
【個人的な神作品】
*ICO(Act,PS2等)
*風ノ旅ビト(Act,PS3)
*rain(ADV,PS3)
*Demons&DarkSouls(Act,PS3)
*DarkSouls2(Act,PS3等)
*ラストオブアス(TPS,PS3)
*428(ADV,PSP等)
*シュタインズゲート(ADV,PS3等)
*空の軌跡,零の軌跡(RPG,PC等)
*ペルソナ5(RPG,PS4)
*ジルオール(RPG,PS2等)
*幻想水滸伝1-3(RPG,PS等)
*シャドウハーツ1&2(RPG,PS2)
*月下の夜想曲(Act,PS等)
*Ysシリーズ(ARPG,Vita等)
*逆転裁判(ADV,DS等)
*キングダムハーツ(RPG,PS2等)
*GTAシリーズ(TPS,PS3,ceroZ)
*ウィッチャー3(RPG,PS4,Z)
*スプラトゥーン(TPS,WiiU)
*華アワセ(乙女ゲーム,PC)
【個人的な秀作】
*ホライゾンゼロドーン(Act,PS等)
*FF5(RPG,SF)
*DQ5(RPG,SF)
*モンハン2G(Act,PSP)
*デビルメイクライ4(Act,PS3)
*アサシンクリード(Act,PS3,Z)
*アンチャーテッド(TPS,PS3)
*IQ(パズル,PS)
*TRICK&LOGIC(ADV,PSP)
*零~zero~(ADV,PS2)
*零~濡鴉の巫女~(ADV,WiiU)
*SIREN(Act,PS2等)
*ぐるみん(Act,PSP&PC)
*ダンガンロンパ1&2(ADV,PSP)
*プロジェクトディーバ(音楽,etc)
*龍が如く4(ADV,PS3)
*東方・紅魔城伝説2(Act,PC)
*式神の城(Stg,PS2)
*ペルソナ4(RPG,PS2等)
*大神(RPG,Wii等)
*ニーア・レプリカント(RPG,PS3)
*メタルギアソリッド(Act,PS等)
*dokuro(ADV,Vita)
【個人的な惜作】
*仁王(Act,PS4)
*三国無双7(Act,PS4)
*FF15(ARPG,PS4)
*閃の軌跡Ⅱ,②,③感想,④,⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈(RPG,PS3)
*絶対絶望少女(Act,Vita)
*ジルオールゼロ(Act,PS3)
*ブレスオブファイヤ5(RPG,PS2)
*ドラッグオンドラグーン3(ARPG,PS3)
*エスカ&ロジーのアトリエ(RPG,PS3)
*FF13-3ライトニングR(RPG,PS3)
*テイルズヴェスペリア、②感想(RPG,PS3)
*Tree of Savior(ARPG,ネット)
*ECO(RPG,ネット)
*タルタロス、②、③(ARPG,ネット)
*歴史物(小説・漫画)
独自性、戦闘操作性、快適か
ストーリー、キャラ、デザイン
音楽、画質、難易度で評価
【プレイ日記】
★スクエニのゲームの感想
*いけにえと雪のセツナ
(1), (2), (3), (4), (5)
クリア後の感想
Amazon工作疑惑
★任天堂ゲームの感想
*スプラトゥーンの日記
S以上・96凸ギア立ち回り戦略
おすすめ武器
C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A
マップざっくり考察
★ファルコムゲームの感想
*東京ザナドゥの日記
ネタバレは少なめのつもりです
1話, 2話, 3話, 4話, 5話,
幕間, 6話, 7話, 最終話
クリア後の感想
*閃の軌跡Ⅱ
*①,②,③クリア後レヴュー,④,
⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈
*その他
*空の軌跡,零の軌跡
*Ysシリーズ
*ぐるみん
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
主観多々。世界観重視。
厨二ファンタジーと美男美女が好き。
【個人的な神作品】
*ICO(Act,PS2等)
*風ノ旅ビト(Act,PS3)
*rain(ADV,PS3)
*Demons&DarkSouls(Act,PS3)
*DarkSouls2(Act,PS3等)
*ラストオブアス(TPS,PS3)
*428(ADV,PSP等)
*シュタインズゲート(ADV,PS3等)
*空の軌跡,零の軌跡(RPG,PC等)
*ペルソナ5(RPG,PS4)
*ジルオール(RPG,PS2等)
*幻想水滸伝1-3(RPG,PS等)
*シャドウハーツ1&2(RPG,PS2)
*月下の夜想曲(Act,PS等)
*Ysシリーズ(ARPG,Vita等)
*逆転裁判(ADV,DS等)
*キングダムハーツ(RPG,PS2等)
*GTAシリーズ(TPS,PS3,ceroZ)
*ウィッチャー3(RPG,PS4,Z)
*スプラトゥーン(TPS,WiiU)
*華アワセ(乙女ゲーム,PC)
【個人的な秀作】
*ホライゾンゼロドーン(Act,PS等)
*FF5(RPG,SF)
*DQ5(RPG,SF)
*モンハン2G(Act,PSP)
*デビルメイクライ4(Act,PS3)
*アサシンクリード(Act,PS3,Z)
*アンチャーテッド(TPS,PS3)
*IQ(パズル,PS)
*TRICK&LOGIC(ADV,PSP)
*零~zero~(ADV,PS2)
*零~濡鴉の巫女~(ADV,WiiU)
*SIREN(Act,PS2等)
*ぐるみん(Act,PSP&PC)
*ダンガンロンパ1&2(ADV,PSP)
*プロジェクトディーバ(音楽,etc)
*龍が如く4(ADV,PS3)
*東方・紅魔城伝説2(Act,PC)
*式神の城(Stg,PS2)
*ペルソナ4(RPG,PS2等)
*大神(RPG,Wii等)
*ニーア・レプリカント(RPG,PS3)
*メタルギアソリッド(Act,PS等)
*dokuro(ADV,Vita)
【個人的な惜作】
*仁王(Act,PS4)
*三国無双7(Act,PS4)
*FF15(ARPG,PS4)
*閃の軌跡Ⅱ,②,③感想,④,⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈(RPG,PS3)
*絶対絶望少女(Act,Vita)
*ジルオールゼロ(Act,PS3)
*ブレスオブファイヤ5(RPG,PS2)
*ドラッグオンドラグーン3(ARPG,PS3)
*エスカ&ロジーのアトリエ(RPG,PS3)
*FF13-3ライトニングR(RPG,PS3)
*テイルズヴェスペリア、②感想(RPG,PS3)
*Tree of Savior(ARPG,ネット)
*ECO(RPG,ネット)
*タルタロス、②、③(ARPG,ネット)
*歴史物(小説・漫画)
独自性、戦闘操作性、快適か
ストーリー、キャラ、デザイン
音楽、画質、難易度で評価
【プレイ日記】
★スクエニのゲームの感想
*いけにえと雪のセツナ
(1), (2), (3), (4), (5)
クリア後の感想
Amazon工作疑惑
★任天堂ゲームの感想
*スプラトゥーンの日記
S以上・96凸ギア立ち回り戦略
おすすめ武器
C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A
マップざっくり考察
★ファルコムゲームの感想
*東京ザナドゥの日記
ネタバレは少なめのつもりです
1話, 2話, 3話, 4話, 5話,
幕間, 6話, 7話, 最終話
クリア後の感想
*閃の軌跡Ⅱ
*①,②,③クリア後レヴュー,④,
⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈
*その他
*空の軌跡,零の軌跡
*Ysシリーズ
*ぐるみん
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
PR
BUSTAFELLOWS(バスタフェロウズ)のネタバレOn/Offありの感想
(未プレイの方にも読んで頂ける文章のつもりです)。
多少ネタバレが漏れてしまっているかもしれないので、お気にされる方はお戻り下さい。
あと、公式サイトや体験版(第一章)や第二章の内容から勝手に妄想しちゃってる事なんかは入ってます。
私はこの作品をサスペンスとして分類して感想文を書きましたが、本格推理物ではないですが事件の謎を追う物語としてミステリに分類した方が良かったのかもしれません。
乙女ゲームのバスタフェロウズを只今プレイ中です。真相未クリアです。(→ネタバレありのタブ内はクリア後に記載しました。)
このバスタフェ 、エンターテイメントとしての完成度が高いです。普通に面白い!萌えなくても面白い。TVドラマ感覚で楽しめます。乙ゲはやや苦手で「普通のゲーム」を探してる方々にもお勧め出来ると思います。
今までも手軽な乙ゲを紹介してと頼まれて「サイドキックス」を挙げて好評を得る事は度々あったのですが…、バスタフェはそれ以上の完成度と思います!
(ストーリーも演出もキャラも良い。欠点はシステムが最悪な事と恋愛描写がやっぱり少し下手…というかテーマが乙女ゲームに合ってないと思いました。各エピソードは面白いが、全体構成がよくあるパターンでややオリジナリティが不足しているかなっと。乙ゲ界では評判が良いようで自分がこの手の話に片っ端から手を出してるだけかも)。
バスタフェはサイドキックスと同じ会社で同じ世界観を維持されています。
バスタフェはストーリーの出来が良く更に一般受けの方向性です。乙ゲというより普通の青年漫画とTVドラマ感覚で万人が手軽に楽しめると思います。テーマは「ペルソナ5」に似ていると思いますが、ペルソナより更にライトな方向です。主人公もメインキャラも「社会人なりたての初々しい『正義感』と『必要悪』の両立で葛藤する」という主題を描いています。誰もが共感できる普遍的なテーマですよね。厨二病に近いですが、社会性との両立を目指すという意味では掘り込みも現実的で浅くライトなキャラクター性と思います。答えの出ない問題と向き合いすぎて鬱になるといった暗さもあまりありません。ドラマの「踊る大捜査線」とか「半沢直樹」とか漫画の「ブラックジャック」のような感覚で楽しく爽やかに読み進められると思います。
演出も男性向けの人気作のようにスチルが動きます。数が出ない女性向けでは珍しいですよね。スマホ市場の伸びに上の会社が大きく期待して出資してくれたりしないとここまで頑張ってもらえないと思いました。
UIもお洒落です。文章も軽く読み易く、展開も早く、シリアス面は泣けますし、適宜コミカルなノリでバランス良くお手軽に楽しめます。
女主人公も守られではありますが、彼女も人を助けるスキル持ちなので、そこまでクセの強い方ではないかなと思います。ただ明らかな危険にも突っ込みますし、守られるのが当然だと思ってる、男性陣が高スペックなので女主人公が魅力少ないお馬鹿さんには見えます…。(私は主人公をあまり気にしない方です)。
ああ、忘れていました、女主人公ボイスありです。OnOff切り替え可能です。21歳という設定よりも幼い思考の主人公なので気になる人は気になるかもしれません。高校生くらいかな。今後はボイスありも増えてくるかもしれませんね。スマホゲームだと電車通勤の社会人層も狙い易いと思うので第三者視点のユーザーを開拓する方が購買力もあり未来を描きやすいと思います。
今気づきましたがテウタは大卒じゃないんですね。学校にも行かず21歳で企業に入らずフリーなんてやってる…。スタッフがそういう環境だったんでしょうけど、その経歴じゃあ名家出身の弁護士とかの家族とは価値観が合わず所帯を持つのは向かないでしょうね…。個人的にはテウタのお馬鹿っぽい価値観には少々違和感がありました。
恋愛面についても普通の社会人男性との純愛を爽やかに描いています。
経験値がそれなりにある年上の男性達が、乙ゲの理想像のように、主人公を妹のように丁寧に大事に甘やかして守ってくれるので、とても爽やかに描かれています。多くの女性が夢に描くドラマのようなロマンチックな関係性が描かれていると思います。主人公を性的対象というより小動物感覚で可愛がる物という扱いの男性陣をどうやってその気にさせて一線を踏み出させるか…みたいな攻略感覚でしょうか。サスペンスが書きたくてついでに恋愛を後から足したようなストーリーなので、主題と恋愛が関係ない点はあります。
少し不満を述べるならば、一応全員社会人という設定ですが、どのキャラも精神年齢は設定よりもやや低めです。モズはしっかり者なので年齢以上かもしれません。シュウはそもそもファンタジーなので年齢がとかいう問題でないかも。何故低く感じるのか、原因はスタッフの方向性が「現実にあり得るようなリアリティのある恋愛」を描く方向ではなく、「恋愛を夢見る層に向けた夢物語の騎士様との恋愛」を描く方向性だからと思います。欠点の少ないキャラばかりを並べた弊害かと…。学生層や、酸いも甘いも漁り尽くした40代以上がメインターゲットの作風かなと思います。現実でも恋愛が進行中の社会人層にはやや響かない可能性があるかな、と感じました。
キャラクターも多くの女性に受けるように社会性の高い、スペックも良い、素晴らしい男性ばかりです。危うい正義感を掲げる点はやや心配ですが、そこはフィクションなのでどうにかなります。
むしろ、欠点が少ない点が欠点と言いますか…、例えばアダムは完璧過ぎる点が唯一の欠点と作中でヘルベチカに評されています。個人的にはモズが完璧過ぎるかと…、公式のダウナー設定が霞むレベルで…、知名度高く一般人気の高い福山さんですし公式は一般層も狙っているのでしょうか。料理上手、面倒見よい、誰とも揉めない社交性、家族想い、家庭的、イケメン、医者、公務員、仕事熱心、若手のホープ、更にはそこそこ優しくそこそこドライで現実的でメンタルも強く頼れるタイプ…身長が低めな以外は良物件過ぎです(笑)
以上、総合的に高い水準です。
ところが、…システムは最悪です…!控えめに言ってクソ仕様です。
スタッフはストーリーや演出に自信があり、好みの属性でないキャラクターとも恋愛して欲しいという希望があったようには思いますが…、強制的に長い共通ルートを何度も見させられて、ユーザーからすると単調な作業時間が長引くだけで迷惑でしかありません。最速スキップで各キャラの√解放にそれぞれ1時間位かかりました。ミニゲームもないので完全に作業でした。
攻略方法も分かり難いし、黒色選択肢は見難いし、なぜ選択肢ジャンプが章を跨いで使えないのか、そもそもシーン切り替えにスキップモードですら時間がかかり過ぎる。と文句しかありませんでした。
…という事で少し攻略のコツなど書いてみたいと思いました。
このシステム面さえ無ければ多くのプレイヤーが楽しめるゲームと思うので、正直勿体無いです。乙ゲ業界はコンシューマーでは近年数が出ずに採算化が難しくなってますので新規ユーザーが増えて欲しいと期待しています。個人的には口コミ評価が分かり易いコンシューマーや買いきりでないと気分が乗らず手を出せません。
以下、各キャラの雑感。体験版での印象です。ネタバレ少なめのつもりです。
個人的には公式HP一見した時点でアダム推しです。次にモズが好みでした。体験版の時点で完璧過ぎるアダムが更に気になります、謎の法則によると何かありそう…(笑)
(1)リンボ
弁護士。
『責任感あり、人の中に自分を認識、孤独』

公式HPではややアッパーよりかなという印象でしたが、体験版をプレイすると普通の少年漫画の主人公キャラだなあ、社会人厨二病だなあといった印象でした。普通の社交性高い社会人男性なのでリアルな恋愛感覚でドキドキ出来ました。リンボが声掛けたメンバーらしく一応リーダーっぽい立ち位置なのかなと思います。
他のキャラよりも正義感に危うさを感じます。どこかまだ熱血少年のようです。挫折をしきってないお坊っちゃん感というか、自信家というか…。基本はどんな状況でも笑ってます。社会人になって現実に打ちのめされる人も多いと思うので、共感をしやすいキャラと思います。
ネタバレありの文章…リンボについてはスタッフのケアレスミスが気になってしまい辛口長文です。気になるかもしれない方は読まないで下さいませ。
「熱血」「ヒーロー」「リーダーシップ」「直球」「社交的」「厨二病」「常識人」
sideAでリンボがテウタにかける一声、「お前が居ないと俺は生きていけない」。切迫した状況であれだけの事を言って他者を勇気付けられるリンボは御伽噺の王子様そのものにカッコ良かったです。
リンボは元々キャラが厨二病患者で、実際より若い考え方をするお坊ちゃんなんですが、背景設定も社交性ある弁護士だったり、髪型もキャラデザも普通のイケメンだったりで、けっこう現実みのあるキャラクターでした。特に変わった性癖も無い様でデートの手段や雰囲気の盛り上げ方もごく普通の一般的なデートの方向性です。
個別√のsideBでは、この中途半端なリアリティが仇となって、リンボ編のテウタも非常に幼い考え方をしているように感じられ、我儘に感じてしまいましたし、そもそもリンボも気が利かないように感じられました。
家族ぐるみで付き合いの長いシェフのレストランに付き合って早々の女の子を付き合わせるリンボも、女を試すようで20代後半の男性としては非常に自分勝手に感じました。
そして、テウタも成人した社会人、21歳なのですから、家族ぐるみの付き合いのある古い友人を紹介されるのであれば、靴は履き慣れたヒールのない靴にすべきとも思いますし、シェフがもてなしてくれた料理を楽しんで味合わないのはマナーがなく、私個人の考え方では社会人として言語道断の態度でした。
リンボは名家の跡取りで、性格はキツイものの愛情深いお姉さんを尊重している、ご両親も同様に尊敬しているからこそ、あれだけ真っ直ぐに挫折も知らずに育ったのだと感じられます。なのでその男性と真剣に向き合うのであればテウタはそのご家族とご友人も尊重しなければならない。その点から考えるにあの二人は価値観が合わず将来の関門を乗り越える事は出来ないのではないかと思えてしまいました。もしも私がリンボの両親であれば、友人に対して気遣いの出来ない女は嫁として認めません。(私はどちらかというとリンボと同世代ですよ;)
乙ゲに要求する項目ではないですが、恋愛はおままごとでも綺麗事ばかりではなく、異なる環境で育った男女がお互いの価値観を擦り合わせていく、将来への事前シミュレーションです。そこには二人だけの自己満ではなく、支えてくれる周囲への配慮が必要なはずです。社会性が高い二人というキャラ設定が崩壊してます。私にはこの乙女ゲームは恋愛を描こうとしている作品に感じられなくなってしまいました。恋愛を夢見る層への妄想を垂れ流している作品です。まあそれこそが乙ゲなんでしょうが…。だとしたら、最初から舞台を夢世界にして、職業も独自の物にして、ヤンデレ属性を入れるなどファンタジー要素を前面に出して欲しかったです。誰もが経験した事のある日常のレストランデートでの我儘は冷めます…。世の女性は現実では様々な忍耐を偲んで生きているのですから、ユーザーを馬鹿にしているように感じられました。
以上からリンボのキャラ設定はレストランに行った事のない若い学生層がターゲットだと考えられます。
せっかくスマホでもリリースして、癖のない外見に、感情移入しやすい純粋なキャラクター性、20代後半の働き盛りの社会人…という方向性…。うーん、スタッフのマーケティング能力が中途半端で実に勿体ないかなーと思いました。リンボはパッケージに使っているように一般層狙いの呼び込みキャラの位置なんですよね…。そこで購買力の高い社会人層をばっさり切り捨てるのは現状の業界縮小を想定すると少し厳しいかな、と個人的には思いました。苦しくなる一方の業界ですのでしっかりマーケティングを練って、どの層をターゲットにして、どうお金を貰い、どんなサービスを提供するのか…きちんと勝てる戦略を立てて頂きたいと思いました。
別にサスペンス重視のノベルゲームで、恋愛要素はオマケ程度で売れるなら、(私は買わないけど)それでも良いです。ただ描くのであれば、少しの設定で修正出来るようなケアレスミスは、スタッフ間で指摘し合って補修して欲しいです。
とやや辛口なのも、一定以上にこの作品を評価して、一消費者として次の作品を期待させてもらっているからだと思います。
(2)シュウ
殺し屋。
『冷静な視点で、客観的判断力がある』

公式HPではタバコを吸う男性は苦手だろうなーと思いましたが、体験版プレイしてキャラを把握するとむしろ麻薬やアル厨という設定でなくて良かったと思いました…。
けっこう刹那的な危うさのあるキャラです。共通√の序盤、チャプター2で既に泣けました。
ハードボイルドでワイルドです。頼り甲斐のある武闘派で、身体張って守ってくれるんでトキメキます。彼に惚れ込んじゃうユーザーは多いのではないでしょうか。
理想のカッコいい男性像を夢のままに描いたキャラの様に感じます。
「ツンデレ(軽度)」「クール」「無表情」「皮肉屋」「ワイルド」「俺様」「刹那的」「ロマンチスト」
強引なところがカッコいいです。髪型と眉毛は好みじゃないんですが、その他はとってもカッコ良い。外見さえ自分好みだったらハマれたかもなあって思っていました。
リンボやモズは、弁護士だったり医者だったりと、キャラ設定も背景も職業も現実的な面が強いですが、シュウは殺し屋なので完全にファンタジーの世界の住人です。
なので、現実を忘れてゲームの世界に没頭出来ました。あと私は強引な男性が好みなので、シュウの恋愛へのアプローチはけっこう好きでした。身体はって必死に守ろうとしてくれて、しかもワイルド…かっこ良いです。
テウタは次々にこれでもかと危険に突っ込んでいきますが、既に音声も切っており淡々と読んでいたので、特に気にならずに済みました。
sideAの最後のキスシーンは、しっかりリードしてくれて、ワイルドなオスっぽさがあってドキドキしました。
sideBの雪だるまイベント、テウタ可愛すぎて泣けました。私の中のベストオブテウタでした!!ヤンもいい奴!俺女!
(3)ヘルベチカ
美容整形外科医。
『自立したいが、感情的で人に固執する』

外見もキャラも一番特徴があると思います。中性的な感じがします。立ち位置は王道の軟派キャラなんですが、スタッフの好みなのか静かな気合を感じます。
好みが分かれるクセの強いキャラと思うので完全な一般受けを狙うなら彼は居なくても話は成り立つかなとも一瞬思ったのですが、何気に一番義賊っぽいスキルを持ってます。コア層狙いのキャラなのかな。乙ゲというジャンルが好きな人は好きなタイプと思います(笑)。
ドライな性格かと思えば意外と熱いところがあって、一番ミステリアスだと思います。
公式HPにも書いてますけど彼は記憶がありません。彼の√はその辺の自分探しの内容になります。厨二的なテーマなんですが、切り口がとても面白かったです。人間としてカッコイイ人だと思いました。
「物腰柔らか」「毒舌」「ドライ」「ミステリアス」「ナルシスト」「女性関係」「セクハラ」
5人の個別√と2つの真相√込みで私はヘルベチカ√が面白かったです!
読む前からアダム推しで次がモズだったんですが、結局そんな萌えずに終わったので、純粋に萌え物というよりサスペンス物として読んでました。
順番はモズ→リンボ→シュウ→ヘルベチカ→スケアクロウだったんで、4キャラ目で流石に金太郎飴感はありましたが、ヘルベチカは楽しんで読めました。
リンボ√以外は共通√から殆ど泣きながら読んでたんですけど、ヘルベチカ√はもうずっと号泣でした。誇張なしで10回以上泣いてて、もうページめくるたびに涙溢れてくる感じでした。リアル事情で空き時間10分づつくらいで小刻みに読んでたのにもかかわらず、ずっと号泣!!(涙腺弱い)
自分探しっていうテーマはよくあるテーマだと思うんですが、アメリカのスラム街から成り上がる物語が斬新でした。類似で思いつくのがバナナフィッシュ くらい(?)自分的にはけっこう新しい気分で読めた乙女ゲームのストーリーでした。
シュウの最初の感想で、刹那的なキャラなのに麻薬やってなくて安心したーみたいな事書きましたが、ヘルベチカは思いっきりヤクチュウにされてました…;;お、ここまで突っ込んで表現しちゃう?って感じて、かなり前のめりで読んでました。萌えてないのに、純粋にストーリーで先が気になって、ぐいぐいと物語に引き込まれていってました。辛く苦しい過去があっても目を逸らしたくても今後の為に向き合っていく…。ヘルベチカはキャラデザがそんなに好みじゃなかったんですが、ストーリー上の格好良さは私の中ではナンバーワンになりました!
危険に突っ込んで守られるテウタにもうけっこうウンザリしてたけど、まあ、そこは出来るだけ無かった事として忘れるように気にしないように読んでました。
sideAはそんな感じで号泣しながら読めてて、その勢いでsideBも読んだのでまた泣きながら読んでました。
キスしてきゃー(。>∀<。)とか言って読んでたけど、読み終わったら、結局特に萌える事もなく、妄想する事もなく…。単純にストーリーが好きだっただけみたいです。まあ、外見も性格属性もそんな好みのタイプじゃないから仕方ないのかな…。話にハマってる間は萌えれるかもって思ったんですけど(涙)。
(4)モズ
検死官。
『人間関係は苦手で、探究心が強い』

公式HPではダウナーっぽく表記されてますが体験版の時点で普通のクーデレです。前述しましたが身長以外は完璧過ぎる理想物件。高学歴理系エリートって現実でも専門用語で日常会話するダメ人間はいくらでも居るので…自分の周囲と比較すると普通に社交性が高い人だと思いました。
私はキャラに介護されるのも介護するのも大好きです。リアルでも料理好きはポイント高いです。
「一応ダウナー」「クーデレ」「完璧」「温厚」「家庭的」「世話焼き」「苦労人」「シスコン」
料理上手で面倒見よく家族想いで仕事熱心…。完全完璧っス。他のキャラの√ではとにかく常識人でテウタを思いやってくれる。
…なんですけど、どうも完璧過ぎて…、なんでしょうね、あんまり獣っぽさが感じられない点だけが残念でした。この作品の全キャラに言えるんですけど、テウタに対して家族愛だったり妹として見てる部分が強いのでエロくないんですよね…。私は人間なんて一皮剥いたらケダモノだと思ってる節があるんですが、どうもその生物らしさがあまり無いかな…と感じました。少なくとも一対一のシーンだともっとエゴを出してくれても良いと思います。男性に女性があまりに甘えて我慢させていると、結局は自分の幻想に恋をしているだけで、相手は疲れてしまうんじゃないかな…とか心配しちゃいました。恐らくモズは自分に劣等感を抱いてる、そこをテウタには理解して貰いたいと他人事ながら思ってしまいました。
でも、とにかく冷静で常識人のモズはデートもそつなく、気遣いも上手で、親から見た理想の愛娘の婿候補だと思います(笑)
こういう男性を選べる人が、幸せになれる女性と思います。
モズはテウタに告白する際に、過去の罪を告白しています。個人的にこのエピソードは面白かったです。価値観は人それぞれ異なり、経験も立場も異なるので、男女でお互いの価値観が完全に一致する事はあり得ません。二人は関係性を進めるにあたり、価値観の不一致を乗り越えなければなりませんでした。
そのハードルを若い情熱のまま、やすやすと乗り越えてしまった為にモズとテウタの関係性はもはや恋人というより家族のような利害共同体になってしまったのかな、とも感じられました。
(5)スケアクロウ
引きこもりハッカー。
『壁を作らないで距離を詰めるのが上手』

素直で可愛いです。一歳上ですが弟キャラ。他のキャラは普通に社会人っぽく一定の壁を保つクールな面があるので、クロが素直でイジられ役になる事でメンバーの仲を繋いでる印象を受けました。彼のおかげで仲の良い飲み友達っぽいワチャワチャ感が楽しめます。リアルに大事にしてあげたい性格です。
家主で仕事を見つけてくるので、一番居ないとストーリーが成り立たない立ち位置と思います。
「ムードメーカー」「弟系(歳上設定)」「純情」「照れ屋」「ヤンデル(超軽度)」「天才」
私は乙女ゲームのショタがやや苦手でして…、スケアクロウは歳上ながら弟キャラなんで、攻略キャラの中じゃ淡々と読んでた方だと思います。
お父さんと電車の中に居る間は泣きながら読んでましたけど!
過去の悪行と向き合うってパターンが個別√はリンボ&ヘルベチカ&スケアクロウが一緒で金太郎飴感が強かったです。同じ構成のストーリーだったら、個人的には麻薬中毒にまでなったヘルベチカの方が衝撃的だったんだと思います…(泣)。
sideBはショタで読んでられるかなって心配だったんですが、泥んこ遊びしてたとことか普通に楽しんで読めた!モズお母さんきた( ^ω^ )とか別の面で喜んでた気もしますが…(家庭的なキャラ好き)。
(6)
「完璧」「幼馴染」「一途」「過保護」「非恋愛√」「バッドのみ?」「ヤンデレ」「ヤンデル?」「殺害」

結論から言うと…最終的な結末は公式HPを最初に見た時から想定してた結末でした…、なので何も意外な要素なく、正直ガッカリしました。
途中で結末をいろいろ考えながら読んでいて、アダム普通に生き残って普通にテウタとくっついたら詰まらないなーとか、そもそもルイロペスの弟はアダムだろうなーって予想したりしてたり、もしかしたらアダムは最終的に狂ってリンボ達を殺しちゃったりしてーとか、テウタを襲って来たりしてーとか、お兄ちゃんが蘇ってきたりしてーとか、もっと色々最悪のケースを想定してたんで、実際真相√読んで、ああお兄ちゃん殺しただけかーとか思ってました。いや、視界もままならないまま、発狂していくアダムが可哀想で号泣してましたけど(涙腺弱い)、でもどっかで物足りないなーもっとグロい結末下さいって思ってました…(鬼)。
でも、きちんと最後にアダムが死んだような死んでないような結末にしてくれた点は評価してます。生き延びてテウタとくっついてたらきっとデートの演出が相当魅力的じゃないと不満だったと思うし、その恋愛描写の実力はこのスタッフチームには無いだろうと思います…;;
シャドウハーツ1と同じような結末だったので、続編は是非シャドウハーツ2のような展開でお願いしたいと期待しちゃってます。シャドウハーツ1はヒロインが自己犠牲の後に肩にもたれかかって眠るように移動中の車内で死んじゃいます。シャドウハーツ2は死後半年たってその死を受け入れられずに苦しむ男主人公が描かれます。
スタンドバイミーもモチーフのようですので、クリス君(リバー・フェニックス)の死もきっと掛かっているんでしょうね…。あれは今でも辛く悲しい出来事でした。
この真相編、よくあるタイプだなって思ってたんですけど乙女ゲームでいうと蝶毒に似てる気がします。属性考察をすると殺害要素、幼馴染、ヤンデル、嘘つき、完璧系、社交的、サスペンス、真相…と似通っているなあと一度思ってしまうともう、そう見えてしまいました…。もしも、ルイロペスのボスだったらもっと似てましたね…別の真相でそこは良かったかもしれません。
スタンドバイミーがモチーフだと分かって…私が(モズを除いて)リンボ達皆もテウタも精神年齢が低い点を気にしていた点の謎が解けました。もともと作者は12歳くらいを想定して描いていたんですね…。
そして、テウタも攻略キャラ達もみんな雄っぽさが無いと不満を述べていた点も同時に解決しました。作者は『無償の愛』を描きたかったんだと…。だから、この作品のテーマは男と女が出会って愛を育む物語ではなく、そもそもリアルな社会人の恋愛を描く気も無かった。これは、家族愛・友情の物語だったんだなあと分かりました。恋愛描写が苦手だと割り切った上で、サスペンスに友情を入れ込んだら面白いだろうと…。ええ、サスペンスとしては非常に面白かったです。乙女ゲームの中でも私の中ではトップに近い文章力でした。ただ、恋愛物としては少し物足りないですし、萌えれなかった点は残念でした。私はスタンドバイミー単体はとても好きなんですが、それは乙女ゲームではないジャンルで勝負して欲しいテーマかなと思いました。
アダムの属性ですが、なかなか難しいです。殺害という違法行為をしている点、それが主人公への想い故である点、そもそも脳腫瘍(?)で病気になっていて、ついには精神まで壊れていく…と項目を挙げていくとヤンデレだと思います。
ただ主人公が認識しておらず初登場時から病んでいるキャラはヤンデルに分類される事が一般的です。優しいキャラに萌える読者が意味不明な発狂に引く事が多いからだと考えています。だから初登場から病んでいるアダムは「ヤンデル」の一面が強いと客観的には分類します。
アダムについては普段の常識人っぷりがこれでもかとアピールされている点、狂いきる前に主人公への一途な想いも説明されている点から、ヤンデレが苦手な一般層に受け入れられやすく作られていると思います。なので定義上というより、読者目線で考えると「ヤンデレ」にカテゴライズされるキャラかなと思いました。
私は幼馴染好きなので好意を抱いた年月の長さから考えても、テウタとのカップリングはどうしてもアダムを推してしまいます。ストーリーが好みでなかろうが無償の愛に萌えなかろうが、テウタにアダムを忘れては欲しくないと感じました。その死を乗り越えて最終的に別の人と結ばれるとしても、その想いを受け止める時間をテウタに作って貰いたいと思いました。
今更ながら世間の感想をほんの少しだけ読んだのですが、真相がハッピーエンドじゃなくて嫌だという声が多い事に驚きました…。私は真相編ではバッドエンドな事だけを高評価してそれ以外の独創性の無さを低評価していたのですが、改めて自分はこの作品のターゲット層では無かったと痛感した次第です…。
大きな声で言い辛い自分の思いをここに書かせてもらいます。様々な意見がある事は良い事ですが、独自性や物語性を求めるユーザーが業界から離れていく…という実情を察しました…。個人的にはテンプレを壊す気概の無い作品はプレイしたく無いので、真相をバッドエンドにした、アダムが攻略キャラにならないという点がこの作品の全体構成の最大の長所だと考えています。
とはいえ、バスタフェのプレイヤー層は爽やかな幸せ物語を願う層が多いようなので、単純にビジネスを考えるならば、アダム√はここまでガチガチの攻略制限を設けなくても良かったのかもなあと感じました。ここまで愛の深い幼馴染の悲劇を真相扱いにしてしまうと、「じゃあ今までの他の攻略キャラと愛を育んだ世界線は何だったの?」「もう感情移入しちゃってるんだけど?」というモヤモヤは残りますしね。誰か一人攻略したら、ルイロペス事件√とお兄ちゃん事件√が読めるという程度の攻略制限だった方が、ユーザー自体もハッピーエンドでプレイを終えるか、悲恋で終えるかを選択出来ますので、そちらの方が『ゲーム性』という意味でも、より多くのプレイヤーの需要に応えるシステムになったのかもしれません。
もしも、アダムが生き残ってハッピーエンドを迎えてしまったら、バスタフェはここまで話題になる事はなかったのかなと思います。乙ゲメーカーとしては大手では無いわけですし、バッドエンドで勝負するくらいの覚悟がスタッフに見受けられたからこそ、応援してあげたいというファンも増えて、ここまで口コミは盛り上がったのだと感じています。
(バスタフェの攻略方法をいろいろ考察して纏めたのは、あの時点では私が最初だと考えています。グーグル検索やツイッターや板などは閲覧していましたが、あの時点ではどの選択肢を選んだかというざっくりした内容しか語られていなかったと思います。とはいっても、このブログはそもそもメインコンテンツは男性向けの超高難易度アクションの攻略サイト(笑)ですので乙ゲのキーワードでグーグルAIに弾かれていたくらいのしょぼしょぼサイトなんですが...一応2020年2月の1ヶ月でバスタのページにもそこそこ反応頂いております。)
売上ランキングにはカウントされておらず、中古市場メインと考えてもバスタフェを2月にプレイした新規ユーザーの総数は1000人を超えるのではないかと私は想像しています。Switch初週の売上数は3000という弱小ネームバリューの作品としては、これは偉業と言っても良いのではないでしょうか。新型コロナ騒ぎもプラスには働いて、もしかしたらアプリ版や中古版のユーザー含めたら5千や1万という大台を超える可能性もあるかもしれません。ゲーム業界の片隅にでも乙ゲ作品が生き残ってくれる事を期待させていただきたいと考えています。
【プレイを終えての総評】
私はプレイ済みの乙女ゲーム50タイトル程度のライトユーザーです。総合板などよく見てるので未プレイのゲームもユーザー層はそこそこ把握してる方かもしれません。ただ、乙女ゲームでは優しいキャラや純愛が苦手でして…それが原因で合わないキャラは多い方です(一般ゲーではむしろ優しいキャラが好物)。なので、殆どの乙女ゲームはスキップモード速読を多用します。使ってないゲームは4タイトルくらいです…。このゲームは攻略作業以外ではスキップは使用していません。全文をゆっくり読んだ乙女ゲームは私としては史上5作目となります。ですので、恋愛描写が微妙とか、ゲームに求めてる物が違うとか、ストーリーが好みだったキャラと萌え属性が合わないとか、文句タラタラな文面ではありますが、私はこのゲームを高評価しています。私の好み属性は乙女ユーザーの中ではやや特殊な方ですので、おそらくバスタフェロウズは一般層含めた多くの女性が楽しめる作品だと考えています。
真相のストーリーや属性があまり合わなかったので、最終的には元々好み属性のモズ推しなのかなー…(?)。真相も想像の範囲内過ぎたという点以外では面白かったですし、悪くはないと思っています。私の中ではテウタはこの後しばらく真相の結果を受け止めて生きていくんだろうな、という妄想でいっぱいです。どのルートでも数回以上号泣しながら読めていたんで、誇張なしに10回は涙をポロポロ流して読んでいました。萌えはともかくストーリーは面白かったです。全体構成はもう少しオリジナリティが欲しかったと思いました。
---------------------------------
*乙女ゲーム目次
*歴代乙女ゲームおすすめランキング
*蝶の毒華の鎖感想(ネタバレなし)
*ハトアリシリーズ感想(ネタバレ全開)
*バスタフェロウズ攻略方法
*華アワセ感想(ネタバレなし)
*華アワセ(いろは編と全編)考察と感想(ネタバレ全開)
*一般ゲーム感想まとめ
---------------------------------
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
(未プレイの方にも読んで頂ける文章のつもりです)。
多少ネタバレが漏れてしまっているかもしれないので、お気にされる方はお戻り下さい。
あと、公式サイトや体験版(第一章)や第二章の内容から勝手に妄想しちゃってる事なんかは入ってます。
私はこの作品をサスペンスとして分類して感想文を書きましたが、本格推理物ではないですが事件の謎を追う物語としてミステリに分類した方が良かったのかもしれません。
乙女ゲームのバスタフェロウズを只今プレイ中です。真相未クリアです。(→ネタバレありのタブ内はクリア後に記載しました。)
このバスタフェ 、エンターテイメントとしての完成度が高いです。普通に面白い!萌えなくても面白い。TVドラマ感覚で楽しめます。乙ゲはやや苦手で「普通のゲーム」を探してる方々にもお勧め出来ると思います。
今までも手軽な乙ゲを紹介してと頼まれて「サイドキックス」を挙げて好評を得る事は度々あったのですが…、バスタフェはそれ以上の完成度と思います!
(ストーリーも演出もキャラも良い。欠点はシステムが最悪な事と恋愛描写がやっぱり少し下手…というかテーマが乙女ゲームに合ってないと思いました。各エピソードは面白いが、全体構成がよくあるパターンでややオリジナリティが不足しているかなっと。乙ゲ界では評判が良いようで自分がこの手の話に片っ端から手を出してるだけかも)。
バスタフェはサイドキックスと同じ会社で同じ世界観を維持されています。
バスタフェはストーリーの出来が良く更に一般受けの方向性です。乙ゲというより普通の青年漫画とTVドラマ感覚で万人が手軽に楽しめると思います。テーマは「ペルソナ5」に似ていると思いますが、ペルソナより更にライトな方向です。主人公もメインキャラも「社会人なりたての初々しい『正義感』と『必要悪』の両立で葛藤する」という主題を描いています。誰もが共感できる普遍的なテーマですよね。厨二病に近いですが、社会性との両立を目指すという意味では掘り込みも現実的で浅くライトなキャラクター性と思います。答えの出ない問題と向き合いすぎて鬱になるといった暗さもあまりありません。ドラマの「踊る大捜査線」とか「半沢直樹」とか漫画の「ブラックジャック」のような感覚で楽しく爽やかに読み進められると思います。
演出も男性向けの人気作のようにスチルが動きます。数が出ない女性向けでは珍しいですよね。スマホ市場の伸びに上の会社が大きく期待して出資してくれたりしないとここまで頑張ってもらえないと思いました。
UIもお洒落です。文章も軽く読み易く、展開も早く、シリアス面は泣けますし、適宜コミカルなノリでバランス良くお手軽に楽しめます。
女主人公も守られではありますが、彼女も人を助けるスキル持ちなので、そこまでクセの強い方ではないかなと思います。ただ明らかな危険にも突っ込みますし、守られるのが当然だと思ってる、男性陣が高スペックなので女主人公が魅力少ないお馬鹿さんには見えます…。(私は主人公をあまり気にしない方です)。
ああ、忘れていました、女主人公ボイスありです。OnOff切り替え可能です。21歳という設定よりも幼い思考の主人公なので気になる人は気になるかもしれません。高校生くらいかな。今後はボイスありも増えてくるかもしれませんね。スマホゲームだと電車通勤の社会人層も狙い易いと思うので第三者視点のユーザーを開拓する方が購買力もあり未来を描きやすいと思います。
今気づきましたがテウタは大卒じゃないんですね。学校にも行かず21歳で企業に入らずフリーなんてやってる…。スタッフがそういう環境だったんでしょうけど、その経歴じゃあ名家出身の弁護士とかの家族とは価値観が合わず所帯を持つのは向かないでしょうね…。個人的にはテウタのお馬鹿っぽい価値観には少々違和感がありました。
恋愛面についても普通の社会人男性との純愛を爽やかに描いています。
経験値がそれなりにある年上の男性達が、乙ゲの理想像のように、主人公を妹のように丁寧に大事に甘やかして守ってくれるので、とても爽やかに描かれています。多くの女性が夢に描くドラマのようなロマンチックな関係性が描かれていると思います。主人公を性的対象というより小動物感覚で可愛がる物という扱いの男性陣をどうやってその気にさせて一線を踏み出させるか…みたいな攻略感覚でしょうか。サスペンスが書きたくてついでに恋愛を後から足したようなストーリーなので、主題と恋愛が関係ない点はあります。
少し不満を述べるならば、一応全員社会人という設定ですが、どのキャラも精神年齢は設定よりもやや低めです。モズはしっかり者なので年齢以上かもしれません。シュウはそもそもファンタジーなので年齢がとかいう問題でないかも。何故低く感じるのか、原因はスタッフの方向性が「現実にあり得るようなリアリティのある恋愛」を描く方向ではなく、「恋愛を夢見る層に向けた夢物語の騎士様との恋愛」を描く方向性だからと思います。欠点の少ないキャラばかりを並べた弊害かと…。学生層や、酸いも甘いも漁り尽くした40代以上がメインターゲットの作風かなと思います。現実でも恋愛が進行中の社会人層にはやや響かない可能性があるかな、と感じました。
キャラクターも多くの女性に受けるように社会性の高い、スペックも良い、素晴らしい男性ばかりです。危うい正義感を掲げる点はやや心配ですが、そこはフィクションなのでどうにかなります。
むしろ、欠点が少ない点が欠点と言いますか…、例えばアダムは完璧過ぎる点が唯一の欠点と作中でヘルベチカに評されています。個人的にはモズが完璧過ぎるかと…、公式のダウナー設定が霞むレベルで…、知名度高く一般人気の高い福山さんですし公式は一般層も狙っているのでしょうか。料理上手、面倒見よい、誰とも揉めない社交性、家族想い、家庭的、イケメン、医者、公務員、仕事熱心、若手のホープ、更にはそこそこ優しくそこそこドライで現実的でメンタルも強く頼れるタイプ…身長が低めな以外は良物件過ぎです(笑)
以上、総合的に高い水準です。
ところが、…システムは最悪です…!控えめに言ってクソ仕様です。
スタッフはストーリーや演出に自信があり、好みの属性でないキャラクターとも恋愛して欲しいという希望があったようには思いますが…、強制的に長い共通ルートを何度も見させられて、ユーザーからすると単調な作業時間が長引くだけで迷惑でしかありません。最速スキップで各キャラの√解放にそれぞれ1時間位かかりました。ミニゲームもないので完全に作業でした。
攻略方法も分かり難いし、黒色選択肢は見難いし、なぜ選択肢ジャンプが章を跨いで使えないのか、そもそもシーン切り替えにスキップモードですら時間がかかり過ぎる。と文句しかありませんでした。
…という事で少し攻略のコツなど書いてみたいと思いました。
このシステム面さえ無ければ多くのプレイヤーが楽しめるゲームと思うので、正直勿体無いです。乙ゲ業界はコンシューマーでは近年数が出ずに採算化が難しくなってますので新規ユーザーが増えて欲しいと期待しています。個人的には口コミ評価が分かり易いコンシューマーや買いきりでないと気分が乗らず手を出せません。
以下、各キャラの雑感。体験版での印象です。ネタバレ少なめのつもりです。
個人的には公式HP一見した時点でアダム推しです。次にモズが好みでした。体験版の時点で完璧過ぎるアダムが更に気になります、謎の法則によると何かありそう…(笑)
(1)リンボ
弁護士。
『責任感あり、人の中に自分を認識、孤独』
公式HPではややアッパーよりかなという印象でしたが、体験版をプレイすると普通の少年漫画の主人公キャラだなあ、社会人厨二病だなあといった印象でした。普通の社交性高い社会人男性なのでリアルな恋愛感覚でドキドキ出来ました。リンボが声掛けたメンバーらしく一応リーダーっぽい立ち位置なのかなと思います。
他のキャラよりも正義感に危うさを感じます。どこかまだ熱血少年のようです。挫折をしきってないお坊っちゃん感というか、自信家というか…。基本はどんな状況でも笑ってます。社会人になって現実に打ちのめされる人も多いと思うので、共感をしやすいキャラと思います。
ネタバレありの文章…リンボについてはスタッフのケアレスミスが気になってしまい辛口長文です。気になるかもしれない方は読まないで下さいませ。
ネタバレありの感想(クリックで表示)(辛口長文)
「熱血」「ヒーロー」「リーダーシップ」「直球」「社交的」「厨二病」「常識人」
sideAでリンボがテウタにかける一声、「お前が居ないと俺は生きていけない」。切迫した状況であれだけの事を言って他者を勇気付けられるリンボは御伽噺の王子様そのものにカッコ良かったです。
リンボは元々キャラが厨二病患者で、実際より若い考え方をするお坊ちゃんなんですが、背景設定も社交性ある弁護士だったり、髪型もキャラデザも普通のイケメンだったりで、けっこう現実みのあるキャラクターでした。特に変わった性癖も無い様でデートの手段や雰囲気の盛り上げ方もごく普通の一般的なデートの方向性です。
個別√のsideBでは、この中途半端なリアリティが仇となって、リンボ編のテウタも非常に幼い考え方をしているように感じられ、我儘に感じてしまいましたし、そもそもリンボも気が利かないように感じられました。
家族ぐるみで付き合いの長いシェフのレストランに付き合って早々の女の子を付き合わせるリンボも、女を試すようで20代後半の男性としては非常に自分勝手に感じました。
そして、テウタも成人した社会人、21歳なのですから、家族ぐるみの付き合いのある古い友人を紹介されるのであれば、靴は履き慣れたヒールのない靴にすべきとも思いますし、シェフがもてなしてくれた料理を楽しんで味合わないのはマナーがなく、私個人の考え方では社会人として言語道断の態度でした。
リンボは名家の跡取りで、性格はキツイものの愛情深いお姉さんを尊重している、ご両親も同様に尊敬しているからこそ、あれだけ真っ直ぐに挫折も知らずに育ったのだと感じられます。なのでその男性と真剣に向き合うのであればテウタはそのご家族とご友人も尊重しなければならない。その点から考えるにあの二人は価値観が合わず将来の関門を乗り越える事は出来ないのではないかと思えてしまいました。もしも私がリンボの両親であれば、友人に対して気遣いの出来ない女は嫁として認めません。(私はどちらかというとリンボと同世代ですよ;)
乙ゲに要求する項目ではないですが、恋愛はおままごとでも綺麗事ばかりではなく、異なる環境で育った男女がお互いの価値観を擦り合わせていく、将来への事前シミュレーションです。そこには二人だけの自己満ではなく、支えてくれる周囲への配慮が必要なはずです。社会性が高い二人というキャラ設定が崩壊してます。私にはこの乙女ゲームは恋愛を描こうとしている作品に感じられなくなってしまいました。恋愛を夢見る層への妄想を垂れ流している作品です。まあそれこそが乙ゲなんでしょうが…。だとしたら、最初から舞台を夢世界にして、職業も独自の物にして、ヤンデレ属性を入れるなどファンタジー要素を前面に出して欲しかったです。誰もが経験した事のある日常のレストランデートでの我儘は冷めます…。世の女性は現実では様々な忍耐を偲んで生きているのですから、ユーザーを馬鹿にしているように感じられました。
以上からリンボのキャラ設定はレストランに行った事のない若い学生層がターゲットだと考えられます。
せっかくスマホでもリリースして、癖のない外見に、感情移入しやすい純粋なキャラクター性、20代後半の働き盛りの社会人…という方向性…。うーん、スタッフのマーケティング能力が中途半端で実に勿体ないかなーと思いました。リンボはパッケージに使っているように一般層狙いの呼び込みキャラの位置なんですよね…。そこで購買力の高い社会人層をばっさり切り捨てるのは現状の業界縮小を想定すると少し厳しいかな、と個人的には思いました。苦しくなる一方の業界ですのでしっかりマーケティングを練って、どの層をターゲットにして、どうお金を貰い、どんなサービスを提供するのか…きちんと勝てる戦略を立てて頂きたいと思いました。
別にサスペンス重視のノベルゲームで、恋愛要素はオマケ程度で売れるなら、(私は買わないけど)それでも良いです。ただ描くのであれば、少しの設定で修正出来るようなケアレスミスは、スタッフ間で指摘し合って補修して欲しいです。
とやや辛口なのも、一定以上にこの作品を評価して、一消費者として次の作品を期待させてもらっているからだと思います。
(2)シュウ
殺し屋。
『冷静な視点で、客観的判断力がある』
公式HPではタバコを吸う男性は苦手だろうなーと思いましたが、体験版プレイしてキャラを把握するとむしろ麻薬やアル厨という設定でなくて良かったと思いました…。
けっこう刹那的な危うさのあるキャラです。共通√の序盤、チャプター2で既に泣けました。
ハードボイルドでワイルドです。頼り甲斐のある武闘派で、身体張って守ってくれるんでトキメキます。彼に惚れ込んじゃうユーザーは多いのではないでしょうか。
理想のカッコいい男性像を夢のままに描いたキャラの様に感じます。
ネタバレありの感想(クリックで表示)
「ツンデレ(軽度)」「クール」「無表情」「皮肉屋」「ワイルド」「俺様」「刹那的」「ロマンチスト」
強引なところがカッコいいです。髪型と眉毛は好みじゃないんですが、その他はとってもカッコ良い。外見さえ自分好みだったらハマれたかもなあって思っていました。
リンボやモズは、弁護士だったり医者だったりと、キャラ設定も背景も職業も現実的な面が強いですが、シュウは殺し屋なので完全にファンタジーの世界の住人です。
なので、現実を忘れてゲームの世界に没頭出来ました。あと私は強引な男性が好みなので、シュウの恋愛へのアプローチはけっこう好きでした。身体はって必死に守ろうとしてくれて、しかもワイルド…かっこ良いです。
テウタは次々にこれでもかと危険に突っ込んでいきますが、既に音声も切っており淡々と読んでいたので、特に気にならずに済みました。
sideAの最後のキスシーンは、しっかりリードしてくれて、ワイルドなオスっぽさがあってドキドキしました。
sideBの雪だるまイベント、テウタ可愛すぎて泣けました。私の中のベストオブテウタでした!!ヤンもいい奴!俺女!
(3)ヘルベチカ
美容整形外科医。
『自立したいが、感情的で人に固執する』
外見もキャラも一番特徴があると思います。中性的な感じがします。立ち位置は王道の軟派キャラなんですが、スタッフの好みなのか静かな気合を感じます。
好みが分かれるクセの強いキャラと思うので完全な一般受けを狙うなら彼は居なくても話は成り立つかなとも一瞬思ったのですが、何気に一番義賊っぽいスキルを持ってます。コア層狙いのキャラなのかな。乙ゲというジャンルが好きな人は好きなタイプと思います(笑)。
ドライな性格かと思えば意外と熱いところがあって、一番ミステリアスだと思います。
公式HPにも書いてますけど彼は記憶がありません。彼の√はその辺の自分探しの内容になります。厨二的なテーマなんですが、切り口がとても面白かったです。人間としてカッコイイ人だと思いました。
ネタバレありの感想(クリックで表示)
「物腰柔らか」「毒舌」「ドライ」「ミステリアス」「ナルシスト」「女性関係」「セクハラ」
5人の個別√と2つの真相√込みで私はヘルベチカ√が面白かったです!
読む前からアダム推しで次がモズだったんですが、結局そんな萌えずに終わったので、純粋に萌え物というよりサスペンス物として読んでました。
順番はモズ→リンボ→シュウ→ヘルベチカ→スケアクロウだったんで、4キャラ目で流石に金太郎飴感はありましたが、ヘルベチカは楽しんで読めました。
リンボ√以外は共通√から殆ど泣きながら読んでたんですけど、ヘルベチカ√はもうずっと号泣でした。誇張なしで10回以上泣いてて、もうページめくるたびに涙溢れてくる感じでした。リアル事情で空き時間10分づつくらいで小刻みに読んでたのにもかかわらず、ずっと号泣!!(涙腺弱い)
自分探しっていうテーマはよくあるテーマだと思うんですが、アメリカのスラム街から成り上がる物語が斬新でした。類似で思いつくのがバナナフィッシュ くらい(?)自分的にはけっこう新しい気分で読めた乙女ゲームのストーリーでした。
シュウの最初の感想で、刹那的なキャラなのに麻薬やってなくて安心したーみたいな事書きましたが、ヘルベチカは思いっきりヤクチュウにされてました…;;お、ここまで突っ込んで表現しちゃう?って感じて、かなり前のめりで読んでました。萌えてないのに、純粋にストーリーで先が気になって、ぐいぐいと物語に引き込まれていってました。辛く苦しい過去があっても目を逸らしたくても今後の為に向き合っていく…。ヘルベチカはキャラデザがそんなに好みじゃなかったんですが、ストーリー上の格好良さは私の中ではナンバーワンになりました!
危険に突っ込んで守られるテウタにもうけっこうウンザリしてたけど、まあ、そこは出来るだけ無かった事として忘れるように気にしないように読んでました。
sideAはそんな感じで号泣しながら読めてて、その勢いでsideBも読んだのでまた泣きながら読んでました。
キスしてきゃー(。>∀<。)とか言って読んでたけど、読み終わったら、結局特に萌える事もなく、妄想する事もなく…。単純にストーリーが好きだっただけみたいです。まあ、外見も性格属性もそんな好みのタイプじゃないから仕方ないのかな…。話にハマってる間は萌えれるかもって思ったんですけど(涙)。
(4)モズ
検死官。
『人間関係は苦手で、探究心が強い』
公式HPではダウナーっぽく表記されてますが体験版の時点で普通のクーデレです。前述しましたが身長以外は完璧過ぎる理想物件。高学歴理系エリートって現実でも専門用語で日常会話するダメ人間はいくらでも居るので…自分の周囲と比較すると普通に社交性が高い人だと思いました。
私はキャラに介護されるのも介護するのも大好きです。リアルでも料理好きはポイント高いです。
ネタバレありの感想(クリックで表示)
「一応ダウナー」「クーデレ」「完璧」「温厚」「家庭的」「世話焼き」「苦労人」「シスコン」
料理上手で面倒見よく家族想いで仕事熱心…。完全完璧っス。他のキャラの√ではとにかく常識人でテウタを思いやってくれる。
…なんですけど、どうも完璧過ぎて…、なんでしょうね、あんまり獣っぽさが感じられない点だけが残念でした。この作品の全キャラに言えるんですけど、テウタに対して家族愛だったり妹として見てる部分が強いのでエロくないんですよね…。私は人間なんて一皮剥いたらケダモノだと思ってる節があるんですが、どうもその生物らしさがあまり無いかな…と感じました。少なくとも一対一のシーンだともっとエゴを出してくれても良いと思います。男性に女性があまりに甘えて我慢させていると、結局は自分の幻想に恋をしているだけで、相手は疲れてしまうんじゃないかな…とか心配しちゃいました。恐らくモズは自分に劣等感を抱いてる、そこをテウタには理解して貰いたいと他人事ながら思ってしまいました。
でも、とにかく冷静で常識人のモズはデートもそつなく、気遣いも上手で、親から見た理想の愛娘の婿候補だと思います(笑)
こういう男性を選べる人が、幸せになれる女性と思います。
モズはテウタに告白する際に、過去の罪を告白しています。個人的にこのエピソードは面白かったです。価値観は人それぞれ異なり、経験も立場も異なるので、男女でお互いの価値観が完全に一致する事はあり得ません。二人は関係性を進めるにあたり、価値観の不一致を乗り越えなければなりませんでした。
そのハードルを若い情熱のまま、やすやすと乗り越えてしまった為にモズとテウタの関係性はもはや恋人というより家族のような利害共同体になってしまったのかな、とも感じられました。
(5)スケアクロウ
引きこもりハッカー。
『壁を作らないで距離を詰めるのが上手』
素直で可愛いです。一歳上ですが弟キャラ。他のキャラは普通に社会人っぽく一定の壁を保つクールな面があるので、クロが素直でイジられ役になる事でメンバーの仲を繋いでる印象を受けました。彼のおかげで仲の良い飲み友達っぽいワチャワチャ感が楽しめます。リアルに大事にしてあげたい性格です。
家主で仕事を見つけてくるので、一番居ないとストーリーが成り立たない立ち位置と思います。
ネタバレありの感想(クリックで表示)(やや辛口)
「ムードメーカー」「弟系(歳上設定)」「純情」「照れ屋」「ヤンデル(超軽度)」「天才」
私は乙女ゲームのショタがやや苦手でして…、スケアクロウは歳上ながら弟キャラなんで、攻略キャラの中じゃ淡々と読んでた方だと思います。
お父さんと電車の中に居る間は泣きながら読んでましたけど!
過去の悪行と向き合うってパターンが個別√はリンボ&ヘルベチカ&スケアクロウが一緒で金太郎飴感が強かったです。同じ構成のストーリーだったら、個人的には麻薬中毒にまでなったヘルベチカの方が衝撃的だったんだと思います…(泣)。
sideBはショタで読んでられるかなって心配だったんですが、泥んこ遊びしてたとことか普通に楽しんで読めた!モズお母さんきた( ^ω^ )とか別の面で喜んでた気もしますが…(家庭的なキャラ好き)。
(6)
真相ルート ネタバレありの感想(クリックで表示)(辛口気味)
「完璧」「幼馴染」「一途」「過保護」「非恋愛√」「バッドのみ?」「ヤンデレ」「ヤンデル?」「殺害」
結論から言うと…最終的な結末は公式HPを最初に見た時から想定してた結末でした…、なので何も意外な要素なく、正直ガッカリしました。
途中で結末をいろいろ考えながら読んでいて、アダム普通に生き残って普通にテウタとくっついたら詰まらないなーとか、そもそもルイロペスの弟はアダムだろうなーって予想したりしてたり、もしかしたらアダムは最終的に狂ってリンボ達を殺しちゃったりしてーとか、テウタを襲って来たりしてーとか、お兄ちゃんが蘇ってきたりしてーとか、もっと色々最悪のケースを想定してたんで、実際真相√読んで、ああお兄ちゃん殺しただけかーとか思ってました。いや、視界もままならないまま、発狂していくアダムが可哀想で号泣してましたけど(涙腺弱い)、でもどっかで物足りないなーもっとグロい結末下さいって思ってました…(鬼)。
でも、きちんと最後にアダムが死んだような死んでないような結末にしてくれた点は評価してます。生き延びてテウタとくっついてたらきっとデートの演出が相当魅力的じゃないと不満だったと思うし、その恋愛描写の実力はこのスタッフチームには無いだろうと思います…;;
シャドウハーツ1と同じような結末だったので、続編は是非シャドウハーツ2のような展開でお願いしたいと期待しちゃってます。シャドウハーツ1はヒロインが自己犠牲の後に肩にもたれかかって眠るように移動中の車内で死んじゃいます。シャドウハーツ2は死後半年たってその死を受け入れられずに苦しむ男主人公が描かれます。
スタンドバイミーもモチーフのようですので、クリス君(リバー・フェニックス)の死もきっと掛かっているんでしょうね…。あれは今でも辛く悲しい出来事でした。
この真相編、よくあるタイプだなって思ってたんですけど乙女ゲームでいうと蝶毒に似てる気がします。属性考察をすると殺害要素、幼馴染、ヤンデル、嘘つき、完璧系、社交的、サスペンス、真相…と似通っているなあと一度思ってしまうともう、そう見えてしまいました…。もしも、ルイロペスのボスだったらもっと似てましたね…別の真相でそこは良かったかもしれません。
スタンドバイミーがモチーフだと分かって…私が(モズを除いて)リンボ達皆もテウタも精神年齢が低い点を気にしていた点の謎が解けました。もともと作者は12歳くらいを想定して描いていたんですね…。
そして、テウタも攻略キャラ達もみんな雄っぽさが無いと不満を述べていた点も同時に解決しました。作者は『無償の愛』を描きたかったんだと…。だから、この作品のテーマは男と女が出会って愛を育む物語ではなく、そもそもリアルな社会人の恋愛を描く気も無かった。これは、家族愛・友情の物語だったんだなあと分かりました。恋愛描写が苦手だと割り切った上で、サスペンスに友情を入れ込んだら面白いだろうと…。ええ、サスペンスとしては非常に面白かったです。乙女ゲームの中でも私の中ではトップに近い文章力でした。ただ、恋愛物としては少し物足りないですし、萌えれなかった点は残念でした。私はスタンドバイミー単体はとても好きなんですが、それは乙女ゲームではないジャンルで勝負して欲しいテーマかなと思いました。
アダムの属性ですが、なかなか難しいです。殺害という違法行為をしている点、それが主人公への想い故である点、そもそも脳腫瘍(?)で病気になっていて、ついには精神まで壊れていく…と項目を挙げていくとヤンデレだと思います。
ただ主人公が認識しておらず初登場時から病んでいるキャラはヤンデルに分類される事が一般的です。優しいキャラに萌える読者が意味不明な発狂に引く事が多いからだと考えています。だから初登場から病んでいるアダムは「ヤンデル」の一面が強いと客観的には分類します。
アダムについては普段の常識人っぷりがこれでもかとアピールされている点、狂いきる前に主人公への一途な想いも説明されている点から、ヤンデレが苦手な一般層に受け入れられやすく作られていると思います。なので定義上というより、読者目線で考えると「ヤンデレ」にカテゴライズされるキャラかなと思いました。
私は幼馴染好きなので好意を抱いた年月の長さから考えても、テウタとのカップリングはどうしてもアダムを推してしまいます。ストーリーが好みでなかろうが無償の愛に萌えなかろうが、テウタにアダムを忘れては欲しくないと感じました。その死を乗り越えて最終的に別の人と結ばれるとしても、その想いを受け止める時間をテウタに作って貰いたいと思いました。
今更ながら世間の感想をほんの少しだけ読んだのですが、真相がハッピーエンドじゃなくて嫌だという声が多い事に驚きました…。私は真相編ではバッドエンドな事だけを高評価してそれ以外の独創性の無さを低評価していたのですが、改めて自分はこの作品のターゲット層では無かったと痛感した次第です…。
大きな声で言い辛い自分の思いをここに書かせてもらいます。様々な意見がある事は良い事ですが、独自性や物語性を求めるユーザーが業界から離れていく…という実情を察しました…。個人的にはテンプレを壊す気概の無い作品はプレイしたく無いので、真相をバッドエンドにした、アダムが攻略キャラにならないという点がこの作品の全体構成の最大の長所だと考えています。
とはいえ、バスタフェのプレイヤー層は爽やかな幸せ物語を願う層が多いようなので、単純にビジネスを考えるならば、アダム√はここまでガチガチの攻略制限を設けなくても良かったのかもなあと感じました。ここまで愛の深い幼馴染の悲劇を真相扱いにしてしまうと、「じゃあ今までの他の攻略キャラと愛を育んだ世界線は何だったの?」「もう感情移入しちゃってるんだけど?」というモヤモヤは残りますしね。誰か一人攻略したら、ルイロペス事件√とお兄ちゃん事件√が読めるという程度の攻略制限だった方が、ユーザー自体もハッピーエンドでプレイを終えるか、悲恋で終えるかを選択出来ますので、そちらの方が『ゲーム性』という意味でも、より多くのプレイヤーの需要に応えるシステムになったのかもしれません。
もしも、アダムが生き残ってハッピーエンドを迎えてしまったら、バスタフェはここまで話題になる事はなかったのかなと思います。乙ゲメーカーとしては大手では無いわけですし、バッドエンドで勝負するくらいの覚悟がスタッフに見受けられたからこそ、応援してあげたいというファンも増えて、ここまで口コミは盛り上がったのだと感じています。
(バスタフェの攻略方法をいろいろ考察して纏めたのは、あの時点では私が最初だと考えています。グーグル検索やツイッターや板などは閲覧していましたが、あの時点ではどの選択肢を選んだかというざっくりした内容しか語られていなかったと思います。とはいっても、このブログはそもそもメインコンテンツは男性向けの超高難易度アクションの攻略サイト(笑)ですので乙ゲのキーワードでグーグルAIに弾かれていたくらいのしょぼしょぼサイトなんですが...一応2020年2月の1ヶ月でバスタのページにもそこそこ反応頂いております。)
売上ランキングにはカウントされておらず、中古市場メインと考えてもバスタフェを2月にプレイした新規ユーザーの総数は1000人を超えるのではないかと私は想像しています。Switch初週の売上数は3000という弱小ネームバリューの作品としては、これは偉業と言っても良いのではないでしょうか。新型コロナ騒ぎもプラスには働いて、もしかしたらアプリ版や中古版のユーザー含めたら5千や1万という大台を超える可能性もあるかもしれません。ゲーム業界の片隅にでも乙ゲ作品が生き残ってくれる事を期待させていただきたいと考えています。
【プレイを終えての総評】
私はプレイ済みの乙女ゲーム50タイトル程度のライトユーザーです。総合板などよく見てるので未プレイのゲームもユーザー層はそこそこ把握してる方かもしれません。ただ、乙女ゲームでは優しいキャラや純愛が苦手でして…それが原因で合わないキャラは多い方です(一般ゲーではむしろ優しいキャラが好物)。なので、殆どの乙女ゲームはスキップモード速読を多用します。使ってないゲームは4タイトルくらいです…。このゲームは攻略作業以外ではスキップは使用していません。全文をゆっくり読んだ乙女ゲームは私としては史上5作目となります。ですので、恋愛描写が微妙とか、ゲームに求めてる物が違うとか、ストーリーが好みだったキャラと萌え属性が合わないとか、文句タラタラな文面ではありますが、私はこのゲームを高評価しています。私の好み属性は乙女ユーザーの中ではやや特殊な方ですので、おそらくバスタフェロウズは一般層含めた多くの女性が楽しめる作品だと考えています。
真相のストーリーや属性があまり合わなかったので、最終的には元々好み属性のモズ推しなのかなー…(?)。真相も想像の範囲内過ぎたという点以外では面白かったですし、悪くはないと思っています。私の中ではテウタはこの後しばらく真相の結果を受け止めて生きていくんだろうな、という妄想でいっぱいです。どのルートでも数回以上号泣しながら読めていたんで、誇張なしに10回は涙をポロポロ流して読んでいました。萌えはともかくストーリーは面白かったです。全体構成はもう少しオリジナリティが欲しかったと思いました。
---------------------------------
*乙女ゲーム目次
*歴代乙女ゲームおすすめランキング
*蝶の毒華の鎖感想(ネタバレなし)
*ハトアリシリーズ感想(ネタバレ全開)
*バスタフェロウズ攻略方法
*華アワセ感想(ネタバレなし)
*華アワセ(いろは編と全編)考察と感想(ネタバレ全開)
*一般ゲーム感想まとめ
---------------------------------
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
BUSTAFELLOWS共通√攻略方法考察
バスタフェの攻略作業に苦労したので、簡単に共通√の攻略のコツを書きます。
攻略制限は無いそうです。
他にも丁寧な攻略サイトありますのでそちらもご確認下さい。
【攻略のコツ】
*選択肢の色で
リンボは黒色
シュウは青色
ヘルベチカは桃色
モズは黄色
スケアクロウは緑色
を多く選ぶと攻略出来ると思われます。
*≪共通Save2≫から全キャラ攻略出来ます(確認済み)。
*記事の方向性のポイントは捨てても、心理テストのキャラポイントを稼ぐだけで充分です(未確認→確認済み)。
*攻略したいキャラの思考によせて選択肢を選ぶのが良さそうです。
*黒色は分かり難いのでとりあえず皆が喜びそうな黒色を選ぶと良いかもしれない(未確認)。リンボが一番分かり難く攻略難易度が高いので、気力のある一番最初か、慣れてきた一番最後が良いかもしれません(各人の自由です)。
*ログで巻き戻る分にはデメリットは無さそうです(未確認)。
*心理テストの選択肢以外は適当でも大丈夫かもしれません(未確認)。一応自分の選んだ選択肢を載せておきます。
*個別√は特に分かりずらいと感じませんでしたので適当で大丈夫と思います。
*不備や間違いや誤表記等ありましたらコメントやツイッターでご指摘お願い致します。
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街のエンタメについて
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所があるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:黒色4点
*↑責任感。関係性の中に自分の形。孤独。→リンボ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)吸ってみたい
*猫の名付け親がリンボになれば恐らくリンボルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をリンボと開封する
*水着をリンボが選ぶ
【個別:リンボ√sideA】
*↓そっと見守る路線です。
(L-1)やめておこう
(L-2)聞きたくない
(L-3)ヴァレリーさんの言う通り
(L-4)喧嘩を止めない
(L-5)話しかけない
(L-6)手を握る
(L-7)賛成する
(L-8)グラスを取り替えない
≪リンボ個別Save≫
(L-9)絶対に死なない
➡︎Linbo Ending
≪リンボ個別Save≫より
(L-9)リンボの為に命を賭ける
➡︎Bad Ending B
タイトルのゲームスタート画面より【リンボ√sideA】を選択
*↓しつこく干渉する方向。
(L-1)面白そう
(L-2)聞きたい
(L-3)リンボの気持ちは分かる
(L-4)喧嘩を止める
(L-5)話しかける
(L-6)黙って見つめる
(L-7)反対する
➡︎Bad Ending A
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の犯罪について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
*)↑「シュウの喫煙を奨励した」実績に繋がる
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:青色4点
*↑客観的判断。冷静な視点。→シュウ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)早く見つかるといいね
・(3-2)吸ってみたい
*猫の名付け親がシュウになれば恐らくシュウルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をシュウと開封する
*水着をシュウが選ぶ
【個別:シュウ√sideA】
(S-1)理解したいとは思ってる
(S-2)シュウの家族だから
(S-3)シュウに電話する
(S-4)関係ある
≪シュウ個別Save≫
(S-5)何もしない
(S-6)その聞き方はずるい
➡︎Shu Ending
≪シュウ個別Save≫より
(S-5)結束バンドを解く
➡︎Bad Ending
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の人間について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)正直言ってお金は欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:桃色4点
*↑自立した人間でありたい。感情的で関係性に固執。ヘルベチカに似ている。→ヘルベチカ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がヘルベチカになれば恐らくヘルベチカルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をヘルベチカと開封する
*水着をヘルベチカが選ぶ
【個別:ヘルベチカ√sideA】
(H-1)リンボに連絡する
(H-2)聞いてみる
(H-3)声をかける
(H-4)たまにはいいんじゃない?
(H-5)無理矢理中に入る
(H-6)1218
➡︎Helvetica Ending
タイトルのゲームスタート画面より【ヘルベチカ√sideA】を選択
(H-1)シュウに連絡する
(H-2)聞かないでおく
(H-3)そっとしておく
(H-4)らしくないよ
(H-5)リンボ達にまかせておく
(H-6)0000
(H-7)0000
➡︎Bad Ending
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の犯罪について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:黄色4点
*↑円滑を意識。人間関係に苦手意識。探究心が強い。→モズ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がモズになれば恐らくモズルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をモズと開封する
*水着をモズが選ぶ
【個別:モズ√sideA】
(M-1)ユズの手掛かりがあるといいね
(M-2)何を考えているかは分からない
(M-3)分からない
≪モズ個別Save≫
(M-4)アイビーを助けて
➡︎Mozu Ending
≪モズ個別Save≫より
(M-4)トロイ先生を助けて
➡︎Bad Ending
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の人間について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:緑色4点
*↑距離を詰めるのが上手。壁を感じさせない。自然体。クロ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がクロになれば恐らくクロルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をクロと開封する
*水着をクロが選ぶ
【個別:クロ√sideA】
(C-1)ありがとう
(C-2)質問する
(C-3)こっちにおいで
≪クロ個別Save≫
(C-4)暗号の意味を聞く
➡︎Crow Ending
≪クロ個別Save≫より
(C-4)スケアクロウを止める
➡︎Bad Ending
【無断転載禁止】
…自分が年末年始もありそこそこ多忙の中、時間かけて攻略方法を考察したのに、有名攻略サイトに無断で丸ごとコピーされているのに気付きました。当方の目的は縮小する市場を憂い新規ユーザーが挫折しにくくなるようにという点ではありますが、金儲けの為の無断コピーは正直良い気分ではないというクレームをここに記述しておきます。個人ブログならともかく、明らかにゲームを未購入でプレイしていないサイトの無断はちょっと気持ち悪いです。
あの某サイト数年以上前から他のゲームでも、殆どの乙女ゲームで記事を勝手に転載してると言われててやめないので悪質だと思います。
以下、ネタバレ少なめの個人的感想です。
未プレイの方にも読んで頂ける文章のつもりです。
*バスタフェロウズ感想(ネタバレOn/Offあり)
未確認の箇所を確認したいが、記事を書いて色分けしただけで力尽きそうです。
---------------------------------
*乙女ゲーム目次
*歴代乙女ゲームおすすめランキング
*蝶の毒華の鎖感想(ネタバレなし)
*ハトアリシリーズ感想(ネタバレ全開)
*華アワセ感想(ネタバレなし)
*華アワセ(いろは編と全編)考察と感想(ネタバレ全開)
*一般ゲーム感想まとめ
---------------------------------
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
バスタフェの攻略作業に苦労したので、簡単に共通√の攻略のコツを書きます。
攻略制限は無いそうです。
他にも丁寧な攻略サイトありますのでそちらもご確認下さい。
【攻略のコツ】
*選択肢の色で
リンボは黒色
シュウは青色
ヘルベチカは桃色
モズは黄色
スケアクロウは緑色
を多く選ぶと攻略出来ると思われます。
*≪共通Save2≫から全キャラ攻略出来ます(確認済み)。
*記事の方向性のポイントは捨てても、心理テストのキャラポイントを稼ぐだけで充分です(未確認→確認済み)。
*攻略したいキャラの思考によせて選択肢を選ぶのが良さそうです。
*黒色は分かり難いのでとりあえず皆が喜びそうな黒色を選ぶと良いかもしれない(未確認)。リンボが一番分かり難く攻略難易度が高いので、気力のある一番最初か、慣れてきた一番最後が良いかもしれません(各人の自由です)。
*ログで巻き戻る分にはデメリットは無さそうです(未確認)。
*心理テストの選択肢以外は適当でも大丈夫かもしれません(未確認)。一応自分の選んだ選択肢を載せておきます。
*個別√は特に分かりずらいと感じませんでしたので適当で大丈夫と思います。
*不備や間違いや誤表記等ありましたらコメントやツイッターでご指摘お願い致します。
①リンボ攻略(クリックで表示)
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街のエンタメについて
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所があるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:黒色4点
*↑責任感。関係性の中に自分の形。孤独。→リンボ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)吸ってみたい
*猫の名付け親がリンボになれば恐らくリンボルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をリンボと開封する
*水着をリンボが選ぶ
【個別:リンボ√sideA】
*↓そっと見守る路線です。
(L-1)やめておこう
(L-2)聞きたくない
(L-3)ヴァレリーさんの言う通り
(L-4)喧嘩を止めない
(L-5)話しかけない
(L-6)手を握る
(L-7)賛成する
(L-8)グラスを取り替えない
≪リンボ個別Save≫
(L-9)絶対に死なない
➡︎Linbo Ending
≪リンボ個別Save≫より
(L-9)リンボの為に命を賭ける
➡︎Bad Ending B
タイトルのゲームスタート画面より【リンボ√sideA】を選択
*↓しつこく干渉する方向。
(L-1)面白そう
(L-2)聞きたい
(L-3)リンボの気持ちは分かる
(L-4)喧嘩を止める
(L-5)話しかける
(L-6)黙って見つめる
(L-7)反対する
➡︎Bad Ending A
②シュウ攻略(クリックで表示)
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の犯罪について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
*)↑「シュウの喫煙を奨励した」実績に繋がる
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:青色4点
*↑客観的判断。冷静な視点。→シュウ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)早く見つかるといいね
・(3-2)吸ってみたい
*猫の名付け親がシュウになれば恐らくシュウルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をシュウと開封する
*水着をシュウが選ぶ
【個別:シュウ√sideA】
(S-1)理解したいとは思ってる
(S-2)シュウの家族だから
(S-3)シュウに電話する
(S-4)関係ある
≪シュウ個別Save≫
(S-5)何もしない
(S-6)その聞き方はずるい
➡︎Shu Ending
≪シュウ個別Save≫より
(S-5)結束バンドを解く
➡︎Bad Ending
③ヘルベチカ攻略(クリックで表示)
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の人間について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)正直言ってお金は欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:桃色4点
*↑自立した人間でありたい。感情的で関係性に固執。ヘルベチカに似ている。→ヘルベチカ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がヘルベチカになれば恐らくヘルベチカルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をヘルベチカと開封する
*水着をヘルベチカが選ぶ
【個別:ヘルベチカ√sideA】
(H-1)リンボに連絡する
(H-2)聞いてみる
(H-3)声をかける
(H-4)たまにはいいんじゃない?
(H-5)無理矢理中に入る
(H-6)1218
➡︎Helvetica Ending
タイトルのゲームスタート画面より【ヘルベチカ√sideA】を選択
(H-1)シュウに連絡する
(H-2)聞かないでおく
(H-3)そっとしておく
(H-4)らしくないよ
(H-5)リンボ達にまかせておく
(H-6)0000
(H-7)0000
➡︎Bad Ending
④モズ攻略(クリックで表示)
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の犯罪について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:黄色4点
*↑円滑を意識。人間関係に苦手意識。探究心が強い。→モズ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がモズになれば恐らくモズルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をモズと開封する
*水着をモズが選ぶ
【個別:モズ√sideA】
(M-1)ユズの手掛かりがあるといいね
(M-2)何を考えているかは分からない
(M-3)分からない
≪モズ個別Save≫
(M-4)アイビーを助けて
➡︎Mozu Ending
≪モズ個別Save≫より
(M-4)トロイ先生を助けて
➡︎Bad Ending
⑤スケアクロウ攻略(クリックで表示)
【共通√】
(チャプター1)
・(1-1)表
≪共通Save1≫
・(1-2)この街の人間について
*↑記事の方向性についての選択肢はポイントを捨てても、√分岐に影響しない事を確認した為、巻き戻り機能でそれぞれの選択肢の実績(Memorabilia)さえ取れば、共通Save1は保持する必要は無いかもしれない。
・(1-3)シューホーンだった
・(1-4)選択しない(時間切れ)
・(1-5)ちょっとムカつく人だと思った
・(1-6)お金よりも特ダネが欲しい
(チャプター2)
・(2-1)あっちに喫煙所あるよ
・(2-2)選択しない(時間切れ)
・(2-3)優しいんだね
≪共通Save2≫
・(2-4)心理テスト、各設問
<1>相手の間違いを指摘出来る方だ
Yes→黒/No→緑
<2>他人を頼るのはあまり好きではない
Yes→桃/No→黒
<3>他人にプレゼントを選ぶのが好きだ
Yes→緑/No→黄
<4>自分の行動は感情的というより理論的だ
Yes→黄/No→桃
<5>結末を予想して準備してする方だ
Yes→青/No→黒
<6>好奇心が強い方だ
Yes→緑/No→青
<7>人や動物の世話が好き
Yes→黄/No→桃
<8>分からない時は分かるまで追求する
Yes→黄/No→青
<9>社会問題に関心がある方だ
Yes→黒/No→桃
<10>失敗した事を長く後悔する方だ
Yes→緑/No→青
*)↑心理テストは全ての選択肢の中で最もウエイトが大きい様に思いました。攻略キャラによせて回答を選ぶと良いです。
・テスト回答:緑色4点
*↑距離を詰めるのが上手。壁を感じさせない。自然体。クロ√より。
・(2-5)選択しない(時間切れ)
・(2-6)勝負する
・(2-7)人差し指でコインの外側を擦る
(チャプター3)
・(3-1)私も会いたいな
・(3-2)やめておく
*猫の名付け親がクロになれば恐らくクロルート突入決定
(チャプター4)
*選択肢無し
*手紙をクロと開封する
*水着をクロが選ぶ
【個別:クロ√sideA】
(C-1)ありがとう
(C-2)質問する
(C-3)こっちにおいで
≪クロ個別Save≫
(C-4)暗号の意味を聞く
➡︎Crow Ending
≪クロ個別Save≫より
(C-4)スケアクロウを止める
➡︎Bad Ending
【無断転載禁止】
…自分が年末年始もありそこそこ多忙の中、時間かけて攻略方法を考察したのに、有名攻略サイトに無断で丸ごとコピーされているのに気付きました。当方の目的は縮小する市場を憂い新規ユーザーが挫折しにくくなるようにという点ではありますが、金儲けの為の無断コピーは正直良い気分ではないというクレームをここに記述しておきます。個人ブログならともかく、明らかにゲームを未購入でプレイしていないサイトの無断はちょっと気持ち悪いです。
あの某サイト数年以上前から他のゲームでも、殆どの乙女ゲームで記事を勝手に転載してると言われててやめないので悪質だと思います。
以下、ネタバレ少なめの個人的感想です。
未プレイの方にも読んで頂ける文章のつもりです。
*バスタフェロウズ感想(ネタバレOn/Offあり)
未確認の箇所を確認したいが、記事を書いて色分けしただけで力尽きそうです。
---------------------------------
*乙女ゲーム目次
*歴代乙女ゲームおすすめランキング
*蝶の毒華の鎖感想(ネタバレなし)
*ハトアリシリーズ感想(ネタバレ全開)
*華アワセ感想(ネタバレなし)
*華アワセ(いろは編と全編)考察と感想(ネタバレ全開)
*一般ゲーム感想まとめ
---------------------------------
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
華アワセ いろは編と全編の考察と感想
乙女ゲーム「華アワセ」のいろは編を10周しました…。沼りすぎです。
自分の個人解釈を書きたいと思います。間違っている可能性大です。
考察って赤面モノなんですが、再プレイのモチベ用に公式本が出るまでは、ボチボチ更新したいです。
①全編といろは編の主題と物語構成についての考察
分かり易く言うと「華アワセ全体の解説」です。あくまで一個人の解釈です。この複雑な物語をどういう視点で読めば、理解しやすいのか…という事を恥ずかしながら偉そうに拙文にてご説明致します。
細かく言うと、蛟/姫空木編の記録的高評価がなぜ唐紅/うつつ/いろは編で下がってしまうのか、という点を考察したいと思います。
(つまり糖度が下がっていく理由)。
(一般的乙女ゲームとの差異点について)。
(あと、いろは編で個別√無しの理由/封神システムの理由/甘党じゃない理由/新キャラの意義や場面が二転三転する理由等も考える)。
②ついでに用語解説とか複雑な各ツキとかループについても個人解釈を入れます。と思っていたが1の文章量が多過ぎて力尽きたので書きかけです…。
⇒丁寧な図解を載せているサイト様見つけましたのでご検索下さい。
*)ネタバレ全開です。長文です。ご注意下さい。
数年前1読のみで記憶朧げな部分多々あります。ご了承下さい。
*)ネタバレ少なめ(未プレイ向け)の感想はコチラの記事です。
******目次******
①-(0)序文
①-(1)蛟
①-(2)姫空木
①-(3)唐紅
①-(4)うつつ
①-(5)いろは
①*まとめ
①-(6)百歳
②-(a)トートタロット
②-(b)和歌
******************
*)物語は公開された時点で読み手一人一人の感想だけが真実であると思います。特に萌えは「考えるな、感じろ・・・!」の世界のモノなので、理屈で分解する作業や一個人の解釈は絶対的な物では無いと考えております。もしも、他者の解釈にご興味のある方、また違う視点で物語を見つめたい方が居られましたらどうぞお読み下さい。
*)自分は至高のゲームと思うんですがツイッターや板では8:2程度で賛否が割れ、アマゾンに至っては酷評(笑)と評価が分かれています。(ゲーム性は下がって格安過ぎた価格は普通に上がっているのである程度の低評価は仕方ない。他キャラ推しの人が、いろはが好みかどうかでも評価は割れる)。
私個人としてはこの物語は論理的に構成されていると考えています。
一方で、表向きには、ループの中にループを入れたり世界線が変更されたりと、一読すると複雑過ぎて、単なる作者の自己満足作品を読まされているように感じられてしまう出来になっている事も事実と思います。
ですが、この作品を私個人は読み易くシンプルな全体像を持つ物語と受け止めています。伏線は解説を明言され無くとも殆ど綺麗に回収されています。
時代の流れと共に乙ゲ業界が縮小する中、自分が何故この作品を名作と思ったかを書き残しておきます。
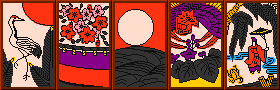
低糖化の理由は一言でいうと『各キャラでテーマが違う』からだと思います。作者が物語の主軸としている葛藤が五光によって異なるからです。
そしてその男性心理を理解してあげる事が蛟→姫→紅→うつつ→いろは、の順に難しくなってきますし、所謂「乙女ゲーム」の域を超えかかってくるので結果として糖度が下がっているように感じられます。おそらく作者としてはストーリーの順に愛情の質量は増している、より複雑になっていると解釈しているからこそこの順序なのだと思います。(ベクトルが異なるので単純比較は出来ませんしキャラの優劣を述べているわけではありません)。
よって、別に恋愛心理の比重は下がっていません。一時的な欲望として身体の接触の表現量が下がっていくだけと思います。
蛟が「中学生男子(DT)」
姫が「高校生男子(メンヘラ)」
唐紅が「社会人男性(普通)」
うつつが「幼稚園児(ヤンデレ)」としたら
いろはは「人間以前の小学生」です(笑)。
全年齢対象乙女ゲームの「華アワセ」というタイトルは、それぞれの年齢でヒトが成長を経験していく「恋愛葛藤」をテーマとして描かれています。そして女性がその男性をどう受け止めるかという過程。乙女ゲームが描こうとしている『「恋愛」とは何なのか』を突き詰めていく物語です。
低評価の理由はヤンデレゲーとかメリバゲーに分類されるので方向性がぶれていく様に感じられるだけだと思います。
以下、五光各キャラについて。
一般論としての性格。
(1)蛟…童貞型ヤンデレ。厨二男子。
(2)姫…ホラー型ヤンデレ。メンヘラ。
(3)唐紅…オレ様型。最もマトモ。
(4)うつつ…重過ぎ型ヤンデレ。逆コナン。
(5)いろは…機械型ヤンデレ。逆コナン。
(6)百歳…準ラスボス。真の不遇キャラ。
こんなところと思います。
個人的に語ります。
意見の割れるいろは編の為に蛟/姫/唐紅/うつつ編についても長文です。特に唐紅/うつつ編にもいろは編考察が入ってきます。

巽の蛟。
こちらは一般論と相違ないです。理性と肉欲で葛藤する普通の男の子を描いています。テーマは『欲情』。キャベツ畑から赤ちゃんが生まれるという女性側の幻想を信じているピュアな少女が、現実の男の子の生々しい生理的本能を受け止められるのかという葛藤や過程が丁寧に描かれています。
蛟は「愛のあるヤンデレ」に分類はされるでしょうが、ぶっちゃけごく普通の男子なので、乙女ゲームユーザーの中でも多くの人に受け入れられると思います。乙女ゲームでここまで生々しく描かれるのは珍しいですが、人間としては普遍的なテーマですよね。
図書館で押し倒された主人公がそれを悔やむ蛟の部屋に行った時、(その出来事を私から越えなければ彼を失ってしまう)と、自ら肌を晒していくエピソードは見事でした。現実の恋愛でもどこかしら女性は男性の肉欲に譲歩する事あると思います。
蛟は数斗の「コイン」と戦います。五斗は帝の執着の負の部分のようですが、「男女を不幸にする感情」「恋愛失敗要因」を象徴しているように思います。スートはタロット用語です。コインは硬貨・物質的世界・大地の事だそうです。
コインの正体は長髪男だったり露蕗だったりします。華アワセにおいてコインは「肉欲」「物理欲求」を表しているのだと考えています。
蛟を受け入れた主人公にショックを受けるいろはは、まるで娘を溺愛する父親のようですw
童貞の蛟じゃ満足出来ねえだろ、と言って迫ってくる唐紅の自尊心も可愛らしい。
良いお友達を目指して姫がホラーになるEDは衝撃的でした。良くも悪くも華アワセを代表するEDは蛟編の姫空木と思っています…;
というか、この姫EDが印象的過ぎた為にヤンデレゲー、バッドエンドゲーという地位を確立しきってしまい、結果的に後にシナリオ重視型へと偏重していった時にユーザーが付いて行けなかったのかもしれませんね…。もしかしたら元々ユーザーは物語にオチやテーマなど求めていない層が多いのかもしれません。(私も乙ゲにストーリーは求めない層です。華アワセは期待以上に面白かったです)。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****

坎の姫空木。
「乙女ゲームの愛のあるヤンデレキャラとは何か」を突き詰めたようなキャラクターでした。姫空木のテーマは『エゴ』『恋愛観』だと思います。「外面完璧なのに、中身はドロドロ」というキャラです。
『社会的にどういう振る舞いが正しいとされるのかは理解出来て実践出来ても、自分の内実を晒して受け止めてもらうにはどうしたら良いのか分からない、本当のあるがままの自分を受け入れて欲しい』という葛藤が描かれていると思います。
なぜ乙女ゲームにおいて非現実なヤンデレキャラが人気属性なのか、ヤンデレキャラの魅力とは何かを問い質すようなキャラクターです。社会とか建前とか捨てて恋愛にのめり込みたいという乙女の欲望、そしてエロのスパイスとしての嫉妬・独占…そういった物が詰め込まれていました。
女性は「完璧で頼り甲斐のある男性」という幻想を捨て、すぐ挫けて間違えを起こす男性を助けてあげよう、相互依存という関係性を目指していこうと支え合いを学びます。男性がヒロイン扱いとなるいわゆる「カウンセリングゲー」ですね…(笑)
男性側の欲望を女性が受け止める構成なので自然に糖度は高いです。ある意味R18より高いんじゃないかと…。そしてこれがMax糖度となる為、以降は失速感が否めず、意見が分かれていきます。男性向け用語である「オカズとして使えるゲーム」としての性能(女性向け糖度と同意義とする)は蛟/姫編と比べると、唐う/いろは編は下がります。
数斗の「チャリス」はツキによって正体が異なります。茉莉花だったり斧定だったりします。タロットにおいてチャリスはカップ(聖杯)の事です。水・感情を意味します。
斧定は花札制度を整えた人でゲーム内においてはおそらく「華詠」という男性像を象徴するキャラです。茉莉花は姫空木に愛されなかった少女です。乙女ゲームのユーザーを象徴しているのだと思います。華アワセにおいてチャリスは「恋愛心」「恋愛への憧れ」「押し付ける妄想」「一方的なエゴ」「自己承認欲求」などの事かなと思います。つまりはごく普通の人間です。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****

寅の唐紅。
『漢』キャラ。唐紅は「第一印象最悪だけど実は良いヒト」というポジションのキャラです。五光の中で最もメンタル強く、状況対応力があり、頼り甲斐がある。女性向けPCゲームの王道キャラですね。多分一番人気なんじゃないでしょうか。最終的には百歳と二分しているかもしれませんね…。
唐紅という言葉は有名な和歌「ちはやふる…」にも描かれる紅葉の血のような色を指します。桜花はそのまま桜。キャラデザにも胸に桜の花をさしています。唐紅というキャラのモチーフは一瞬で華々しく咲き誇り一時で散る無常観「もののあわれ」である事と流血なのかなと思います。
唐紅の価値観では、男女の仲はお互い気持ち良くなって満足し後腐れなくが漢の甲斐性というような所があります。歴史でいうとシーザーとかそういうカリスマ性がありますね…、武士道を例に出すように日本における古典的な男女の理想の恋愛観というものを叩き込まれています。女に尽くすタイプです。TPO弁えないセクハラや歯に衣きせぬ発言以外は…(笑)。
なので唐紅は自身の情欲のコントロールもお手の物で、女性を気持ち良くさせて寸止めで帰宅させるというテクニックもマナー・処世術として身に付けています。いろは推しの私でも実際に入るなら絶対桜花組です!(株を上げ過ぎてる感があるので他の五光をフォローすると、桜花組は水妹の資格を失う生徒は出ていませんが、それなりの事はしてますよ多分…)。
そういった唐紅の葛藤は蛟や姫よりも上の次元になっていきます。『一時の仲ではなく、男が女を幸せにするとはどういう事か。寄添い夫婦になるとはどういう物か。他人の人生に介在する覚悟』が唐紅のテーマと思います。つまりは『結婚観』『家庭観』ですね。
なので唐紅の父親は浮気をしてしまい、母親はそれが原因で病んでしまい、唐紅は家庭観が壊れているという設定なのだと思います。でも唐紅は厳しいお祖母さんの愛情を受けて、その教えを尊重していますよね。
五光は上司命令で仕事として一時的な恋人ごっこをしているに過ぎず、主人公は上司の結婚相手です。ホストみたいなお仕事ですね…。唐紅は一時的な関係性で深く踏み込む事に躊躇してしまいます。
唐紅の主人公の前ではいつも出来ている自己セーブが出来ずに戸惑う姿は可愛らしいですが、その程度の描写に留まります。キス以上の進展は意外となく…、ユーザーは期待していた糖度よりも低くてガッカリしてしまいます…。
家庭観がないという事は自信が無い、自己を愛せない、という事です。唐紅は一時の快楽を満たしてあげる事は出来ても、一生かけて女性を幸せにする自信がありません。
主人公は唐紅の身内にも誰にも言えなかった自己否定感を拭い、その生い立ちを肯定してあげる事で、母には彼女なりの想いがあった事を示す事で唐紅の孤独を救います。
艮(母親)と対峙する際にいめを犠牲にしてしまいます。これはうつつが原因にもなっていますが唐紅編の二人はいめを犠牲にしてエンディングを迎えます。更に唐紅は帝に逆らって泉姫の寿命を縮めようとしてしまいます。(いろはの件は唐紅に責任は無いとしました)。二つが唐紅編の男女に欠けていた点として、いろは編との対比になっている様に思います。
唐紅は数斗と戦いません。ソードに攻撃はされますが、対峙する事なく本編を終えます。おそらく唐紅/うつつ/いろはの3人の対比が華アワセとして2つのテーマになっています。うつつは恋愛心理のみで他が欠け、いろはは恋愛感情が抜けているキャラクターです。なので、唐紅は欠点が少なく五光の中で最も恋愛上手として描かれているようです。花札の五光とタロットのスートをテーマにしたいというコンセプト上で艮組を二人に分けたのかもしれませんね。
*)恋愛上手な唐紅に欠けて、恋愛下手のいろはにはある要素が1つあります。というか他の五光にはなく、いろはにある物、それは『幸せな家庭観』です。それがあるからこそいろはが最終的に選ばれる真ルートになり得ます。
いろはは世界の外から来た神の子なので地上に親を持たず、みことの祖父と両親に育てられます。主人公と義理の兄弟みたいな関係性です。一族が…とかいう背景を持つ蛟/姫/唐紅/うつつと比べて、幸せな食卓というイメージも具体的に持っていますし、何よりみことの家庭観とビジョンを共有出来ます。
唐紅/うつつ/いろは編の総論として、いろはが家庭像を提示出来るからいろは編のみは最終的なハッピーエンドを迎えると思われます。
いろはに食欲に関するエピソード、家庭に関するエピソードが多いのはそういう理由だと思います。甘党だったりそうでなかったりする理由も「甘党」を強調したいのではなく、「みことの味=家庭の味」が好きなんだという表現かもしれませんね。岩石は無理なようですが(笑)
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****

丑のうつつ。
社会性と正義感が欠如して、自分と主人公以外はどうでも良いという価値観の持ち主です。ヤンデレの定義そのものに挑戦してみた感じのキャラです。
うつつはおそらく唐紅といろはの対比として設定されたんじゃないかなと推測しています。いろはは大円団キャラなので「弥栄」(体制維持=世界平和)を自身の価値観として表明します。いろは編のみことも「みんなが幸せを目指したい」と言います。その壮大過ぎる価値観と対比をなすのが、「さよなら人類」を表明するうつつと思います。
唐紅は「女性本位」でかつオババに教え込まれた漢の甲斐性を価値観として掲げます。対してうつつは恋愛至上主義でどこまでも「自分達本位」です。
社会的に結ばれない方が幸せな境遇の男女が恋愛したらどうなるのか…そういったロミジュリ的な、究極の恋愛観を詰め込んだキャラなんだと思いました。蛟/姫編では出てきません。存在せずバッドエンドすら存在しない事が悲劇なんだと思います。かろうじてラブミーという顔すら出ないモブキャラで登場します…。「いめ」と「うつつ」という二つの顔を持つ二重人格です。
うつつの内実は恋愛感情のみです。例えば社会的地位であったりに興味も執着もありません。「自分」と「主人公」、「それ以外のどうでもいいもの」、その3つしかありません。家庭を取り合った唐紅と、主人公に執着するいろはには嫉妬心や敵愾心を示すものの、五光であるとか、帝、華園、華詠…といった立場や名誉や環境、金銭、職業などに一切の執着をみせません。失った恋愛感情を取り戻して普通の「人間」になるいろはと、恋愛感情以外を切り捨ててしまううつつの大きな差は社会性だと思います。うつつのテーマは『社会性』『背徳感/正義感』だと思います。
そしてうつつの愛情は幼稚園児の愛情、つまり家族愛なのだと思います。うつつ編の女性の愛情は母性愛です。
唐う編の数斗は「ソード」です。一族を捨て駆け落ちした蛟の母親です。息子の為に他を切り捨てます。ソードは風・論理性・知性・正義・試練だそうです。
ソードは「正義感・社会性の欠如」を象徴しているのかなと思います。
また、いろは編のラスボスはうつつ編の泉姫になります。それが数斗の「ワンド」です。ワンドは火・活力・情熱・野心だそうです。
幸せな結婚をして子宝に恵まれるものの五斗に利用されてエーテル体の化け物になってしまいます。作中のうつつが「いろはを犠牲にした報いを受けた」といった趣旨の発言をしていました。華アワセにおいてワンドは「周囲を省みない情熱」を象徴しているように思います。
*)うつつのテーマとして『背徳感』を追記しました。許されない仲というのは恋愛物語の大いなるスパイスになります。
古典的なロミジュリも、源氏物語の義母への想いも、大恋愛の名著って基本的に許されない恋ですよね…。
乙女ゲーム(ギャルゲー)が一定のジャンルを築いている理由として現実には難しい浮気が楽しめるからだと述べる評論家も居ます。私はその意見に反対派で、華アワセ以外の乙女ゲームは最推し以外は基本スキップモードで速読するかそもそも√放棄するか…というような人間ですので乙ゲ主人公の浮気自体が地雷に近かったりします。そういった層を想定してうつつ編は主人公が唐紅√に入り込む前に、分岐が設定されています。
でも、そもそも3度目のツキは唐紅のツキです。それをうつつはいろはを犠牲にして奪い取っていきます。だから、華アワセはツキを持っているキャラ(タイトルキャラ)以外はバッドエンドのみというシステムなのだと思います。逆に言うとそのシステムを成立させたいから、唐紅とうつつは同じディスクなんだと思われます。
作者が挑戦したかったのは、大勢の地雷を踏まない程度ギリギリラインの背徳感だと感じられました。
うつつ編導入直後の二人の邂逅シーン、部屋の窓からうつつが入ろうとするシーンはロミジュリを模しているという暗示なのかもしれません。
*)色々書きましたが、うつつに欠点があった事で彼自体を否定しているわけではありません。常人が1週間で消えるという設定の奈落において、3度のツキで10年近く耐えたわけです。消えかかってケを帯びて人間の皮を失い化け物になっていく…そういった恐怖とも闘いながら彼は求めてはいけないツキを望んでしまった。
いろはは神の子であり人間ではないのでうつつより想いが歪み過ぎずに済んだだけです。彼は超能力者ではあっても人間に過ぎなかった、彼の限界だったのだと思います。
結果、彼は奪い取ったツキにおいても最終的にはより悲惨なバッドエンドを迎えてしまいます。
ツキの半身と泉姫の世界を変える力、更には積年の百歳とうつつの後悔によって、いくつもの祈りと奇跡が重なって、いろはとみことのツキは生まれます。
いろは編は短いバッドを除くと、いろは一本道で他の五光や百歳のバッドエンドがない事が不満点として挙げられます。
けれども、いろは編において五光と百歳は自身の無力を呪いながらも、いろはが神の力を持つ彼としても出来る限りの「皆の幸せ」を目指した事を感じ取れた為に最愛の女性を託して祝福しています。
私は個人的には、それこそが彼らにとっての究極のメリーバットという形なのかと捉えています。
だからこそ、いろは編は戦闘が封神という五光全員とみことの6人で力を合わせる演出なのだと考えています。
華アワセにとって「華」はおそらく(男性の)恋心です。和歌における「花(桜)」の意味だと思います。「アワセ」は想いを合わせて、一方的ではない相互関係を持つ事だと思われます。
いろはは、みことと各五光を口説いて協力を奮起します。いろはのエンディングは、五光全員で恋心を重ねて掴み取る、五光全員のエンディングです。
私は、不完全ではあっても必死に想いを紡いだ彼らも愛してあげたいと思います。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****

乾のいろは。
神の子(亥の子)=ツクヨミ(=スサノオ?)=アダム=ツキの半身=二人目の主人公です。
感情を失った真相キャラクター。
前述しましたが、最終目標は世界平和という壮大なキャラクターです…。さすが大円団キャラです。流石は神の子です。
いろはのテーマはずばり『恋愛感情』『気力』。エンディングで感情を理解してやっと人間になります。ここでいう気力は「人生の意義」です。
いろは編のラスボスが五斗ではなく「ワンド」(情熱・活力)になっているのも対比関係を重視しての事だと思います。別のツキのハッピーエンド後の泉姫のなれの果てをラスボスにするというのはグロいですよね…。
うつつ編の女性は母性ですが、いろは編の女性は生活能力皆無の少女です。ニノとひなたの評価は能天気で大バカ者、両親の愛情に育まれ守られた太陽のような女の子です。いろはの恋愛観が幼少期から止まっており、女の子を守ってあげるという少年漫画的な初恋レベルの程度だからと思います。いろはは世界を救うヒーローになりたい子なんですね。
(合わせて0番の愚者のカード(天真爛漫)との整合性だったり、いろはのS度に負けない強いヒロイン(むしろみことのが強い)である必要性があったと思いますが、それについてはまた別に纏めたいです…。)
いろはは3作終えてバッドエンドのみという不遇属性を持ちます。このキャラクターを何とか幸せにしてあげたいというモチベーションを多くのユーザーに与えるという手腕は見事でした。
もし、いろは編が全編通してのテーマだったり伏線回収に重きをおかずに乙女ゲームとしての性能を追求していればビジネスとしては大成功だっただろうと思います。でも、作者は華アワセという五編の物語としてのテーマ性を重視した事によっていろはの糖度は下がっていきます。結果として賛否両論にはなりましたが、個人的にはテーマ性を貫いた事で一部のユーザーにとっては一生物の大作として心に残る偉業を成し遂げたと思います。貫かれた『恋愛とは何か』というテーマは無意識のうちにユーザー心理に残っていく事でしょう。
いろははみことへの愛情を認識して初めて自身の発情にも気付きます。持て余したいろははショウ君に相談します。流石大円団キャラですね。ショウ君に「小学生かよ」と驚愕されます(今までどうしてたんだ、神か)。きっと周囲の男子からオカズを融通されてこれから少しずつ自己セーブ力を身に付けていくんですねぇ。人間以前だったいろは君がやっと蛟君レベルになりました(笑)
他のツキのみことを知って嫉妬心からみことを外出先に放置してしまいます。いやあ、DVキャラですなぁ…。すぐに反省するところは優しいですが。やっと姫空木君レベルですかね…。唐紅君に届くのはずっと先でしょう…。
このまま喧嘩エピソードを最後にエンディングまで行ってしまいます。あと1エピソードを途中に挟む余裕があれば読後感も変わったでしょうので、そのあたりは一工夫欲しかったです。予算の関係などもあるでしょうが…(私の嗜好に無いので気付きませんでしたが一応このイベントはさらっと愛の言葉を告げてくれるイベントだったんですね…)。
終盤のいろはは多分蛟編の中盤程度で、姫編の序盤なんじゃないか…。だからエンディングにおいても恋愛下手で不完全なのだと思います。それでも、彼女を大切にして周囲を大切にして少しずつ前進していってくれると思います。
*)いろはが自身の活力、生きる目的を「弥栄」と定めた事で、それを支えたいとみことは泉姫に覚醒します。
上記で「弥栄=天下泰平=万歳=体制維持」を私は「世界平和」のような物だと意訳しました。が、世界平和と恋愛観がどう関わっているのか、伝わり難いと反省した為表記を改めます。
「弥栄=子孫繁栄」と訳し直します。亥の子がそもそも神の子というよりは子孫繁栄という意義の強い語ですので、子孫繁栄という解釈はおそらく作者の意図と大きくは外れていないと思います。
つまり、いろはは愛情とは「子供を育てる事」だと、恋愛とは「穏やかな家庭を築く事」であると、それこそが自分の生きる意味だと決めたという事だと思います。その決意をその場にいた五光と女百歳は認めたのだと思います。
男女が恋愛して、身体重ねるのって、子育ての為でしょ?恋愛って子孫の為、家庭の為だよね?という真理なんですけど、随分と乙ゲらしくはない結論が提示されて物語は完結されます。
いろは編が「皆の幸せ」を目指すのは、平穏な家庭の為には二人の関係性だけでなく、皆との関係性、社会性が大事だからだと思います。
酷な言い方をすると弥栄を目指さなかったから、うつつの子孫(ひなた)は不幸になってしまい、常世までツキを求めに旅立ったんですね…;
*)エンディングにおいていろはが「結婚観」を獲得しているのか、唐紅編をいろははクリアーしているのかについて悩んでみました。
おそらくいろはは蛟/姫編に至ってはクリア前です。性欲を自制出来ないし、嫉妬心の表明だったり独占欲も自制出来ない、相手を信じる事もまだまだ下手です。
けれども、みことの人生を背負っていく覚悟は出来ているんじゃないかと思いました。いろはってそもそも他の女に興味ないし恋愛をエンターテイメントと思っていない。告白をした時点でもはやプロポーズというか毎作ウェディングみたいな格好しているのでそもそも結婚する気はあるだろうと思いました。
いろはが結婚観をクリアしている=いろはが自己愛を獲得しているというエピソードが弥栄イベント前にあります。お風呂のシーンで幼少期に「自分は何者なのか悩んだ、讃岐に頭を撫でて貰って落ち着いた」と語っています。いろはは自分が愛されて育った事をしっかり自覚してその愛情をみことに与える事が出来ています。いろはは唐紅編はクリア済みなんですね。
子供風呂イベントでいろはにとって頭を撫でる事は最大級の愛情表現であると分かります。常世で男百歳に抱き締められて枯渇をおこしたみことの頭をいろははそっと撫でています。不安や答えの出ない悩みを忘れ、ただ近くの想いやりに感謝の出来る…彼にとって表現し得る限りの優しさだったのだと思います。
ユーザーは後ろの布団が気になっていいから押し倒せよ!くらいの気分のシーンでしょうけど。
いろは編は恋愛の蕾期間が長くなかなか進展しないように感じられます。いろはの恋愛に関する精神年齢が子供止まりなので、二人は子供の姿で、ありのまま向き合う必要があった、そういった表現なのかもしれません。
いろはは逆コナン君なので、大人の身体の状態でしか表現出来ない欲情…身体の反射的な反応と闘うシーンに追加して、ありのままの心で向き合う子供の身体のシーンが必要だったと思います。更に嫉妬やエゴも入れなきゃ、背徳感もいるよね…と。総括キャラなんで入れ込む要素が多過ぎてツキだとか祈りだとかで場面が二転三転してしまいます。
構成に四苦八苦して発売が遅れるわけです…。作者の物語全体に対する思い入れが強かったからこそいろは編はややこしくなり過ぎちゃったみたいです。別にいろはだけ特に贔屓されてるとかキャラ性の問題ではなく、物語全体構成への拘りを捨てきれなかったから、蛟/姫/紅/うつつ…と綴られてきた物語への愛情ゆえに、いろは編は複雑になったんだと思います。
*)男性視点という試みについて
いろはの「背徳感」(うつつ編)は帝の結婚相手に入れ込んでいく事です。プリーステス関連のイベントがいろはのうつつ編にあたると思います。いろはの自分都合で女性側に背徳感が無いという点も男性視点に切り替えられた理由かなあと思ったりしました。
あと、いろは編は封神という五光全員のルートで世界平和を目指す物語なので、戦隊モノにしたかったというのも理由だと考えています。
そもそも華アワセ自体がみことが五光を攻略するというより、メロメロに惚れ込んでくれる五光が奪い合って殴り合ってる物語なんで…もう別に男性視点でいいやんって感じはします。
いろははツキの半身で泉姫と同じらしいので、もう一人の主人公扱いなんだと思います。
ループ物って基本的に男の子が回って女の子を救うので男性視点の方が理解しやすく向いてますよね…。いろは編がみこと視点だったら更に複雑になってしまいます…。
*)みことはいろはに告白して泉姫に覚醒します。ここで二人は『「好き」とは何か』という議論をしています。「相手を知りたい」と思う事、お互いを一緒に知ろうとする事、相手の幸せを願い共に居たいと思う事、じゃないかといった会話をしています。この会話はいろはのテーマである「恋愛感情」への答えというだけでなく、物語の全体テーマである『恋愛とは何か』という問いに対する一つの答えであるように思います。
ずっとその感情が何かも分からず尽くし続けたいろはの魂の想いが、遂にみことへと届き…、そして自分の中に確かにある想いに気付けた…、ただただその事が嬉しくて自然と涙の出てくるエピソードでした。
この数年間二人を見守り続けてきて、度々公式サイトへと通い続けた私自身の願いも叶えられた素敵な瞬間でした。いろは編のリリースを本当にありがとうございました。
*)いろはは、アテュのタワーでも百歳と「愛とは何か」という議論をしています。
「苦しくて苛立つような…心が汚れ、相手も傷つけるようなこの感情を愛だと言うのか」
「彼女は命を懸けてまで自分を想ってくれた人を忘れずに未来を託した。それが愛。」
「苦しみ、悩むその心こそが私そのもの。私はそれを希望と呼ぼう」
「あなたの希望は全ての人間の希望です。」
(この会話を読み解くには、別の主題もあると思うのだが、)
[1]愛とは、汚い感情も含む。人の為に尽くす事も含む。『未来を託す物が愛である。』
[2]悩む心が、やがて『人類の希望』となる。
この2点を更に要約すると
『愛とは未来への希望』
といった趣旨になると思われます。
この趣旨はやはり前述の「子孫繁栄」に繋がってくるように考えました。
個人的意見ですが、恋愛をして家庭を築く事は綺麗事ばかりではありません。嫉妬・独占欲といった一時的な欲求もそうですが、価値観・倫理観の擦り合わせを何度も重ねていき新たなルールを形成して、互いの醜い部分も許容していかねばなりません。
いろはが言葉攻めの多いドSの属性を持つ背景、さらにはみことが気が強く裏表ない少女の性格を持つ背景として、ゲームの短いスパンの中で表現し得る恋愛の始まりの過程においても、二人はきちんと意見を対立させて議論を深めていく必要があったからかなと私は考えています。そして、その先にて得られる未来を託す人類の希望こそ、子孫(子供)だと私は解釈しました。
推測するに、いろは編の男女が表現している物は、一般的な乙女ゲームでよく表現されている「恋愛に憧れるうら若き乙女へ贈る御伽噺の王子様と夢物語」ではありません。「実際に人間の男女が経験する、すれ違いも苦しみもある中で育まれていく、未来への希望を二人で作り出していく過程」のような物ではないかと私は考えました。
勿論、人は神の力を持たないし世界平和なんて目標も実現出来ないので、この物語はファンタジーです。けれど、その土壌の中で出来る限り家庭を表現しようとしたから、いろはは複雑な属性を持っていったのかもしれないなと思いました。
ここまで未来を深く考えてくれているのだから、きっといろはとみことは素敵な家庭を築き、沢山の子宝に恵まれる事と、私は妄想します。その子供達は周囲の人間にも支えられて、穏やかに幸せに育って、さらにはまた大輪の華を繋げると思います。この物語が紡いでくれた深い愛を感じて、私はこの感想文を書くだけで泣きそうでした。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
*)①【まとめ】
五光のテーマ
(1)蛟『情欲』
コイン(物欲)
(2)姫空木『エゴ』
チャリス(心)
(3)唐紅『家庭観』
(4)うつつ『正義感/背徳感』『社会性』
ソード(正義)
(5)いろは『活力/目標』『感情』
ワンド(活力)
ビズログや設定資料も読んだ事ない個人的意見なんで、本気にしないで下さいね…。こういう説もあるんだーくらいでお願いします。
もしも、この作品面白かったなーって素直に思われた方がいらっしゃれば、口コミ評価を上げるようにプラスの情報発信してくださると嬉しいです。私は面白いと思ったのですが、マイナスの感想が目につくので不思議というか、追加コンテンツが出なそうで残念です…。
------以下、雑記。適当な感想文です。------

五斗について。
帝=百歳=五斗=天城=九十九(+)ニノ
乙女ゲームにおける攻略出来ないイケメンの立ち位置。
準ラスボスです。五光が戦う相手で穢れの元締めです。スートの取り纏めです。
負の恋愛感情、一方的で相手を幸せに出来ない押し付けた欲望の象徴なのだと思います。
スートは運命の輪の四大元素なんだそうです。アルカナは世界そのもので終わることのない永遠の輪廻を表すそうです。
つまり華アワセの世界、「現世(変わる世界)」そのものが帝の後悔によって創られた世界なのかもしれません。帝が反省していない古のままの世界が「常世(変わらない世界)」なのかもしれません。
華アワセは華詠(恋をする人)である五光(攻略キャラ)が、スート(運命の輪)と闘う物語として描かれています。その世界を構成する元素がコイン(物欲)、チャリス(心)、ソード(知性)、ワンド(情熱)です。
運命の籠では五光が一時的な関係で泉姫を覚醒させると泉姫は帝に輿入れする事になります。泉姫は再び輪廻に還ります。
帝はおそらく不死です。数千歳だと思います。竹取物語で帝は最後に不死となりますよね。女百歳には子供の姿があるので身体は変化するようです。魂だけが流転するのかもと思っています。
否定する相手が居らず、戦闘相手の居ない常世の百歳はおそらくハッピーエンドを持つ攻略キャラにはなりません。葛藤テーマが存在しないからです。ヤマナシオチナシのFD出たら知りませんが…。女百歳はアワセに参加しますが男百歳は参加しないのもその辺が理由だと思います。
あと、これは根拠のない直感ですがこの作者は「泥臭い人間」を描きたい人だと思いますが、主人公の絶対的味方である女百歳はユーザーにとってあまりに都合の良い進行役であり泥臭さがありませんよね…、この作者的に無さそうと思ってしまいます。もしもあっても百合方面に思います。
みことはいめにも花冠を渡していますし、ニノには別のツキが生まれて、うつつとひなたにもハッピーエンドになれるツキが生まれたようです。なので、ニノにはツキがあるという事になってます。追加FDルートが出るとしてもニノの方が百歳よりも可能性は高いと思います。
ニノのツキ→うつつとひなたのツキ→いろはとみことの新しい世界、という順番で生まれます。そしてそれが二人の最期のツキです。もう想いは永遠の物になりました。
弥栄(万歳)によって数千年から一万年後にまた別の泉姫の生まれ変わりが現れたら、その時にはもしかしたら百歳のツキはあるのかもしれません。万よりは近く千程も遠い望月の再会で命が生まれます。
*)帝バッドエンドについて。
いろは編にたった一つ短いバッドがあります。今作はランキングのご褒美イベントもありませんので、多くのユーザーは最後の最後にこのエンドを見て全シリーズのプレイを終了すると思います。(10位以内に入れとランキングで具体的指示が入るのはシリーズ初です。負ける方が難しいです)。
私は最初いろはのバッドエンドと捉えていました。でもおそらくこれは帝がメインのルートなんじゃないかと、ツイッターや板で他者の感想を読んだ時に思いました。
殆どのユーザーが「何故百歳のハッピールートが無いんだ、百歳ルート作って欲しい」と言っています(私は不要派)。
このバッドエンドには葛藤テーマがあります。『決して叶うことのない想い』という葛藤がSNS上に溢れています。このユーザーの切なさは作中の百歳自身の切なさに勝るとも劣らないんじゃないか…と感じました。
公式はユーザーが百歳推しになる事を明らかに煽っています。立ち絵も見事過ぎる。乙ゲにあまり詳しくない身分ですが他の乙ゲの非攻略キャラってここまで全面的にグッズ出したり特典ポスター付けたりしてたかな…と。
例えば純粋な少女向けの青春学園物タイトルで教師が攻略出来ないのと、華アワセで百歳が攻略出来ないのは違うんじゃないかと思い出しました。
バッドエンドで強引に結婚までしている粗筋なのに、メリバ好きしかユーザーに残っていないのに、これだけ美味しい状況なのに、その過程を細かく描かないなんて女性向けPCゲームであり得るでしょうか…。嗜好が変わっている自覚はありますが私の常識だとあり得ません。
もちろん予算の関係で削られた、追加小説でビジネスを狙っていたなどの可能性もありますが…。
私は作者は読後の切なさを重視して短い帝エンドを意図して入れているように感じます。
ここまで拘っているのであれば作品全体のコンセプトとして『不遇性』というものがあるのかもしれません。「恋愛は報われる想いと同じかそれ以上に報われない想いである」そういったもう一つの結論で最期を〆たいと感じられました。
以上、何はともあれ私は百歳編のFDが出たら間違いなく買います。(これが言いたかった)。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
②(a)トートタロット考察と感想(別ページに移動)(書きかけ)
②(b)コンセプト和歌について(別ページに移動)
*)ネタバレ少なめ(未プレイ向け)の感想はコチラの記事です。
******目次******
考察トップ
①-(0)序文
①-(1)蛟
①-(2)姫空木
①-(3)唐紅
①-(4)うつつ
①-(5)いろは
①*まとめ
①-(6)百歳
②-(a)トートタロット
②-(b)和歌
******************
*******************************
*歴代おすすめ乙女ゲームランキング
*乙女ゲーム関連記事目次
*バスタフェロウズ攻略方法
*バスタフェロウズ感想(ネタバレ少なめ)
---------------------------------
*おすすめ(一般)ゲーム感想
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
乙女ゲーム「華アワセ」のいろは編を10周しました…。沼りすぎです。
自分の個人解釈を書きたいと思います。間違っている可能性大です。
考察って赤面モノなんですが、再プレイのモチベ用に公式本が出るまでは、ボチボチ更新したいです。
①全編といろは編の主題と物語構成についての考察
分かり易く言うと「華アワセ全体の解説」です。あくまで一個人の解釈です。この複雑な物語をどういう視点で読めば、理解しやすいのか…という事を恥ずかしながら偉そうに拙文にてご説明致します。
細かく言うと、蛟/姫空木編の記録的高評価がなぜ唐紅/うつつ/いろは編で下がってしまうのか、という点を考察したいと思います。
(つまり糖度が下がっていく理由)。
(一般的乙女ゲームとの差異点について)。
(あと、いろは編で個別√無しの理由/封神システムの理由/甘党じゃない理由/新キャラの意義や場面が二転三転する理由等も考える)。
②ついでに用語解説とか複雑な各ツキとかループについても個人解釈を入れます。と思っていたが1の文章量が多過ぎて力尽きたので書きかけです…。
⇒丁寧な図解を載せているサイト様見つけましたのでご検索下さい。
*)ネタバレ全開です。長文です。ご注意下さい。
数年前1読のみで記憶朧げな部分多々あります。ご了承下さい。
*)ネタバレ少なめ(未プレイ向け)の感想はコチラの記事です。
******目次******
①-(0)序文
①-(1)蛟
①-(2)姫空木
①-(3)唐紅
①-(4)うつつ
①-(5)いろは
①*まとめ
①-(6)百歳
②-(a)トートタロット
②-(b)和歌
******************
*)物語は公開された時点で読み手一人一人の感想だけが真実であると思います。特に萌えは「考えるな、感じろ・・・!」の世界のモノなので、理屈で分解する作業や一個人の解釈は絶対的な物では無いと考えております。もしも、他者の解釈にご興味のある方、また違う視点で物語を見つめたい方が居られましたらどうぞお読み下さい。
*)自分は至高のゲームと思うんですがツイッターや板では8:2程度で賛否が割れ、アマゾンに至っては酷評(笑)と評価が分かれています。(ゲーム性は下がって格安過ぎた価格は普通に上がっているのである程度の低評価は仕方ない。他キャラ推しの人が、いろはが好みかどうかでも評価は割れる)。
私個人としてはこの物語は論理的に構成されていると考えています。
一方で、表向きには、ループの中にループを入れたり世界線が変更されたりと、一読すると複雑過ぎて、単なる作者の自己満足作品を読まされているように感じられてしまう出来になっている事も事実と思います。
ですが、この作品を私個人は読み易くシンプルな全体像を持つ物語と受け止めています。伏線は解説を明言され無くとも殆ど綺麗に回収されています。
時代の流れと共に乙ゲ業界が縮小する中、自分が何故この作品を名作と思ったかを書き残しておきます。
①序文「五光のテーマについて」(クリックで表示)
低糖化の理由は一言でいうと『各キャラでテーマが違う』からだと思います。作者が物語の主軸としている葛藤が五光によって異なるからです。
そしてその男性心理を理解してあげる事が蛟→姫→紅→うつつ→いろは、の順に難しくなってきますし、所謂「乙女ゲーム」の域を超えかかってくるので結果として糖度が下がっているように感じられます。おそらく作者としてはストーリーの順に愛情の質量は増している、より複雑になっていると解釈しているからこそこの順序なのだと思います。(ベクトルが異なるので単純比較は出来ませんしキャラの優劣を述べているわけではありません)。
よって、別に恋愛心理の比重は下がっていません。一時的な欲望として身体の接触の表現量が下がっていくだけと思います。
蛟が「中学生男子(DT)」
姫が「高校生男子(メンヘラ)」
唐紅が「社会人男性(普通)」
うつつが「幼稚園児(ヤンデレ)」としたら
いろはは「人間以前の小学生」です(笑)。
全年齢対象乙女ゲームの「華アワセ」というタイトルは、それぞれの年齢でヒトが成長を経験していく「恋愛葛藤」をテーマとして描かれています。そして女性がその男性をどう受け止めるかという過程。乙女ゲームが描こうとしている『「恋愛」とは何なのか』を突き詰めていく物語です。
低評価の理由はヤンデレゲーとかメリバゲーに分類されるので方向性がぶれていく様に感じられるだけだと思います。
以下、五光各キャラについて。
一般論としての性格。
(1)蛟…童貞型ヤンデレ。厨二男子。
(2)姫…ホラー型ヤンデレ。メンヘラ。
(3)唐紅…オレ様型。最もマトモ。
(4)うつつ…重過ぎ型ヤンデレ。逆コナン。
(5)いろは…機械型ヤンデレ。逆コナン。
(6)百歳…準ラスボス。真の不遇キャラ。
こんなところと思います。
個人的に語ります。
意見の割れるいろは編の為に蛟/姫/唐紅/うつつ編についても長文です。特に唐紅/うつつ編にもいろは編考察が入ってきます。
(1)蛟 (クリックで表示)
巽の蛟。
こちらは一般論と相違ないです。理性と肉欲で葛藤する普通の男の子を描いています。テーマは『欲情』。キャベツ畑から赤ちゃんが生まれるという女性側の幻想を信じているピュアな少女が、現実の男の子の生々しい生理的本能を受け止められるのかという葛藤や過程が丁寧に描かれています。
蛟は「愛のあるヤンデレ」に分類はされるでしょうが、ぶっちゃけごく普通の男子なので、乙女ゲームユーザーの中でも多くの人に受け入れられると思います。乙女ゲームでここまで生々しく描かれるのは珍しいですが、人間としては普遍的なテーマですよね。
図書館で押し倒された主人公がそれを悔やむ蛟の部屋に行った時、(その出来事を私から越えなければ彼を失ってしまう)と、自ら肌を晒していくエピソードは見事でした。現実の恋愛でもどこかしら女性は男性の肉欲に譲歩する事あると思います。
蛟は数斗の「コイン」と戦います。五斗は帝の執着の負の部分のようですが、「男女を不幸にする感情」「恋愛失敗要因」を象徴しているように思います。スートはタロット用語です。コインは硬貨・物質的世界・大地の事だそうです。
コインの正体は長髪男だったり露蕗だったりします。華アワセにおいてコインは「肉欲」「物理欲求」を表しているのだと考えています。
蛟を受け入れた主人公にショックを受けるいろはは、まるで娘を溺愛する父親のようですw
童貞の蛟じゃ満足出来ねえだろ、と言って迫ってくる唐紅の自尊心も可愛らしい。
良いお友達を目指して姫がホラーになるEDは衝撃的でした。良くも悪くも華アワセを代表するEDは蛟編の姫空木と思っています…;
というか、この姫EDが印象的過ぎた為にヤンデレゲー、バッドエンドゲーという地位を確立しきってしまい、結果的に後にシナリオ重視型へと偏重していった時にユーザーが付いて行けなかったのかもしれませんね…。もしかしたら元々ユーザーは物語にオチやテーマなど求めていない層が多いのかもしれません。(私も乙ゲにストーリーは求めない層です。華アワセは期待以上に面白かったです)。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
(2)姫空木 (クリックで表示)
坎の姫空木。
「乙女ゲームの愛のあるヤンデレキャラとは何か」を突き詰めたようなキャラクターでした。姫空木のテーマは『エゴ』『恋愛観』だと思います。「外面完璧なのに、中身はドロドロ」というキャラです。
『社会的にどういう振る舞いが正しいとされるのかは理解出来て実践出来ても、自分の内実を晒して受け止めてもらうにはどうしたら良いのか分からない、本当のあるがままの自分を受け入れて欲しい』という葛藤が描かれていると思います。
なぜ乙女ゲームにおいて非現実なヤンデレキャラが人気属性なのか、ヤンデレキャラの魅力とは何かを問い質すようなキャラクターです。社会とか建前とか捨てて恋愛にのめり込みたいという乙女の欲望、そしてエロのスパイスとしての嫉妬・独占…そういった物が詰め込まれていました。
女性は「完璧で頼り甲斐のある男性」という幻想を捨て、すぐ挫けて間違えを起こす男性を助けてあげよう、相互依存という関係性を目指していこうと支え合いを学びます。男性がヒロイン扱いとなるいわゆる「カウンセリングゲー」ですね…(笑)
男性側の欲望を女性が受け止める構成なので自然に糖度は高いです。ある意味R18より高いんじゃないかと…。そしてこれがMax糖度となる為、以降は失速感が否めず、意見が分かれていきます。男性向け用語である「オカズとして使えるゲーム」としての性能(女性向け糖度と同意義とする)は蛟/姫編と比べると、唐う/いろは編は下がります。
数斗の「チャリス」はツキによって正体が異なります。茉莉花だったり斧定だったりします。タロットにおいてチャリスはカップ(聖杯)の事です。水・感情を意味します。
斧定は花札制度を整えた人でゲーム内においてはおそらく「華詠」という男性像を象徴するキャラです。茉莉花は姫空木に愛されなかった少女です。乙女ゲームのユーザーを象徴しているのだと思います。華アワセにおいてチャリスは「恋愛心」「恋愛への憧れ」「押し付ける妄想」「一方的なエゴ」「自己承認欲求」などの事かなと思います。つまりはごく普通の人間です。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
(3)唐紅 (クリックで表示)
寅の唐紅。
『漢』キャラ。唐紅は「第一印象最悪だけど実は良いヒト」というポジションのキャラです。五光の中で最もメンタル強く、状況対応力があり、頼り甲斐がある。女性向けPCゲームの王道キャラですね。多分一番人気なんじゃないでしょうか。最終的には百歳と二分しているかもしれませんね…。
唐紅という言葉は有名な和歌「ちはやふる…」にも描かれる紅葉の血のような色を指します。桜花はそのまま桜。キャラデザにも胸に桜の花をさしています。唐紅というキャラのモチーフは一瞬で華々しく咲き誇り一時で散る無常観「もののあわれ」である事と流血なのかなと思います。
唐紅の価値観では、男女の仲はお互い気持ち良くなって満足し後腐れなくが漢の甲斐性というような所があります。歴史でいうとシーザーとかそういうカリスマ性がありますね…、武士道を例に出すように日本における古典的な男女の理想の恋愛観というものを叩き込まれています。女に尽くすタイプです。TPO弁えないセクハラや歯に衣きせぬ発言以外は…(笑)。
なので唐紅は自身の情欲のコントロールもお手の物で、女性を気持ち良くさせて寸止めで帰宅させるというテクニックもマナー・処世術として身に付けています。いろは推しの私でも実際に入るなら絶対桜花組です!(株を上げ過ぎてる感があるので他の五光をフォローすると、桜花組は水妹の資格を失う生徒は出ていませんが、それなりの事はしてますよ多分…)。
そういった唐紅の葛藤は蛟や姫よりも上の次元になっていきます。『一時の仲ではなく、男が女を幸せにするとはどういう事か。寄添い夫婦になるとはどういう物か。他人の人生に介在する覚悟』が唐紅のテーマと思います。つまりは『結婚観』『家庭観』ですね。
なので唐紅の父親は浮気をしてしまい、母親はそれが原因で病んでしまい、唐紅は家庭観が壊れているという設定なのだと思います。でも唐紅は厳しいお祖母さんの愛情を受けて、その教えを尊重していますよね。
五光は上司命令で仕事として一時的な恋人ごっこをしているに過ぎず、主人公は上司の結婚相手です。ホストみたいなお仕事ですね…。唐紅は一時的な関係性で深く踏み込む事に躊躇してしまいます。
唐紅の主人公の前ではいつも出来ている自己セーブが出来ずに戸惑う姿は可愛らしいですが、その程度の描写に留まります。キス以上の進展は意外となく…、ユーザーは期待していた糖度よりも低くてガッカリしてしまいます…。
家庭観がないという事は自信が無い、自己を愛せない、という事です。唐紅は一時の快楽を満たしてあげる事は出来ても、一生かけて女性を幸せにする自信がありません。
主人公は唐紅の身内にも誰にも言えなかった自己否定感を拭い、その生い立ちを肯定してあげる事で、母には彼女なりの想いがあった事を示す事で唐紅の孤独を救います。
艮(母親)と対峙する際にいめを犠牲にしてしまいます。これはうつつが原因にもなっていますが唐紅編の二人はいめを犠牲にしてエンディングを迎えます。更に唐紅は帝に逆らって泉姫の寿命を縮めようとしてしまいます。(いろはの件は唐紅に責任は無いとしました)。二つが唐紅編の男女に欠けていた点として、いろは編との対比になっている様に思います。
唐紅は数斗と戦いません。ソードに攻撃はされますが、対峙する事なく本編を終えます。おそらく唐紅/うつつ/いろはの3人の対比が華アワセとして2つのテーマになっています。うつつは恋愛心理のみで他が欠け、いろはは恋愛感情が抜けているキャラクターです。なので、唐紅は欠点が少なく五光の中で最も恋愛上手として描かれているようです。花札の五光とタロットのスートをテーマにしたいというコンセプト上で艮組を二人に分けたのかもしれませんね。
*)恋愛上手な唐紅に欠けて、恋愛下手のいろはにはある要素が1つあります。というか他の五光にはなく、いろはにある物、それは『幸せな家庭観』です。それがあるからこそいろはが最終的に選ばれる真ルートになり得ます。
いろはは世界の外から来た神の子なので地上に親を持たず、みことの祖父と両親に育てられます。主人公と義理の兄弟みたいな関係性です。一族が…とかいう背景を持つ蛟/姫/唐紅/うつつと比べて、幸せな食卓というイメージも具体的に持っていますし、何よりみことの家庭観とビジョンを共有出来ます。
唐紅/うつつ/いろは編の総論として、いろはが家庭像を提示出来るからいろは編のみは最終的なハッピーエンドを迎えると思われます。
いろはに食欲に関するエピソード、家庭に関するエピソードが多いのはそういう理由だと思います。甘党だったりそうでなかったりする理由も「甘党」を強調したいのではなく、「みことの味=家庭の味」が好きなんだという表現かもしれませんね。岩石は無理なようですが(笑)
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
(4)うつつ (クリックで表示)
丑のうつつ。
社会性と正義感が欠如して、自分と主人公以外はどうでも良いという価値観の持ち主です。ヤンデレの定義そのものに挑戦してみた感じのキャラです。
うつつはおそらく唐紅といろはの対比として設定されたんじゃないかなと推測しています。いろはは大円団キャラなので「弥栄」(体制維持=世界平和)を自身の価値観として表明します。いろは編のみことも「みんなが幸せを目指したい」と言います。その壮大過ぎる価値観と対比をなすのが、「さよなら人類」を表明するうつつと思います。
唐紅は「女性本位」でかつオババに教え込まれた漢の甲斐性を価値観として掲げます。対してうつつは恋愛至上主義でどこまでも「自分達本位」です。
社会的に結ばれない方が幸せな境遇の男女が恋愛したらどうなるのか…そういったロミジュリ的な、究極の恋愛観を詰め込んだキャラなんだと思いました。蛟/姫編では出てきません。存在せずバッドエンドすら存在しない事が悲劇なんだと思います。かろうじてラブミーという顔すら出ないモブキャラで登場します…。「いめ」と「うつつ」という二つの顔を持つ二重人格です。
うつつの内実は恋愛感情のみです。例えば社会的地位であったりに興味も執着もありません。「自分」と「主人公」、「それ以外のどうでもいいもの」、その3つしかありません。家庭を取り合った唐紅と、主人公に執着するいろはには嫉妬心や敵愾心を示すものの、五光であるとか、帝、華園、華詠…といった立場や名誉や環境、金銭、職業などに一切の執着をみせません。失った恋愛感情を取り戻して普通の「人間」になるいろはと、恋愛感情以外を切り捨ててしまううつつの大きな差は社会性だと思います。うつつのテーマは『社会性』『背徳感/正義感』だと思います。
そしてうつつの愛情は幼稚園児の愛情、つまり家族愛なのだと思います。うつつ編の女性の愛情は母性愛です。
唐う編の数斗は「ソード」です。一族を捨て駆け落ちした蛟の母親です。息子の為に他を切り捨てます。ソードは風・論理性・知性・正義・試練だそうです。
ソードは「正義感・社会性の欠如」を象徴しているのかなと思います。
また、いろは編のラスボスはうつつ編の泉姫になります。それが数斗の「ワンド」です。ワンドは火・活力・情熱・野心だそうです。
幸せな結婚をして子宝に恵まれるものの五斗に利用されてエーテル体の化け物になってしまいます。作中のうつつが「いろはを犠牲にした報いを受けた」といった趣旨の発言をしていました。華アワセにおいてワンドは「周囲を省みない情熱」を象徴しているように思います。
*)うつつのテーマとして『背徳感』を追記しました。許されない仲というのは恋愛物語の大いなるスパイスになります。
古典的なロミジュリも、源氏物語の義母への想いも、大恋愛の名著って基本的に許されない恋ですよね…。
乙女ゲーム(ギャルゲー)が一定のジャンルを築いている理由として現実には難しい浮気が楽しめるからだと述べる評論家も居ます。私はその意見に反対派で、華アワセ以外の乙女ゲームは最推し以外は基本スキップモードで速読するかそもそも√放棄するか…というような人間ですので乙ゲ主人公の浮気自体が地雷に近かったりします。そういった層を想定してうつつ編は主人公が唐紅√に入り込む前に、分岐が設定されています。
でも、そもそも3度目のツキは唐紅のツキです。それをうつつはいろはを犠牲にして奪い取っていきます。だから、華アワセはツキを持っているキャラ(タイトルキャラ)以外はバッドエンドのみというシステムなのだと思います。逆に言うとそのシステムを成立させたいから、唐紅とうつつは同じディスクなんだと思われます。
作者が挑戦したかったのは、大勢の地雷を踏まない程度ギリギリラインの背徳感だと感じられました。
うつつ編導入直後の二人の邂逅シーン、部屋の窓からうつつが入ろうとするシーンはロミジュリを模しているという暗示なのかもしれません。
*)色々書きましたが、うつつに欠点があった事で彼自体を否定しているわけではありません。常人が1週間で消えるという設定の奈落において、3度のツキで10年近く耐えたわけです。消えかかってケを帯びて人間の皮を失い化け物になっていく…そういった恐怖とも闘いながら彼は求めてはいけないツキを望んでしまった。
いろはは神の子であり人間ではないのでうつつより想いが歪み過ぎずに済んだだけです。彼は超能力者ではあっても人間に過ぎなかった、彼の限界だったのだと思います。
結果、彼は奪い取ったツキにおいても最終的にはより悲惨なバッドエンドを迎えてしまいます。
ツキの半身と泉姫の世界を変える力、更には積年の百歳とうつつの後悔によって、いくつもの祈りと奇跡が重なって、いろはとみことのツキは生まれます。
いろは編は短いバッドを除くと、いろは一本道で他の五光や百歳のバッドエンドがない事が不満点として挙げられます。
けれども、いろは編において五光と百歳は自身の無力を呪いながらも、いろはが神の力を持つ彼としても出来る限りの「皆の幸せ」を目指した事を感じ取れた為に最愛の女性を託して祝福しています。
私は個人的には、それこそが彼らにとっての究極のメリーバットという形なのかと捉えています。
だからこそ、いろは編は戦闘が封神という五光全員とみことの6人で力を合わせる演出なのだと考えています。
華アワセにとって「華」はおそらく(男性の)恋心です。和歌における「花(桜)」の意味だと思います。「アワセ」は想いを合わせて、一方的ではない相互関係を持つ事だと思われます。
いろはは、みことと各五光を口説いて協力を奮起します。いろはのエンディングは、五光全員で恋心を重ねて掴み取る、五光全員のエンディングです。
私は、不完全ではあっても必死に想いを紡いだ彼らも愛してあげたいと思います。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
(5)いろは (クリックで表示)
乾のいろは。
神の子(亥の子)=ツクヨミ(=スサノオ?)=アダム=ツキの半身=二人目の主人公です。
感情を失った真相キャラクター。
前述しましたが、最終目標は世界平和という壮大なキャラクターです…。さすが大円団キャラです。流石は神の子です。
いろはのテーマはずばり『恋愛感情』『気力』。エンディングで感情を理解してやっと人間になります。ここでいう気力は「人生の意義」です。
いろは編のラスボスが五斗ではなく「ワンド」(情熱・活力)になっているのも対比関係を重視しての事だと思います。別のツキのハッピーエンド後の泉姫のなれの果てをラスボスにするというのはグロいですよね…。
うつつ編の女性は母性ですが、いろは編の女性は生活能力皆無の少女です。ニノとひなたの評価は能天気で大バカ者、両親の愛情に育まれ守られた太陽のような女の子です。いろはの恋愛観が幼少期から止まっており、女の子を守ってあげるという少年漫画的な初恋レベルの程度だからと思います。いろはは世界を救うヒーローになりたい子なんですね。
(合わせて0番の愚者のカード(天真爛漫)との整合性だったり、いろはのS度に負けない強いヒロイン(むしろみことのが強い)である必要性があったと思いますが、それについてはまた別に纏めたいです…。)
いろはは3作終えてバッドエンドのみという不遇属性を持ちます。このキャラクターを何とか幸せにしてあげたいというモチベーションを多くのユーザーに与えるという手腕は見事でした。
もし、いろは編が全編通してのテーマだったり伏線回収に重きをおかずに乙女ゲームとしての性能を追求していればビジネスとしては大成功だっただろうと思います。でも、作者は華アワセという五編の物語としてのテーマ性を重視した事によっていろはの糖度は下がっていきます。結果として賛否両論にはなりましたが、個人的にはテーマ性を貫いた事で一部のユーザーにとっては一生物の大作として心に残る偉業を成し遂げたと思います。貫かれた『恋愛とは何か』というテーマは無意識のうちにユーザー心理に残っていく事でしょう。
いろははみことへの愛情を認識して初めて自身の発情にも気付きます。持て余したいろははショウ君に相談します。流石大円団キャラですね。ショウ君に「小学生かよ」と驚愕されます(今までどうしてたんだ、神か)。きっと周囲の男子からオカズを融通されてこれから少しずつ自己セーブ力を身に付けていくんですねぇ。人間以前だったいろは君がやっと蛟君レベルになりました(笑)
他のツキのみことを知って嫉妬心からみことを外出先に放置してしまいます。いやあ、DVキャラですなぁ…。すぐに反省するところは優しいですが。やっと姫空木君レベルですかね…。唐紅君に届くのはずっと先でしょう…。
このまま喧嘩エピソードを最後にエンディングまで行ってしまいます。あと1エピソードを途中に挟む余裕があれば読後感も変わったでしょうので、そのあたりは一工夫欲しかったです。予算の関係などもあるでしょうが…(私の嗜好に無いので気付きませんでしたが一応このイベントはさらっと愛の言葉を告げてくれるイベントだったんですね…)。
終盤のいろはは多分蛟編の中盤程度で、姫編の序盤なんじゃないか…。だからエンディングにおいても恋愛下手で不完全なのだと思います。それでも、彼女を大切にして周囲を大切にして少しずつ前進していってくれると思います。
*)いろはが自身の活力、生きる目的を「弥栄」と定めた事で、それを支えたいとみことは泉姫に覚醒します。
上記で「弥栄=天下泰平=万歳=体制維持」を私は「世界平和」のような物だと意訳しました。が、世界平和と恋愛観がどう関わっているのか、伝わり難いと反省した為表記を改めます。
「弥栄=子孫繁栄」と訳し直します。亥の子がそもそも神の子というよりは子孫繁栄という意義の強い語ですので、子孫繁栄という解釈はおそらく作者の意図と大きくは外れていないと思います。
つまり、いろはは愛情とは「子供を育てる事」だと、恋愛とは「穏やかな家庭を築く事」であると、それこそが自分の生きる意味だと決めたという事だと思います。その決意をその場にいた五光と女百歳は認めたのだと思います。
男女が恋愛して、身体重ねるのって、子育ての為でしょ?恋愛って子孫の為、家庭の為だよね?という真理なんですけど、随分と乙ゲらしくはない結論が提示されて物語は完結されます。
いろは編が「皆の幸せ」を目指すのは、平穏な家庭の為には二人の関係性だけでなく、皆との関係性、社会性が大事だからだと思います。
酷な言い方をすると弥栄を目指さなかったから、うつつの子孫(ひなた)は不幸になってしまい、常世までツキを求めに旅立ったんですね…;
*)エンディングにおいていろはが「結婚観」を獲得しているのか、唐紅編をいろははクリアーしているのかについて悩んでみました。
おそらくいろはは蛟/姫編に至ってはクリア前です。性欲を自制出来ないし、嫉妬心の表明だったり独占欲も自制出来ない、相手を信じる事もまだまだ下手です。
けれども、みことの人生を背負っていく覚悟は出来ているんじゃないかと思いました。いろはってそもそも他の女に興味ないし恋愛をエンターテイメントと思っていない。告白をした時点でもはやプロポーズというか毎作ウェディングみたいな格好しているのでそもそも結婚する気はあるだろうと思いました。
いろはが結婚観をクリアしている=いろはが自己愛を獲得しているというエピソードが弥栄イベント前にあります。お風呂のシーンで幼少期に「自分は何者なのか悩んだ、讃岐に頭を撫でて貰って落ち着いた」と語っています。いろはは自分が愛されて育った事をしっかり自覚してその愛情をみことに与える事が出来ています。いろはは唐紅編はクリア済みなんですね。
子供風呂イベントでいろはにとって頭を撫でる事は最大級の愛情表現であると分かります。常世で男百歳に抱き締められて枯渇をおこしたみことの頭をいろははそっと撫でています。不安や答えの出ない悩みを忘れ、ただ近くの想いやりに感謝の出来る…彼にとって表現し得る限りの優しさだったのだと思います。
ユーザーは後ろの布団が気になっていいから押し倒せよ!くらいの気分のシーンでしょうけど。
いろは編は恋愛の蕾期間が長くなかなか進展しないように感じられます。いろはの恋愛に関する精神年齢が子供止まりなので、二人は子供の姿で、ありのまま向き合う必要があった、そういった表現なのかもしれません。
いろはは逆コナン君なので、大人の身体の状態でしか表現出来ない欲情…身体の反射的な反応と闘うシーンに追加して、ありのままの心で向き合う子供の身体のシーンが必要だったと思います。更に嫉妬やエゴも入れなきゃ、背徳感もいるよね…と。総括キャラなんで入れ込む要素が多過ぎてツキだとか祈りだとかで場面が二転三転してしまいます。
構成に四苦八苦して発売が遅れるわけです…。作者の物語全体に対する思い入れが強かったからこそいろは編はややこしくなり過ぎちゃったみたいです。別にいろはだけ特に贔屓されてるとかキャラ性の問題ではなく、物語全体構成への拘りを捨てきれなかったから、蛟/姫/紅/うつつ…と綴られてきた物語への愛情ゆえに、いろは編は複雑になったんだと思います。
*)男性視点という試みについて
いろはの「背徳感」(うつつ編)は帝の結婚相手に入れ込んでいく事です。プリーステス関連のイベントがいろはのうつつ編にあたると思います。いろはの自分都合で女性側に背徳感が無いという点も男性視点に切り替えられた理由かなあと思ったりしました。
あと、いろは編は封神という五光全員のルートで世界平和を目指す物語なので、戦隊モノにしたかったというのも理由だと考えています。
そもそも華アワセ自体がみことが五光を攻略するというより、メロメロに惚れ込んでくれる五光が奪い合って殴り合ってる物語なんで…もう別に男性視点でいいやんって感じはします。
いろははツキの半身で泉姫と同じらしいので、もう一人の主人公扱いなんだと思います。
ループ物って基本的に男の子が回って女の子を救うので男性視点の方が理解しやすく向いてますよね…。いろは編がみこと視点だったら更に複雑になってしまいます…。
*)みことはいろはに告白して泉姫に覚醒します。ここで二人は『「好き」とは何か』という議論をしています。「相手を知りたい」と思う事、お互いを一緒に知ろうとする事、相手の幸せを願い共に居たいと思う事、じゃないかといった会話をしています。この会話はいろはのテーマである「恋愛感情」への答えというだけでなく、物語の全体テーマである『恋愛とは何か』という問いに対する一つの答えであるように思います。
ずっとその感情が何かも分からず尽くし続けたいろはの魂の想いが、遂にみことへと届き…、そして自分の中に確かにある想いに気付けた…、ただただその事が嬉しくて自然と涙の出てくるエピソードでした。
この数年間二人を見守り続けてきて、度々公式サイトへと通い続けた私自身の願いも叶えられた素敵な瞬間でした。いろは編のリリースを本当にありがとうございました。
*)いろはは、アテュのタワーでも百歳と「愛とは何か」という議論をしています。
「苦しくて苛立つような…心が汚れ、相手も傷つけるようなこの感情を愛だと言うのか」
「彼女は命を懸けてまで自分を想ってくれた人を忘れずに未来を託した。それが愛。」
「苦しみ、悩むその心こそが私そのもの。私はそれを希望と呼ぼう」
「あなたの希望は全ての人間の希望です。」
(この会話を読み解くには、別の主題もあると思うのだが、)
[1]愛とは、汚い感情も含む。人の為に尽くす事も含む。『未来を託す物が愛である。』
[2]悩む心が、やがて『人類の希望』となる。
この2点を更に要約すると
『愛とは未来への希望』
といった趣旨になると思われます。
この趣旨はやはり前述の「子孫繁栄」に繋がってくるように考えました。
個人的意見ですが、恋愛をして家庭を築く事は綺麗事ばかりではありません。嫉妬・独占欲といった一時的な欲求もそうですが、価値観・倫理観の擦り合わせを何度も重ねていき新たなルールを形成して、互いの醜い部分も許容していかねばなりません。
いろはが言葉攻めの多いドSの属性を持つ背景、さらにはみことが気が強く裏表ない少女の性格を持つ背景として、ゲームの短いスパンの中で表現し得る恋愛の始まりの過程においても、二人はきちんと意見を対立させて議論を深めていく必要があったからかなと私は考えています。そして、その先にて得られる未来を託す人類の希望こそ、子孫(子供)だと私は解釈しました。
推測するに、いろは編の男女が表現している物は、一般的な乙女ゲームでよく表現されている「恋愛に憧れるうら若き乙女へ贈る御伽噺の王子様と夢物語」ではありません。「実際に人間の男女が経験する、すれ違いも苦しみもある中で育まれていく、未来への希望を二人で作り出していく過程」のような物ではないかと私は考えました。
勿論、人は神の力を持たないし世界平和なんて目標も実現出来ないので、この物語はファンタジーです。けれど、その土壌の中で出来る限り家庭を表現しようとしたから、いろはは複雑な属性を持っていったのかもしれないなと思いました。
ここまで未来を深く考えてくれているのだから、きっといろはとみことは素敵な家庭を築き、沢山の子宝に恵まれる事と、私は妄想します。その子供達は周囲の人間にも支えられて、穏やかに幸せに育って、さらにはまた大輪の華を繋げると思います。この物語が紡いでくれた深い愛を感じて、私はこの感想文を書くだけで泣きそうでした。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
*)①【まとめ】
五光のテーマ
(1)蛟『情欲』
コイン(物欲)
(2)姫空木『エゴ』
チャリス(心)
(3)唐紅『家庭観』
(4)うつつ『正義感/背徳感』『社会性』
ソード(正義)
(5)いろは『活力/目標』『感情』
ワンド(活力)
ビズログや設定資料も読んだ事ない個人的意見なんで、本気にしないで下さいね…。こういう説もあるんだーくらいでお願いします。
もしも、この作品面白かったなーって素直に思われた方がいらっしゃれば、口コミ評価を上げるようにプラスの情報発信してくださると嬉しいです。私は面白いと思ったのですが、マイナスの感想が目につくので不思議というか、追加コンテンツが出なそうで残念です…。
------以下、雑記。適当な感想文です。------
(6)百歳 (クリックで表示)
五斗について。
帝=百歳=五斗=天城=九十九(+)ニノ
乙女ゲームにおける攻略出来ないイケメンの立ち位置。
準ラスボスです。五光が戦う相手で穢れの元締めです。スートの取り纏めです。
負の恋愛感情、一方的で相手を幸せに出来ない押し付けた欲望の象徴なのだと思います。
スートは運命の輪の四大元素なんだそうです。アルカナは世界そのもので終わることのない永遠の輪廻を表すそうです。
つまり華アワセの世界、「現世(変わる世界)」そのものが帝の後悔によって創られた世界なのかもしれません。帝が反省していない古のままの世界が「常世(変わらない世界)」なのかもしれません。
華アワセは華詠(恋をする人)である五光(攻略キャラ)が、スート(運命の輪)と闘う物語として描かれています。その世界を構成する元素がコイン(物欲)、チャリス(心)、ソード(知性)、ワンド(情熱)です。
運命の籠では五光が一時的な関係で泉姫を覚醒させると泉姫は帝に輿入れする事になります。泉姫は再び輪廻に還ります。
帝はおそらく不死です。数千歳だと思います。竹取物語で帝は最後に不死となりますよね。女百歳には子供の姿があるので身体は変化するようです。魂だけが流転するのかもと思っています。
否定する相手が居らず、戦闘相手の居ない常世の百歳はおそらくハッピーエンドを持つ攻略キャラにはなりません。葛藤テーマが存在しないからです。ヤマナシオチナシのFD出たら知りませんが…。女百歳はアワセに参加しますが男百歳は参加しないのもその辺が理由だと思います。
あと、これは根拠のない直感ですがこの作者は「泥臭い人間」を描きたい人だと思いますが、主人公の絶対的味方である女百歳はユーザーにとってあまりに都合の良い進行役であり泥臭さがありませんよね…、この作者的に無さそうと思ってしまいます。もしもあっても百合方面に思います。
みことはいめにも花冠を渡していますし、ニノには別のツキが生まれて、うつつとひなたにもハッピーエンドになれるツキが生まれたようです。なので、ニノにはツキがあるという事になってます。追加FDルートが出るとしてもニノの方が百歳よりも可能性は高いと思います。
ニノのツキ→うつつとひなたのツキ→いろはとみことの新しい世界、という順番で生まれます。そしてそれが二人の最期のツキです。もう想いは永遠の物になりました。
弥栄(万歳)によって数千年から一万年後にまた別の泉姫の生まれ変わりが現れたら、その時にはもしかしたら百歳のツキはあるのかもしれません。万よりは近く千程も遠い望月の再会で命が生まれます。
*)帝バッドエンドについて。
いろは編にたった一つ短いバッドがあります。今作はランキングのご褒美イベントもありませんので、多くのユーザーは最後の最後にこのエンドを見て全シリーズのプレイを終了すると思います。(10位以内に入れとランキングで具体的指示が入るのはシリーズ初です。負ける方が難しいです)。
私は最初いろはのバッドエンドと捉えていました。でもおそらくこれは帝がメインのルートなんじゃないかと、ツイッターや板で他者の感想を読んだ時に思いました。
殆どのユーザーが「何故百歳のハッピールートが無いんだ、百歳ルート作って欲しい」と言っています(私は不要派)。
このバッドエンドには葛藤テーマがあります。『決して叶うことのない想い』という葛藤がSNS上に溢れています。このユーザーの切なさは作中の百歳自身の切なさに勝るとも劣らないんじゃないか…と感じました。
公式はユーザーが百歳推しになる事を明らかに煽っています。立ち絵も見事過ぎる。乙ゲにあまり詳しくない身分ですが他の乙ゲの非攻略キャラってここまで全面的にグッズ出したり特典ポスター付けたりしてたかな…と。
例えば純粋な少女向けの青春学園物タイトルで教師が攻略出来ないのと、華アワセで百歳が攻略出来ないのは違うんじゃないかと思い出しました。
バッドエンドで強引に結婚までしている粗筋なのに、メリバ好きしかユーザーに残っていないのに、これだけ美味しい状況なのに、その過程を細かく描かないなんて女性向けPCゲームであり得るでしょうか…。嗜好が変わっている自覚はありますが私の常識だとあり得ません。
もちろん予算の関係で削られた、追加小説でビジネスを狙っていたなどの可能性もありますが…。
私は作者は読後の切なさを重視して短い帝エンドを意図して入れているように感じます。
ここまで拘っているのであれば作品全体のコンセプトとして『不遇性』というものがあるのかもしれません。「恋愛は報われる想いと同じかそれ以上に報われない想いである」そういったもう一つの結論で最期を〆たいと感じられました。
以上、何はともあれ私は百歳編のFDが出たら間違いなく買います。(これが言いたかった)。
****目次**** トップ*序文*蛟*姫空木*唐紅*うつつ*いろは*まとめ*百歳 トート*和歌 ****
②(a)トートタロット考察と感想(別ページに移動)(書きかけ)
②(b)コンセプト和歌について(別ページに移動)
*)ネタバレ少なめ(未プレイ向け)の感想はコチラの記事です。
******目次******
考察トップ
①-(0)序文
①-(1)蛟
①-(2)姫空木
①-(3)唐紅
①-(4)うつつ
①-(5)いろは
①*まとめ
①-(6)百歳
②-(a)トートタロット
②-(b)和歌
******************
*******************************
*歴代おすすめ乙女ゲームランキング
*乙女ゲーム関連記事目次
*バスタフェロウズ攻略方法
*バスタフェロウズ感想(ネタバレ少なめ)
---------------------------------
*おすすめ(一般)ゲーム感想
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
閃の軌跡3の情報がいくつか揃ってきたので、どんな内容になるのかなあという妄想を垂れ流してみます。
(1)閃の軌跡2を振り返って
私は閃の軌跡2のストーリーの出来はそれは酷いものだったと評価しております。10点満点で0点レベルですねー…。
理由としては…
①起承転結がない。
べつに序破急でも何部構成でも物語として成り立っていれば良いのですが、とにかく主題が不明のため、山無しオチ無しという結果に感じられます。
②主人公サイドの目的が明確でない。
空や零は、地域の治安維持のお仕事という分かりやすいお題目がありました。
しかし、閃1&2は学生の物語なので国政や戦争を主導するお題目がないんですよね…。
ちょっと強いオモチャ(現実でいうと原爆みたいな?)を手に入れてみたから、ちょっと遊んで周辺各国を侵略してしまいました…という。何ともお粗末なお話でした。
③オリビエの意図が分かりにくい。
帝国編はオズボーンvsオリビエの国策をどうするかという意見の対立が主題のハズだと思われます。
リィンは途中で親子関係が出てきたり、灰の起動者とやらになりますが、帝国全体の趨勢に対し意見を持たない脇役でしかありません。
ただ、庶出の皇子様であるオリビエは、オズボーンに対してどうも裏の部分が色濃い怪しい奴だと警戒しているだけで、「国の為にならないから今直ぐ殺してしまった方がいい」とか明確な目的を持ってはいないんですよね。叩けば埃が出るんじゃないかな、くらいのテンションかなと。
オズボーンはハーメルの虐殺を利用して宰相に成り上がったり、ウロボロスと取り引きしてリベールに攻め込もうとしたり、政治に闇は付き物かもしれませんが、どうも正道でない部分が強い。底知れない箇所が見え隠れするから、此奴の目的は何だ、と訝しんでるくらいなんですよね。つまり、主人公やオリビエが能動的に動けない、黒幕も尻尾を出さない…と、大きくお話が動く状況がないまま2作消化してしまい3作目も同じ感じ(結社については少しは動きそう)と思われれる点が物語として弱いんですよね…。
以上が、簡単な閃の軌跡のストーリー構成を評価しない理由になります。
(2)閃の軌跡3の概要予想
次回作も同じ様なノリなのかというと、Yesだと思われます。
リィン君は親子関係に淡い期待をしてしまっておりオズボーンが悪だと断定する程には至らなそうですし(そうでないと侵略に貢献した意図が想像出来ない)、オリビエに至っても粗探しは続けるものの政治の道具に出来そうなキーカードまでは入手出来てはいなそうです。
よって、『閃の軌跡3』は足掛け5年目(零からカウントするともっと長い)でありながら、リィンとオリビエは未だに蚊帳の外で、結社側とオズボーン側が兵器(至宝?)の取り合いをするテロの表面を横から眺める、という内容になるのではないか…と予想されます。
実際には、結社の執行者や傭兵と刃を交えるのはリィンやランディ達第二分校勢力かも知れません。
ただ、結社側の指揮陣営(キャラ表だとカンパネルラ?)とオズボーン陣営から見れば第二分校は単なる一部隊かなと。その両陣営の意図を少しでも忖度出来る知識を有するのは教会勢力くらいじゃないか…と。オリビエは至宝やら結社の意図くらいは予測しているかも知れませんが。リィンの役割は、リアクション芸人ばりの「えぇ!?」というアクションだけかな…;;
(3)今後の続編数について
ところで、『閃の軌跡3』で何処までストーリーが進むかですが、私は『閃の軌跡4』か別の話があと一つくらいで、クロスベル解放まで進むかなと予想しています。
七曜暦1204年4月から1205年3月の一年間で零、碧、閃1、閃2の4作を消費して帝国がクロスベルを占領するまでが描かれました。
七曜暦1207年の終わりまでにはクロスベルは解放されるそうです。オズボーン失脚が明文化されていたかは覚えておりません;;
閃の軌跡3の始点は1206年4月になりそうです。クロスベル解放まで1年半程かかるのかなと。占領から丁度2年後と換算すると1207年1月頃なので10ヶ月程で解放される可能性も考えられます。
短く見積もって10ヶ月、長く見積もって1年9ヶ月ですと、過去の例から考えて(4作で丸1年)、1作で納める能力はファルコムスタッフには無さそうだなあと予想してしまいます。
まあ、平均取ってあと2作か3作必要なのかなーと考えています。
すると、夫々の作品ごとに何か事件を入れなくてはいけませんから、下記の様な構成になるのかなあと…。
閃3:結社が至宝を顕現させるかその足掛かりを入手するまで。(結社の執行者はリィン達が倒してオズボーンサイドが利を掠めとるのかも?)
閃4:至宝を手にしたオズボーンの真意が見えてきて、オリビエ連合勢力がその意を挫くまで。(至宝は教会が入手するか、消滅するか…?)
碧2:弱ったオズボーン勢力をルーファスがまとめ直そうとするも、ロイド達がクロスベル解放
仮に碧2とした箇所は上手くしたら閃4くらいには入るかもですねー。いずれにせよ読後の満足感らしきものを得るにはまだ先は長そうです。
(4)帝国の至宝
ところで、帝国の至宝って何でしょう??
リベールが「空」で、クロスベルが「幻」(零)でしたから、帝国は「焔」でしょうか。
二柱の巨神が辺境に落ちたそうですので、2つあるのか、1つはクロスベル扱いなのか…。
ゲームシナリオ観点から見ればオズボーンが占領方策を取るのは至宝目的なのかもしれません。
辺境といえば、西のジュライやら北のノーザンブリアや東のクロスベルや北東のノルドあたりでしょうか…?
巨神が落とした力が騎神でそれは7つあるそうです。今のところ帝国には5つ程出ていて、緋のテスタロッサ(魔竜の返り血で呪われたとか魔神になったとか)、灰のヴァリマール、蒼のオルディーネ、あと壊れた紫紺の騎神、ローエングリン城にも一つあるらしい。
残りは2、3個。えっと、クロスベルに出てきた神機は結社の製作物なんでしたっけ?クロスベルと帝国の伝承はまた別物なのかな??
もう、全てがどうでもいいと思うレベルでややこしい(笑)理解出来ない設定は単なる作者の自己満足でしかないのですが、ファルコムスタッフはそれを理解していないようで…。
残りの騎神は閃3、4で出てきそうにも感じます。
また、結社が企画し、オズボーンが乗っ取った幻焔計画とやらは、「クロスベルの虚ろなる幻をもって、帝国の焔を呼び起こす」とかそんな謳い文句でした。
文章通りに受け取ると、二柱の巨神の一つが「幻」でもう一つが「焔」でしょうか…。
閃2で既に「焔」は呼び起こされていそうです。閃3はその焔を結社が再び入手しようと暗躍するお話になりそうに予想されます。
なんとなく帝国編の全体像が見えてきましたが、閃1&2でようやく空FC程度の進行状況だと推測出来ます。空SCの様に物語が終わった満足感が得られるのはやっぱり閃3&4とあと二作消費しそうな予感がします…。
そもそも、スタッフの能力オーバーしていそうですし、もう少し短期の企画の方がビジネス的にも、ユーザーの評価面でも良かったように思います。
(5)オズボーンの目的
リベール、クロスベル、帝国編においてオズボーンは影の黒幕として描かれています。表向きは帝国の領土を拡大させたいようですが、それが何故かは分かりません。
帝国国民の為にさらなる豊かさを目指している理想主義者にはとても見えません。ハーメル事件等々から目的の為には手段を選ばない冷徹な内面が想像されます。
帝国国内でさらなる政治の絶対的な権力が欲しいのでしょうか…。もう十分な権力を持っており帝国はそもそも広大過ぎる敷地がありますから、領土拡大が長い目で見て国益となるのかは甚だ疑問です。事実、クロスベルではレジスタンス活動が盛んなようで文化的背景・経済的利便性など真の意味で併合されるのは1世代は辛抱せねばならなそうです。つまり、エレボニア帝国の国益の為に拡大政策を強行しているのかは微妙な所かなあと…。
産業革命後のスペイン、ポルトガル、イギリスなどを見ると、圧倒的科学力の差があれば可能そうには感じますが、軌跡の世界では動力革命の技術は大陸の主要な国々へは弟子達が技術を広めているように感じられます。少なくともオーバルアーツは汎用装備であり、飛行船はメジャーな乗り物で幕末の日本が黒船に驚愕したような差分ではなさそうです。
つまり、帝国がどれだけ領土を拡大しようと、モンゴル帝国やアレキサンドロス大王のように大部分は支配が行き届かず短期間で瓦解するのではないかと…私にはそう思えてしまいます。
そもそもオズボーンは身分社会意識が根強く残る帝国の歴史を遡っても異端と言える平民出(しかも出自は外国のノーザンブリアあたり?)です。一時的な乱の平定では駆逐しきれない敵を国内に抱え続けています。内外に敵を作り過ぎると信長のように内から裏切られる可能性も考えられます。実際、レクターが側近を務めているのはオズボーンを倒したいからだったような記憶が何処かにあります。(その役割ごとクロウという新キャラに取られた可能性もありますが…)
オズボーンの急進的な拡大政策は帝国にもオズボーン自身にもあまりメリットがないと私は感じています。
だったら、オズボーンには帝国の都合や自身の安定的な立ち位置よりも、更に強く求めている目的があるのではないか…と予測も出来ます。
オズボーンが幻焔計画を結社から乗っ取るのは、乗っ取った後に至宝で世界征服を狙うというよりも、至宝を入手する事がオズボーンにとっての優先すべき第1目的ではないのかと考えてしまいました。オズボーンは結社の盟主や、教会組織のように、至宝を入手して成し遂げたい壮大な目的があるのかもしれません。
オズボーンが北の出身らしいと聞いて思い浮かぶのは、塩の杭事件です。たしか教授やサラもノーザンブリアの出身でした。(何処でその情報があったのか、閃2終盤だったように思いますが…)
あと、リィンの鬼の力が遺伝したものなのかどうか…オズボーンも鬼の力とやらが使えるなら、オズボーンの目的にその力の背景も関係してきそうです。
クロウに撃ち抜かれて、死体が検分された後に蘇ったカラクリも明かされていません。検分した職員を抱きかかえればいいじゃないかとも思いましたが、クレアは「確かに死んでいた」と言っていたような記憶が朧げにあります。
吸血鬼なんですかねえ?
(6)メガネと緑髪
閃の軌跡3のキャラ表を眺めると…眼鏡が居ない!
過去の眼鏡キャラで誰かが裏切る可能性もありますが、ストーリーを纏める為にもう裏切り者(二面性のあるキャラ)は必要ないのかなっと…。
新キャラが多いとはいえ、各国編で眼鏡一人なのかもしれませんし、既にマキアス、エマ、カール、トマス、アリサ母、フィーの兄貴、マクバーン…眼鏡かけてるキャラはいっぱい居ますしね。
今作プレイアブルに緑髪がいるんですよね…。ネギやワジっぽい位置かな〜と邪推しつつ、いやいやトマスが居るし…。クロスベルにワジとネギが来ていたので、帝国にもトマス以外にもう一人来る可能性もありますし、そもそもトヴァルと縁があるカーネリア御自ら姿を見せる可能性もあるのかな〜と妄想しています。
まあ、予測出来ないトンデモ設定は置いておいて、今後の軌跡シリーズがどういった風に広げた風呂敷を纏めるのかは、楽しみな点です(^_^)
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
(1)閃の軌跡2を振り返って
私は閃の軌跡2のストーリーの出来はそれは酷いものだったと評価しております。10点満点で0点レベルですねー…。
理由としては…
①起承転結がない。
べつに序破急でも何部構成でも物語として成り立っていれば良いのですが、とにかく主題が不明のため、山無しオチ無しという結果に感じられます。
②主人公サイドの目的が明確でない。
空や零は、地域の治安維持のお仕事という分かりやすいお題目がありました。
しかし、閃1&2は学生の物語なので国政や戦争を主導するお題目がないんですよね…。
ちょっと強いオモチャ(現実でいうと原爆みたいな?)を手に入れてみたから、ちょっと遊んで周辺各国を侵略してしまいました…という。何ともお粗末なお話でした。
③オリビエの意図が分かりにくい。
帝国編はオズボーンvsオリビエの国策をどうするかという意見の対立が主題のハズだと思われます。
リィンは途中で親子関係が出てきたり、灰の起動者とやらになりますが、帝国全体の趨勢に対し意見を持たない脇役でしかありません。
ただ、庶出の皇子様であるオリビエは、オズボーンに対してどうも裏の部分が色濃い怪しい奴だと警戒しているだけで、「国の為にならないから今直ぐ殺してしまった方がいい」とか明確な目的を持ってはいないんですよね。叩けば埃が出るんじゃないかな、くらいのテンションかなと。
オズボーンはハーメルの虐殺を利用して宰相に成り上がったり、ウロボロスと取り引きしてリベールに攻め込もうとしたり、政治に闇は付き物かもしれませんが、どうも正道でない部分が強い。底知れない箇所が見え隠れするから、此奴の目的は何だ、と訝しんでるくらいなんですよね。つまり、主人公やオリビエが能動的に動けない、黒幕も尻尾を出さない…と、大きくお話が動く状況がないまま2作消化してしまい3作目も同じ感じ(結社については少しは動きそう)と思われれる点が物語として弱いんですよね…。
以上が、簡単な閃の軌跡のストーリー構成を評価しない理由になります。
(2)閃の軌跡3の概要予想
次回作も同じ様なノリなのかというと、Yesだと思われます。
リィン君は親子関係に淡い期待をしてしまっておりオズボーンが悪だと断定する程には至らなそうですし(そうでないと侵略に貢献した意図が想像出来ない)、オリビエに至っても粗探しは続けるものの政治の道具に出来そうなキーカードまでは入手出来てはいなそうです。
よって、『閃の軌跡3』は足掛け5年目(零からカウントするともっと長い)でありながら、リィンとオリビエは未だに蚊帳の外で、結社側とオズボーン側が兵器(至宝?)の取り合いをするテロの表面を横から眺める、という内容になるのではないか…と予想されます。
実際には、結社の執行者や傭兵と刃を交えるのはリィンやランディ達第二分校勢力かも知れません。
ただ、結社側の指揮陣営(キャラ表だとカンパネルラ?)とオズボーン陣営から見れば第二分校は単なる一部隊かなと。その両陣営の意図を少しでも忖度出来る知識を有するのは教会勢力くらいじゃないか…と。オリビエは至宝やら結社の意図くらいは予測しているかも知れませんが。リィンの役割は、リアクション芸人ばりの「えぇ!?」というアクションだけかな…;;
(3)今後の続編数について
ところで、『閃の軌跡3』で何処までストーリーが進むかですが、私は『閃の軌跡4』か別の話があと一つくらいで、クロスベル解放まで進むかなと予想しています。
七曜暦1204年4月から1205年3月の一年間で零、碧、閃1、閃2の4作を消費して帝国がクロスベルを占領するまでが描かれました。
七曜暦1207年の終わりまでにはクロスベルは解放されるそうです。オズボーン失脚が明文化されていたかは覚えておりません;;
閃の軌跡3の始点は1206年4月になりそうです。クロスベル解放まで1年半程かかるのかなと。占領から丁度2年後と換算すると1207年1月頃なので10ヶ月程で解放される可能性も考えられます。
短く見積もって10ヶ月、長く見積もって1年9ヶ月ですと、過去の例から考えて(4作で丸1年)、1作で納める能力はファルコムスタッフには無さそうだなあと予想してしまいます。
まあ、平均取ってあと2作か3作必要なのかなーと考えています。
すると、夫々の作品ごとに何か事件を入れなくてはいけませんから、下記の様な構成になるのかなあと…。
閃3:結社が至宝を顕現させるかその足掛かりを入手するまで。(結社の執行者はリィン達が倒してオズボーンサイドが利を掠めとるのかも?)
閃4:至宝を手にしたオズボーンの真意が見えてきて、オリビエ連合勢力がその意を挫くまで。(至宝は教会が入手するか、消滅するか…?)
碧2:弱ったオズボーン勢力をルーファスがまとめ直そうとするも、ロイド達がクロスベル解放
仮に碧2とした箇所は上手くしたら閃4くらいには入るかもですねー。いずれにせよ読後の満足感らしきものを得るにはまだ先は長そうです。
(4)帝国の至宝
ところで、帝国の至宝って何でしょう??
リベールが「空」で、クロスベルが「幻」(零)でしたから、帝国は「焔」でしょうか。
二柱の巨神が辺境に落ちたそうですので、2つあるのか、1つはクロスベル扱いなのか…。
ゲームシナリオ観点から見ればオズボーンが占領方策を取るのは至宝目的なのかもしれません。
辺境といえば、西のジュライやら北のノーザンブリアや東のクロスベルや北東のノルドあたりでしょうか…?
巨神が落とした力が騎神でそれは7つあるそうです。今のところ帝国には5つ程出ていて、緋のテスタロッサ(魔竜の返り血で呪われたとか魔神になったとか)、灰のヴァリマール、蒼のオルディーネ、あと壊れた紫紺の騎神、ローエングリン城にも一つあるらしい。
残りは2、3個。えっと、クロスベルに出てきた神機は結社の製作物なんでしたっけ?クロスベルと帝国の伝承はまた別物なのかな??
もう、全てがどうでもいいと思うレベルでややこしい(笑)理解出来ない設定は単なる作者の自己満足でしかないのですが、ファルコムスタッフはそれを理解していないようで…。
残りの騎神は閃3、4で出てきそうにも感じます。
また、結社が企画し、オズボーンが乗っ取った幻焔計画とやらは、「クロスベルの虚ろなる幻をもって、帝国の焔を呼び起こす」とかそんな謳い文句でした。
文章通りに受け取ると、二柱の巨神の一つが「幻」でもう一つが「焔」でしょうか…。
閃2で既に「焔」は呼び起こされていそうです。閃3はその焔を結社が再び入手しようと暗躍するお話になりそうに予想されます。
なんとなく帝国編の全体像が見えてきましたが、閃1&2でようやく空FC程度の進行状況だと推測出来ます。空SCの様に物語が終わった満足感が得られるのはやっぱり閃3&4とあと二作消費しそうな予感がします…。
そもそも、スタッフの能力オーバーしていそうですし、もう少し短期の企画の方がビジネス的にも、ユーザーの評価面でも良かったように思います。
(5)オズボーンの目的
リベール、クロスベル、帝国編においてオズボーンは影の黒幕として描かれています。表向きは帝国の領土を拡大させたいようですが、それが何故かは分かりません。
帝国国民の為にさらなる豊かさを目指している理想主義者にはとても見えません。ハーメル事件等々から目的の為には手段を選ばない冷徹な内面が想像されます。
帝国国内でさらなる政治の絶対的な権力が欲しいのでしょうか…。もう十分な権力を持っており帝国はそもそも広大過ぎる敷地がありますから、領土拡大が長い目で見て国益となるのかは甚だ疑問です。事実、クロスベルではレジスタンス活動が盛んなようで文化的背景・経済的利便性など真の意味で併合されるのは1世代は辛抱せねばならなそうです。つまり、エレボニア帝国の国益の為に拡大政策を強行しているのかは微妙な所かなあと…。
産業革命後のスペイン、ポルトガル、イギリスなどを見ると、圧倒的科学力の差があれば可能そうには感じますが、軌跡の世界では動力革命の技術は大陸の主要な国々へは弟子達が技術を広めているように感じられます。少なくともオーバルアーツは汎用装備であり、飛行船はメジャーな乗り物で幕末の日本が黒船に驚愕したような差分ではなさそうです。
つまり、帝国がどれだけ領土を拡大しようと、モンゴル帝国やアレキサンドロス大王のように大部分は支配が行き届かず短期間で瓦解するのではないかと…私にはそう思えてしまいます。
そもそもオズボーンは身分社会意識が根強く残る帝国の歴史を遡っても異端と言える平民出(しかも出自は外国のノーザンブリアあたり?)です。一時的な乱の平定では駆逐しきれない敵を国内に抱え続けています。内外に敵を作り過ぎると信長のように内から裏切られる可能性も考えられます。実際、レクターが側近を務めているのはオズボーンを倒したいからだったような記憶が何処かにあります。(その役割ごとクロウという新キャラに取られた可能性もありますが…)
オズボーンの急進的な拡大政策は帝国にもオズボーン自身にもあまりメリットがないと私は感じています。
だったら、オズボーンには帝国の都合や自身の安定的な立ち位置よりも、更に強く求めている目的があるのではないか…と予測も出来ます。
オズボーンが幻焔計画を結社から乗っ取るのは、乗っ取った後に至宝で世界征服を狙うというよりも、至宝を入手する事がオズボーンにとっての優先すべき第1目的ではないのかと考えてしまいました。オズボーンは結社の盟主や、教会組織のように、至宝を入手して成し遂げたい壮大な目的があるのかもしれません。
オズボーンが北の出身らしいと聞いて思い浮かぶのは、塩の杭事件です。たしか教授やサラもノーザンブリアの出身でした。(何処でその情報があったのか、閃2終盤だったように思いますが…)
あと、リィンの鬼の力が遺伝したものなのかどうか…オズボーンも鬼の力とやらが使えるなら、オズボーンの目的にその力の背景も関係してきそうです。
クロウに撃ち抜かれて、死体が検分された後に蘇ったカラクリも明かされていません。検分した職員を抱きかかえればいいじゃないかとも思いましたが、クレアは「確かに死んでいた」と言っていたような記憶が朧げにあります。
吸血鬼なんですかねえ?
(6)メガネと緑髪
閃の軌跡3のキャラ表を眺めると…眼鏡が居ない!
過去の眼鏡キャラで誰かが裏切る可能性もありますが、ストーリーを纏める為にもう裏切り者(二面性のあるキャラ)は必要ないのかなっと…。
新キャラが多いとはいえ、各国編で眼鏡一人なのかもしれませんし、既にマキアス、エマ、カール、トマス、アリサ母、フィーの兄貴、マクバーン…眼鏡かけてるキャラはいっぱい居ますしね。
今作プレイアブルに緑髪がいるんですよね…。ネギやワジっぽい位置かな〜と邪推しつつ、いやいやトマスが居るし…。クロスベルにワジとネギが来ていたので、帝国にもトマス以外にもう一人来る可能性もありますし、そもそもトヴァルと縁があるカーネリア御自ら姿を見せる可能性もあるのかな〜と妄想しています。
まあ、予測出来ないトンデモ設定は置いておいて、今後の軌跡シリーズがどういった風に広げた風呂敷を纏めるのかは、楽しみな点です(^_^)
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
今更、仁王を買いました〜。
「劣化ダクソ」という評判聞いてまして、いつか買おうと思いつつ、ホライゾンやらダクソ3やら優先させてましたー;
まだ、チュートリアル終わって、九州編の序盤です。
聞いてたとおり我が家の評価も「劣化ダクソ」だなあと…。
といっても、今後フロムの新作も不透明なので、それに似た代替品としての価値は十分にあります!

仁王は、「ダークソウル」の基本システムに、「ディアブロ」のトレハン&ハクスラ要素を足して、世界観は「鬼武者」と言われています。
個人的にアクション要素が魅力のダークソウルに、トレハンとハクスラ要素は不要だと思いました。単なる作業ゲーになってしまいます…。
ううーん…、何か熱中度が足りないなーという感じです。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
「劣化ダクソ」という評判聞いてまして、いつか買おうと思いつつ、ホライゾンやらダクソ3やら優先させてましたー;
まだ、チュートリアル終わって、九州編の序盤です。
聞いてたとおり我が家の評価も「劣化ダクソ」だなあと…。
といっても、今後フロムの新作も不透明なので、それに似た代替品としての価値は十分にあります!
仁王は、「ダークソウル」の基本システムに、「ディアブロ」のトレハン&ハクスラ要素を足して、世界観は「鬼武者」と言われています。
個人的にアクション要素が魅力のダークソウルに、トレハンとハクスラ要素は不要だと思いました。単なる作業ゲーになってしまいます…。
ううーん…、何か熱中度が足りないなーという感じです。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
・歴史小説を読んでたら、久々に無双がやりたくなったので、三国無双を10年ぶりに購入しました。
全くゲーム性が変化してなくて笑ってしまいました。
ダクソなどのアクション性の高めなゲームを好む自分からすると単なる作業ゲー…。歴史好きか、乙女ゲーもしくはギャルゲー好きでないと楽しめないようになってしまい、質の低い古びたゲームで終わってしまいそうな事が残念です。
・あわせて、コーエーの描写に不満があります。
ここで、自分の三国志への拘りを書いておきます。人によって好きな国や人物も異なると思うので…。
私は三国志では周瑜が好きです。劉備や孔明、関羽は美化されてて子供心に苦手でした。8才くらいで既に嘘臭いと感じてました(笑)。曹操や司馬懿の方が中原を抑えたりと必要な時に的確な手をうてて後継者も育てている様に感じ、個人的には蜀よりはやや呉や魏よりです。元々儒教的な歴史観があまり好みでなかったせいか、始皇帝や項羽や商鞅も韓非子も孫子二代も好きな方です。(法治主義が性悪説から発展したものなら広義の儒教かもしれないので、徳治第一主義が苦手とか、表現すべきなのかもです。別に悪逆非道な専制を好むわけでないです。)暗に武帝への不満を滲ませる司馬遷も好きです。天道是非、よって蜀漢正統説は否定的です。

ちょっと偉そうに私が「中原」と称した地理について語ると、定義的には黄河下流域あたりを言うそうですが、ここでは咸陽・長安・洛陽あたりも含むとします。
なんで黄河がこんなに重要拠点と思うかというと、文化的背景や漢帝国の要所でもありましたが経済流通の大部分をしめているからです。
つまり、曹操や司馬懿の方がずっとお金持ちだったと考えられそうです。(三国時代は長引く官吏の腐敗や戦乱によって中原自体も衰えてはいたそうです。)長江流域は中華の中でも肥沃な穀倉地だそうですから呉の得た地理はまだ意味がありますが、蜀というのは見た目の面積では三国並び立っていそうに見えますが、実際の規模は面積ほどの価値はなく、二強状態に小さな蜀がくっついていってるだけように私には見えました。小学生がそう思ったのだから、きっと当時の人もそう思っていたのだと思います。
こういうと少し酷いかもしれませんが、(春秋)戦国時代の韓程度のバランサーでしかなかったように感じます。つまり孔明が目指したのは、天下統一して平和な世をつくることではなく、必要以上に戦乱の世を長引かせて、民を疲弊させる事だったのでは、と私には感じられたのです。
↓に春秋時代の蜀の位置を示して見ます。
秦の始皇帝の小説などを読むと謀反した貴族を蜀に流す刑罰を行っていたりしますから、蜀というのは中原から見たら、田舎も田舎、中華にすら入らない(肌色領域)、辺境の地であったと予想されます。漢の時代を挟めばもう少し蜀の地位は上がってはいそうですが、それでも、経済拠点からは少し外れていそうに感じます。

これは、大人になってから知った知識ですが、三国志演義は千年後の明の時代のものとされています。その前の元に支配された時代に民衆が漢民族による中華統一を願った事と、漢や明が支配の道具として儒教を利用した事が、幅広く演義が流通した背景にあるそうです。
それを知ってしまって、蜀が天下を取るというのは、夢物語にしか感じなくなってしまい、劉備も孔明も欲深い俗物に感じてしまいました。無双内でも曹操が「口だけでは駄目だ」っぽい揶揄をしていますが、私にもそう見えてしまったのです。
まあ、別に中華統一しなくてもヨーロッパみたいに分裂しても戦争が減るならそれで良い気もしますが、秦や漢の統一によって文化が統一された事や儒教の広がりによって中華の民は統一を求める意識が強かったのかなと感じます。

拙い中華論はともかく、周瑜という人は「三国志」の描写だけでも万能な人で、幼い私にはまさに憧れの英雄という感想を持ちました。女顔というのは演義や後世の脚色でしょうが、歴史書においても文句のつけようのない多才な人です。当時の歴史書が事実だけを書いているかは謎ですが、一応そこそこ信頼に足るとされています。
①容姿が良い(肌が白いとか美周郎というのは演義や後世の脚色。実際は男性から見て格好良い恰幅だったのかも?無双のデザインではむしろなよなよしていて軍を率いる事は難しそうです;)
②文武両道(後漢にて尚書令・太尉・洛陽県令など持つ一族の出で政治の知見もあったと考えられる)
③カリスマ性があった(先輩の程普などの逸話や孫策孫権の評価や当時の民衆の逸話など)
④教養深く特に音楽が得意
⑤友情を大事にする(孫策の方が容姿端麗なんだそうな)
⑥三国志の花形・赤壁の立役者と考えられている(演義では孔明。私が愛読した子供向けの演義にも周瑜の実績が後世になって孔明に取られてしまっているといった注釈が付いていました)
⑦若くして死んでしまう…(悲運の英雄…)
等々、史書を読むと完璧過ぎる人だったようで私の憧れも膨らんだものでしたが、最近の三国無双では周瑜が目立っていない!絶世の美女と称される小喬も単なる馬鹿キャラ!あとから乙女ゲーっぽい流行りのイケメンがどんどん追加されてきて、美少女ももっと可愛く無難な性格のキャラが追加されていって、周瑜と二喬の影が非常に薄い…、ネットでは単なるロリコンと書かれる始末…。若い子にもあまり人気がないそうで。「違うんだ、周瑜はもっとカッコいい!」と私は叫びたい…。

という事で久々の三国無双はなんだかなあ…という感じですが、それはそれという事で、演義ベースのコーエー観を楽しんでいます。
・近年の追加要素も概ね面白いです。
(1)晋のストーリー
王元姫のデザインはアトリエっぽい美少女ですし、司馬懿・司馬師・司馬昭も格好良い。王元姫が本当に才女だったのかは司馬炎が政治にあまり興味がなさそうな所から少し疑問を感じます。司馬昭に諸葛誕の裏切りへの注意喚起や政治についても口出ししていたそうですから、当時の女性としては、発言力もあったのだと思います。

司馬昭は必要以上に残虐ではなかったようなので、実際は野心的で覇気のあるイメージですが、コーエーのキャラクターでもそこまで矛盾は感じません。
鍾会のホストっぽい残念イケメン感もコミカルで面白いです。彼は明智光秀っぽい位置の人でもあるので、文武優れても自信家でかつ人柄悪く人付き合いが下手という描写はアリだと思います。
特に賈充の腹黒さと友情を大事にする描写が面白かったです。彼は皇帝殺害など汚れ仕事も多いですが、司馬炎にまで忠実に仕えて、時代に誠実で合理的な人だったのかもと妄想してしまいました。

魏史と違い晋史は信憑性が疑われたりもする分どこまでがその時代を写実していてどこから脚色なのか素人に分かりづらいのでパロディに文句も言いづらいです;;
別にパロディが悪いというわけではないですしね。
しかし、一時的とはいえ中華統一を果たした晋がこれだけ憎まれ役となってしまうのは、匈奴に華北を取られた愚か者と漢民族には映ったからでしょうか?蜀漢が天下をとれば華北は取られなかったと、そういう希望から演義は愛されるのかもしれません。
魏ですら長安の北は取れていないので、三国時代から既に北は押され気味であり、曹魏はよく抑えていたという見方もあるかもしれません。
司馬炎が統一後の政治に興味を示さず女遊びに夢中になった事で、人々の目には司馬家はやりたい政治があったわけでもなく、ただ権力に溺れたかっただけだと映ったのでしょうか?
となると、司馬炎に政治の道を教えなかった司馬昭や王元姫や賈充の教育も悪かったと見るべきかもしれません。賈充は呉の征服には慎重派だったそうなので、蜀と魏の国力差はともかく、魏(晋)と呉はそれほどに均衡が取れていたのかもしれません。
晋の政治については具体的な資料が少ないそうですが、魏については曹操の政治面での改革が多く記録に残っているそうです。そういう意味では曹魏が天下統一を果たしたという見方も出来るのかな、と感じます。仲達も将軍職であり宰相としての実績も経歴もない事から司馬家には、内政に対する理想のビジョンが薄かったのかもしれません。反面、魏の実績をみますと曹操にはやりたい政治があったようにも感じます。
『何がしたかったのか』という内実はもはや想像の粋を出ない答えのないものになってしまいますねー...。
(2)呂布のストーリー
ころころ主人を変えて読者を呆れさせてしまうキャラも、美女に騙されやすいのも、圧倒的な武勇を誇る英雄譚も魅力的な呂布ですが、一騎当千がテーマのゲームと良くあっていて面白いです。

(3)増えた新キャラ
10年のうちに追加されたキャラクターで一番魅力的と思ったのは関銀屏です。二喬と違い、万人受けする清純派のデザインに、性格も良さげで、攻撃力が高くゲーム性能も良い…。これは、使う気になります∑(゚Д゚)
史実に居ない空想の人物だけに自由に描けている点や所詮蜀が正義で呉は悪役なのだなあと感じさせて複雑な気分になります。むしろこの類の容姿で二喬をデザインして欲しい…。

人気投票では一位になったそうですが、郭嘉のキャラは受け入れられませんでした。文武優れたが人徳はなかったそうですから自信家で嫌味っぽいのはいいんですが、別にイケメンでもないだろうし、あんなに不自然にねっとりした話し方でもないだろうなあ…と。あんな話し方だと屈強な前線の兵士達が軍略を聞くはずがない、とか思ってしまいます。
イケメンなら荀彧の方が…と思ったら荀彧のデザインは無難な印象でした。ポリゴンの顔形は良いですが、特にイケメンとして誇張している印象はありませんでしたねー…。
(4)定番キャラ
新キャラが今時の乙女ゲーギャルゲーっぽさを誇張しているのに対し、看板キャラの趙雲・陸遜・夏侯惇は安定させて、しっかり人気を維持しているのは流石だなあと感じました。個人的にはここに周瑜も入れて欲しいところですが小喬のクセの強さや周瑜の女顔過ぎる点など反感を招く描写が多いのでまあ仕方ないですかね…。

昔から子供心に趙雲が美化されているのは違和感がありましたが、趙雲の美化は近年は日本だけでなく各国でも共通しており、脚色されイケメンのイメージが定着してきているそうです。というのも、趙雲の超人過ぎない普通っぽい性格や特に目立ち過ぎない一般人っぽさが近年は中国・台湾など周辺各国で再評価されているそうで…近代化と共に民衆が憧れる英雄像もまた変化していく一つの象徴ともなっているそうです。
貧富の差が縮まり、平和が持続する国で中流階級としてほどほどに幸せになるなら、関羽や呂布ほどの武勇も必要なく、孔明ほどの天才的な閃きも必要ない、曹操ほどの先見の明も政治の腕も要らず、『そこそこ良い上司の下でそこそこ頑張れるちょっと凄い人』が現代の英雄像なのかもしれません。
そういう傾向からは、天から二物も三物も受け取って、顔も頭も性格も良く、親友はイケメン嫁は絶世の美女である周瑜もまた今時の英雄像からは外れてしまっているのかもしれません。
・余談
蜀漢正統説には否定的です、と個人的なファン派閥の立場を冒頭で言いました。
だったら、どこが統一すべきだったと思うのか?というのはなかなか難しい命題でもあります。
三国志は短い期間に興亡があり、どの勢力にもそれぞれ魅力があります。それこそが三国志が長く愛される理由なのかなと思いました。
後漢末期からおよそ100年間つづいた三国時代の後、晋の築いた平和は10年少しで崩れ去り、300年の泥沼を経て、隋の30年程を経て、唐の時代にてようやく長く疲弊した戦乱の世は落ち着きを取り戻せたと思われます。
しかしながら、唐もまた鮮卑の流れを汲む異民族との見方もあり、漢民族による統一ではない、と民からは考えられたのかもしれません。
といっても、漢民族による安定政権が維持された期間はその後2000年もの期間でごくわずかで民族を気にするよりも、平和かどうかを重視すれば良いかなとも感じます。ただ、文化が少し途切れてしまう事は残念かもしれません。
小市民の自分から見ると、平和を築き、文化を発展させる王様が、より多くの人にとっては「良い王様」になりうるのかなあと。
曹丕が漢室から禅譲を受けて皇帝になった時、曹丕は明君ではあったと思います。事実、彼の短い治世は安定していたそうです。九品官人法は隋の時代まで残ったそうですから、当時としては画期的だったのかもしれません。採用時点で身分が決まるという貴族主義な法のため、後の結果をみると、良法だったのかは疑問が残ります。ただ残念な事に皇帝となった後、わずか7年で死んでしまいます。歴史にIFがあるならば、もし曹丕がもっと長生きして、きちんと後継を育てていれば、司馬家が叛く事もなく、早い段階で内乱を平定して魏の国力を弱めず、北の異民族に対抗できたかもしれません。
孫権はわずか19歳で軍閥の長となります。周瑜や程普らに補佐され、若い頃は徳も高く頭も良く尊敬に足る君主だったそうですが、晩年は後継者を選びきれず、優秀な家臣団である陸遜らとも対立してしまい、孫権死後の呉はそのまま内乱が収めきれず国力が衰退してしまったそうです。もし孫権が後継者を正しく選び、諫言に惑わされず優秀な部下の信頼を落とさなければ、呉はもう少し長生きして、後10年凌げば晋は北にも挟撃され、統一王朝の覇者は呉となったかもしれません。
孫呉に関すれば、運によって滅亡していくのではなく、明君が老衰と共に自滅していくように感じられるのがなんとも残念だなあと個人的には感じられます。二宮事件について孫権が放置したのは個人的には疑問が残ります。すでに呆けはじめていたとかでしょうか。その他晩年の行動はどうもおかしい。その頃から孫権は判断力を失っていたのかもしれません...。痴呆による耄碌は仕方ないですが、ここに専制君主制の短所が出てしまっていると感じます。
もしも、皇太子の孫登が亡くならなかったら天下は呉のものだったかもしれません。そうすると周瑜の娘が皇太后になるので、周瑜の血も呉に残ったのですが...。陸遜も国を補佐してうまく纏まったように感じます。
劉備については、子供が暗愚だったのを知り、きちんとした後継者を育てられなかった時点で先がなかったとみなすべきかもしれません。劉備は、曹操の下にも孫権の下にも長く留まらず居場所を得られなかったため長い流浪生活が続いた事こそが蜀の敗因と言えるのかもしれません。いずれにせよ、様々な面から考えて、蜀が中華全土を統一するためにはひとつのIFでは事足りず、もっと若い頃に安定した地盤を得ていなければ苦しかったように感じられます。
司馬家に関すれば、もし禅譲を迫らず魏の臣下という立場を守っていたら、と思う事もありますが、すでに曹家の方から司馬家の権勢を排除したいと兵をあげられていたため、倒すか倒されるかの関係だったのかもしれません。司馬炎は女色に溺れ内政にあまり興味を示さなかったそうですから、ならば司馬昭が司馬攸を後継者にしていればまた変わっていたのかなあと妄想したりもします。
司馬炎が親族に兵と土地を与えたことは、魏の滅亡の原因を司馬家は皇族が弱かった事にある、と考えていたともいわれます。それにより、晋では逆に各地の皇族がそれぞれ力を持ちすぎたために各地で泥沼の内乱となってしまったのかもしれません。
これは、殷周王朝後に長く春秋戦国時代が続いた事で秦漢が郡県制を布いた方針とはまた逆流する流れにも感じられます。
いずれにしろ、統一後に中華を纏めきれなかった事が、長い内乱を招き、ひいては異民族に支配される素地をつくってしまったと言えるかもしれません。
もしも、曹丕が禅譲を迫らなかったら、その後も代わる代わる禅譲が繰り返される事はなかったのでは、と感じる事もありますが、新の前例がある以上、大きな大陸を長く治めるというのはなかなか難しい事なのだなあとも感じられます。そういう考えがある以上、上下関係を説く儒教が平和に一役買うとこれほどにまで求められたのかもしれません。
もしも、蜀が中華統一を果たせば、劉姓は続いたかもしれませんし、それで血の流れる量が減ったのかもしれません。少なくとも明の時代にはそういった考えが根底にあったからこそ蜀漢正統説が支持されたと思われます。(その後に異民族が劉姓を名乗る事が続いたため、実質的にはあまり意味がなかったと思われます。むしろ、漢室を残した方が良かったのかもしれません。)
こうしてあれこれ試行錯誤していくと、漢帝国の成功の一つは劉邦が建国の功臣を統一後に悉く処刑した事にも利があったのかもしれませんし、その後子供世代であった文景の治が安定したものであった事も良かったのかもしれません。そして何より長い戦国の解答でもあった商鞅や韓非子・李斯・蕭何らの作り上げた法治主義の完成度が高かったのかもしれません。
なぜ三国志後の世界が安定しなかったのか、正しい答えは解りませんが、優秀な次世代の後継者を育てる事にどの国も失敗してしまった事が一つの原因なのかなとも思いました。
歴史を振り返ると、平和の維持というのは非常に難しい事であり、むしろ争う事こそが自然の摂理に適った人類という生物の業であるかのようにも感じられます。
しかしながら、兵器があまりに強大になりすぎた現代ではそれは自然の破壊を意味するとも思われます。
どうやったら平和が維持出来るのかに正解はなく、あまりに難しくなりすぎたために、現代の我々は、科学が発展しすぎておらず、個人の武と知が覇権を左右する古代の世界の英雄に憧れを抱くのかもしれません。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
全くゲーム性が変化してなくて笑ってしまいました。
ダクソなどのアクション性の高めなゲームを好む自分からすると単なる作業ゲー…。歴史好きか、乙女ゲーもしくはギャルゲー好きでないと楽しめないようになってしまい、質の低い古びたゲームで終わってしまいそうな事が残念です。
・あわせて、コーエーの描写に不満があります。
ここで、自分の三国志への拘りを書いておきます。人によって好きな国や人物も異なると思うので…。
私は三国志では周瑜が好きです。劉備や孔明、関羽は美化されてて子供心に苦手でした。8才くらいで既に嘘臭いと感じてました(笑)。曹操や司馬懿の方が中原を抑えたりと必要な時に的確な手をうてて後継者も育てている様に感じ、個人的には蜀よりはやや呉や魏よりです。元々儒教的な歴史観があまり好みでなかったせいか、始皇帝や項羽や商鞅も韓非子も孫子二代も好きな方です。(法治主義が性悪説から発展したものなら広義の儒教かもしれないので、徳治第一主義が苦手とか、表現すべきなのかもです。別に悪逆非道な専制を好むわけでないです。)暗に武帝への不満を滲ませる司馬遷も好きです。天道是非、よって蜀漢正統説は否定的です。
ちょっと偉そうに私が「中原」と称した地理について語ると、定義的には黄河下流域あたりを言うそうですが、ここでは咸陽・長安・洛陽あたりも含むとします。
なんで黄河がこんなに重要拠点と思うかというと、文化的背景や漢帝国の要所でもありましたが経済流通の大部分をしめているからです。
つまり、曹操や司馬懿の方がずっとお金持ちだったと考えられそうです。(三国時代は長引く官吏の腐敗や戦乱によって中原自体も衰えてはいたそうです。)長江流域は中華の中でも肥沃な穀倉地だそうですから呉の得た地理はまだ意味がありますが、蜀というのは見た目の面積では三国並び立っていそうに見えますが、実際の規模は面積ほどの価値はなく、二強状態に小さな蜀がくっついていってるだけように私には見えました。小学生がそう思ったのだから、きっと当時の人もそう思っていたのだと思います。
こういうと少し酷いかもしれませんが、(春秋)戦国時代の韓程度のバランサーでしかなかったように感じます。つまり孔明が目指したのは、天下統一して平和な世をつくることではなく、必要以上に戦乱の世を長引かせて、民を疲弊させる事だったのでは、と私には感じられたのです。
↓に春秋時代の蜀の位置を示して見ます。
秦の始皇帝の小説などを読むと謀反した貴族を蜀に流す刑罰を行っていたりしますから、蜀というのは中原から見たら、田舎も田舎、中華にすら入らない(肌色領域)、辺境の地であったと予想されます。漢の時代を挟めばもう少し蜀の地位は上がってはいそうですが、それでも、経済拠点からは少し外れていそうに感じます。
これは、大人になってから知った知識ですが、三国志演義は千年後の明の時代のものとされています。その前の元に支配された時代に民衆が漢民族による中華統一を願った事と、漢や明が支配の道具として儒教を利用した事が、幅広く演義が流通した背景にあるそうです。
それを知ってしまって、蜀が天下を取るというのは、夢物語にしか感じなくなってしまい、劉備も孔明も欲深い俗物に感じてしまいました。無双内でも曹操が「口だけでは駄目だ」っぽい揶揄をしていますが、私にもそう見えてしまったのです。
まあ、別に中華統一しなくてもヨーロッパみたいに分裂しても戦争が減るならそれで良い気もしますが、秦や漢の統一によって文化が統一された事や儒教の広がりによって中華の民は統一を求める意識が強かったのかなと感じます。
拙い中華論はともかく、周瑜という人は「三国志」の描写だけでも万能な人で、幼い私にはまさに憧れの英雄という感想を持ちました。女顔というのは演義や後世の脚色でしょうが、歴史書においても文句のつけようのない多才な人です。当時の歴史書が事実だけを書いているかは謎ですが、一応そこそこ信頼に足るとされています。
①容姿が良い(肌が白いとか美周郎というのは演義や後世の脚色。実際は男性から見て格好良い恰幅だったのかも?無双のデザインではむしろなよなよしていて軍を率いる事は難しそうです;)
②文武両道(後漢にて尚書令・太尉・洛陽県令など持つ一族の出で政治の知見もあったと考えられる)
③カリスマ性があった(先輩の程普などの逸話や孫策孫権の評価や当時の民衆の逸話など)
④教養深く特に音楽が得意
⑤友情を大事にする(孫策の方が容姿端麗なんだそうな)
⑥三国志の花形・赤壁の立役者と考えられている(演義では孔明。私が愛読した子供向けの演義にも周瑜の実績が後世になって孔明に取られてしまっているといった注釈が付いていました)
⑦若くして死んでしまう…(悲運の英雄…)
等々、史書を読むと完璧過ぎる人だったようで私の憧れも膨らんだものでしたが、最近の三国無双では周瑜が目立っていない!絶世の美女と称される小喬も単なる馬鹿キャラ!あとから乙女ゲーっぽい流行りのイケメンがどんどん追加されてきて、美少女ももっと可愛く無難な性格のキャラが追加されていって、周瑜と二喬の影が非常に薄い…、ネットでは単なるロリコンと書かれる始末…。若い子にもあまり人気がないそうで。「違うんだ、周瑜はもっとカッコいい!」と私は叫びたい…。
という事で久々の三国無双はなんだかなあ…という感じですが、それはそれという事で、演義ベースのコーエー観を楽しんでいます。
・近年の追加要素も概ね面白いです。
(1)晋のストーリー
王元姫のデザインはアトリエっぽい美少女ですし、司馬懿・司馬師・司馬昭も格好良い。王元姫が本当に才女だったのかは司馬炎が政治にあまり興味がなさそうな所から少し疑問を感じます。司馬昭に諸葛誕の裏切りへの注意喚起や政治についても口出ししていたそうですから、当時の女性としては、発言力もあったのだと思います。
司馬昭は必要以上に残虐ではなかったようなので、実際は野心的で覇気のあるイメージですが、コーエーのキャラクターでもそこまで矛盾は感じません。
鍾会のホストっぽい残念イケメン感もコミカルで面白いです。彼は明智光秀っぽい位置の人でもあるので、文武優れても自信家でかつ人柄悪く人付き合いが下手という描写はアリだと思います。
特に賈充の腹黒さと友情を大事にする描写が面白かったです。彼は皇帝殺害など汚れ仕事も多いですが、司馬炎にまで忠実に仕えて、時代に誠実で合理的な人だったのかもと妄想してしまいました。
魏史と違い晋史は信憑性が疑われたりもする分どこまでがその時代を写実していてどこから脚色なのか素人に分かりづらいのでパロディに文句も言いづらいです;;
別にパロディが悪いというわけではないですしね。
しかし、一時的とはいえ中華統一を果たした晋がこれだけ憎まれ役となってしまうのは、匈奴に華北を取られた愚か者と漢民族には映ったからでしょうか?蜀漢が天下をとれば華北は取られなかったと、そういう希望から演義は愛されるのかもしれません。
魏ですら長安の北は取れていないので、三国時代から既に北は押され気味であり、曹魏はよく抑えていたという見方もあるかもしれません。
司馬炎が統一後の政治に興味を示さず女遊びに夢中になった事で、人々の目には司馬家はやりたい政治があったわけでもなく、ただ権力に溺れたかっただけだと映ったのでしょうか?
となると、司馬炎に政治の道を教えなかった司馬昭や王元姫や賈充の教育も悪かったと見るべきかもしれません。賈充は呉の征服には慎重派だったそうなので、蜀と魏の国力差はともかく、魏(晋)と呉はそれほどに均衡が取れていたのかもしれません。
晋の政治については具体的な資料が少ないそうですが、魏については曹操の政治面での改革が多く記録に残っているそうです。そういう意味では曹魏が天下統一を果たしたという見方も出来るのかな、と感じます。仲達も将軍職であり宰相としての実績も経歴もない事から司馬家には、内政に対する理想のビジョンが薄かったのかもしれません。反面、魏の実績をみますと曹操にはやりたい政治があったようにも感じます。
『何がしたかったのか』という内実はもはや想像の粋を出ない答えのないものになってしまいますねー...。
(2)呂布のストーリー
ころころ主人を変えて読者を呆れさせてしまうキャラも、美女に騙されやすいのも、圧倒的な武勇を誇る英雄譚も魅力的な呂布ですが、一騎当千がテーマのゲームと良くあっていて面白いです。
(3)増えた新キャラ
10年のうちに追加されたキャラクターで一番魅力的と思ったのは関銀屏です。二喬と違い、万人受けする清純派のデザインに、性格も良さげで、攻撃力が高くゲーム性能も良い…。これは、使う気になります∑(゚Д゚)
史実に居ない空想の人物だけに自由に描けている点や所詮蜀が正義で呉は悪役なのだなあと感じさせて複雑な気分になります。むしろこの類の容姿で二喬をデザインして欲しい…。
人気投票では一位になったそうですが、郭嘉のキャラは受け入れられませんでした。文武優れたが人徳はなかったそうですから自信家で嫌味っぽいのはいいんですが、別にイケメンでもないだろうし、あんなに不自然にねっとりした話し方でもないだろうなあ…と。あんな話し方だと屈強な前線の兵士達が軍略を聞くはずがない、とか思ってしまいます。
イケメンなら荀彧の方が…と思ったら荀彧のデザインは無難な印象でした。ポリゴンの顔形は良いですが、特にイケメンとして誇張している印象はありませんでしたねー…。
(4)定番キャラ
新キャラが今時の乙女ゲーギャルゲーっぽさを誇張しているのに対し、看板キャラの趙雲・陸遜・夏侯惇は安定させて、しっかり人気を維持しているのは流石だなあと感じました。個人的にはここに周瑜も入れて欲しいところですが小喬のクセの強さや周瑜の女顔過ぎる点など反感を招く描写が多いのでまあ仕方ないですかね…。
昔から子供心に趙雲が美化されているのは違和感がありましたが、趙雲の美化は近年は日本だけでなく各国でも共通しており、脚色されイケメンのイメージが定着してきているそうです。というのも、趙雲の超人過ぎない普通っぽい性格や特に目立ち過ぎない一般人っぽさが近年は中国・台湾など周辺各国で再評価されているそうで…近代化と共に民衆が憧れる英雄像もまた変化していく一つの象徴ともなっているそうです。
貧富の差が縮まり、平和が持続する国で中流階級としてほどほどに幸せになるなら、関羽や呂布ほどの武勇も必要なく、孔明ほどの天才的な閃きも必要ない、曹操ほどの先見の明も政治の腕も要らず、『そこそこ良い上司の下でそこそこ頑張れるちょっと凄い人』が現代の英雄像なのかもしれません。
そういう傾向からは、天から二物も三物も受け取って、顔も頭も性格も良く、親友はイケメン嫁は絶世の美女である周瑜もまた今時の英雄像からは外れてしまっているのかもしれません。
・余談
蜀漢正統説には否定的です、と個人的なファン派閥の立場を冒頭で言いました。
だったら、どこが統一すべきだったと思うのか?というのはなかなか難しい命題でもあります。
三国志は短い期間に興亡があり、どの勢力にもそれぞれ魅力があります。それこそが三国志が長く愛される理由なのかなと思いました。
後漢末期からおよそ100年間つづいた三国時代の後、晋の築いた平和は10年少しで崩れ去り、300年の泥沼を経て、隋の30年程を経て、唐の時代にてようやく長く疲弊した戦乱の世は落ち着きを取り戻せたと思われます。
しかしながら、唐もまた鮮卑の流れを汲む異民族との見方もあり、漢民族による統一ではない、と民からは考えられたのかもしれません。
といっても、漢民族による安定政権が維持された期間はその後2000年もの期間でごくわずかで民族を気にするよりも、平和かどうかを重視すれば良いかなとも感じます。ただ、文化が少し途切れてしまう事は残念かもしれません。
小市民の自分から見ると、平和を築き、文化を発展させる王様が、より多くの人にとっては「良い王様」になりうるのかなあと。
曹丕が漢室から禅譲を受けて皇帝になった時、曹丕は明君ではあったと思います。事実、彼の短い治世は安定していたそうです。九品官人法は隋の時代まで残ったそうですから、当時としては画期的だったのかもしれません。採用時点で身分が決まるという貴族主義な法のため、後の結果をみると、良法だったのかは疑問が残ります。ただ残念な事に皇帝となった後、わずか7年で死んでしまいます。歴史にIFがあるならば、もし曹丕がもっと長生きして、きちんと後継を育てていれば、司馬家が叛く事もなく、早い段階で内乱を平定して魏の国力を弱めず、北の異民族に対抗できたかもしれません。
孫権はわずか19歳で軍閥の長となります。周瑜や程普らに補佐され、若い頃は徳も高く頭も良く尊敬に足る君主だったそうですが、晩年は後継者を選びきれず、優秀な家臣団である陸遜らとも対立してしまい、孫権死後の呉はそのまま内乱が収めきれず国力が衰退してしまったそうです。もし孫権が後継者を正しく選び、諫言に惑わされず優秀な部下の信頼を落とさなければ、呉はもう少し長生きして、後10年凌げば晋は北にも挟撃され、統一王朝の覇者は呉となったかもしれません。
孫呉に関すれば、運によって滅亡していくのではなく、明君が老衰と共に自滅していくように感じられるのがなんとも残念だなあと個人的には感じられます。二宮事件について孫権が放置したのは個人的には疑問が残ります。すでに呆けはじめていたとかでしょうか。その他晩年の行動はどうもおかしい。その頃から孫権は判断力を失っていたのかもしれません...。痴呆による耄碌は仕方ないですが、ここに専制君主制の短所が出てしまっていると感じます。
もしも、皇太子の孫登が亡くならなかったら天下は呉のものだったかもしれません。そうすると周瑜の娘が皇太后になるので、周瑜の血も呉に残ったのですが...。陸遜も国を補佐してうまく纏まったように感じます。
劉備については、子供が暗愚だったのを知り、きちんとした後継者を育てられなかった時点で先がなかったとみなすべきかもしれません。劉備は、曹操の下にも孫権の下にも長く留まらず居場所を得られなかったため長い流浪生活が続いた事こそが蜀の敗因と言えるのかもしれません。いずれにせよ、様々な面から考えて、蜀が中華全土を統一するためにはひとつのIFでは事足りず、もっと若い頃に安定した地盤を得ていなければ苦しかったように感じられます。
司馬家に関すれば、もし禅譲を迫らず魏の臣下という立場を守っていたら、と思う事もありますが、すでに曹家の方から司馬家の権勢を排除したいと兵をあげられていたため、倒すか倒されるかの関係だったのかもしれません。司馬炎は女色に溺れ内政にあまり興味を示さなかったそうですから、ならば司馬昭が司馬攸を後継者にしていればまた変わっていたのかなあと妄想したりもします。
司馬炎が親族に兵と土地を与えたことは、魏の滅亡の原因を司馬家は皇族が弱かった事にある、と考えていたともいわれます。それにより、晋では逆に各地の皇族がそれぞれ力を持ちすぎたために各地で泥沼の内乱となってしまったのかもしれません。
これは、殷周王朝後に長く春秋戦国時代が続いた事で秦漢が郡県制を布いた方針とはまた逆流する流れにも感じられます。
いずれにしろ、統一後に中華を纏めきれなかった事が、長い内乱を招き、ひいては異民族に支配される素地をつくってしまったと言えるかもしれません。
もしも、曹丕が禅譲を迫らなかったら、その後も代わる代わる禅譲が繰り返される事はなかったのでは、と感じる事もありますが、新の前例がある以上、大きな大陸を長く治めるというのはなかなか難しい事なのだなあとも感じられます。そういう考えがある以上、上下関係を説く儒教が平和に一役買うとこれほどにまで求められたのかもしれません。
もしも、蜀が中華統一を果たせば、劉姓は続いたかもしれませんし、それで血の流れる量が減ったのかもしれません。少なくとも明の時代にはそういった考えが根底にあったからこそ蜀漢正統説が支持されたと思われます。(その後に異民族が劉姓を名乗る事が続いたため、実質的にはあまり意味がなかったと思われます。むしろ、漢室を残した方が良かったのかもしれません。)
こうしてあれこれ試行錯誤していくと、漢帝国の成功の一つは劉邦が建国の功臣を統一後に悉く処刑した事にも利があったのかもしれませんし、その後子供世代であった文景の治が安定したものであった事も良かったのかもしれません。そして何より長い戦国の解答でもあった商鞅や韓非子・李斯・蕭何らの作り上げた法治主義の完成度が高かったのかもしれません。
なぜ三国志後の世界が安定しなかったのか、正しい答えは解りませんが、優秀な次世代の後継者を育てる事にどの国も失敗してしまった事が一つの原因なのかなとも思いました。
歴史を振り返ると、平和の維持というのは非常に難しい事であり、むしろ争う事こそが自然の摂理に適った人類という生物の業であるかのようにも感じられます。
しかしながら、兵器があまりに強大になりすぎた現代ではそれは自然の破壊を意味するとも思われます。
どうやったら平和が維持出来るのかに正解はなく、あまりに難しくなりすぎたために、現代の我々は、科学が発展しすぎておらず、個人の武と知が覇権を左右する古代の世界の英雄に憧れを抱くのかもしれません。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
・PVを見てコントローラー等操作性が好みでなくなった「モンハン」っぽいゲームが家庭用で出来るかなと期待して購入しました。プレイした感想は、モンハンとはかなり異なりました。クエストメインの狩りゲーというよりは、オープンワールドのARPGといった面が強いです。私が過去に遊んだ作品の中では「ウィッチャー」や「ドラゴンズドグマ」の方がプレイ感覚は似ているかなと思いました。アクション性の高いRPGを探している方ならお好みに合うかもしれません。私は世界観が他のオープンものより気になったので探索が楽しめて良かったと思います。
・ストーリー、世界観、アクション操作性、マップ探索の魅力、グラフィック・・・ARPGに求めるものはバランスよく入っており、マルチがない事・武器防具種類が少ない事に納得出来れば良ゲーですと万人にお勧めしやすい作品です。
★長所
①意外と重厚なストーリー
・序盤はムービーシーンがありますし、世界観が作りこまれていました。なんで文明が滅びたのか機械が闊歩しているのかなと思いながらの遺跡探索はとてもワクワクします。
・日本人から見ても受け入れやすい世界観だと思います。人間集団同士で銃撃戦したりするのは欧米受けを狙ってでしょうか・・・、独創性も高いですが要所要所で流行りを取り入れており万人が楽しめるように工夫されている印象を受けました。
・序盤良いだけに後半ややまとめ方が阿呆臭いのが残念でした。
②美麗なマップグラフィック
・PV見ていると現代のゲームとしては普通に見えますが、世界の端から端までPVクオリティです。美しい景色や謎めいた廃墟が点在しており広いマップも中身がないという事もなくただ目的もなく出歩くだけでも楽しめます。シリーズものではない一作目(?)としてはかなり頑張っている方で期待以上でした。
③そこそこの難易度のアクション
・油断すると敵が主人公をあっさり倒すくらいの難易度はあります。難しすぎる程でもないですが、作業感で戦闘する程でもないです。近接も回避能力が優秀で火力高いので爽快ですし、弓でちくちく格上を倒す事も可能です。口コミで聞いていた程TPSメインという事もなく、レベル相当の敵なら序盤から近接でつっこんで群れを翻弄する事も可能です。スタミナ制限がないので近接は強い。囲まれたところで同時に攻撃してこないAIなのか集団戦になったら即時詰むという程でもないです。
・ただ近接は一種類のみ弓の種類は多数なので、弓が楽しめないと向いていないかもしれません。エイムは無くても隠れて初撃だけゆっくりと弱点に合わせて弱点属性をぶつけ、後は逃げて近接で倒す、罠に誘導する、ステルスで倒すという戦術もアリなので、エイムや反射神経は不得意でも敵は倒せると思います。回避アクション慣れしていないと被弾に苦しむかもしれません。回復薬は補充しやすくそのバランスもよく練られています。良いバランスなので武器種類が増えるともっと楽しめたと思いました。オープンワールドゲーの中ではアクション性能は高い水準だと思います。
④豊富なボリューム
・新規IPとは思えないほどマップも広いですし、サブクエも配置されており、探索しがいがあります。
★短所
①オンラインマルチプレイは出来ない
・モンハンみたいに友人と狩りに行けたら、また楽しみが広がったと思います。事実友人に紹介しても協力が出来ないと聞いて購入を控える人が多いです。またネット対戦なども出来たら面白かったかもしれません。
②衣装・外見カスタマイズが少ない
・最近のRPGの中では外見カスタマイズ要素は少ないと思いました。防具はもう少し豊富でも良かったかもしれません。華があるか、とか萌えるかと聞かれると、そういうゲームではないかなーと答えてしまいます。洋ゲーの中では人物は日本人から見ても抵抗を感じにくいビジュアルだと思います。
③サブクエスト
・そこまで開発に期待してどうする、という感じですが、サブクエは一部ただのおつかいで典型的な物も多く作業感はありました。オープンワールドものなのでこんなものかもしれません。
④素材集め
・剥ぎ取りした素材で強い武器を作れるという要素はそこまで強くもないので、もう少し武器種があって、永続的に収集を楽しめたら神ゲーになれたんじゃないかと感じています。あんまり武器強化が出来過ぎるとアクションというより強化作業ゲーになるのでバランスが難しいのかもしれません。個人的には槍以外にもレイピアや日本刀や斧のような様々なモーションの近接武器が欲しかったです。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
・ストーリー、世界観、アクション操作性、マップ探索の魅力、グラフィック・・・ARPGに求めるものはバランスよく入っており、マルチがない事・武器防具種類が少ない事に納得出来れば良ゲーですと万人にお勧めしやすい作品です。
★長所
①意外と重厚なストーリー
・序盤はムービーシーンがありますし、世界観が作りこまれていました。なんで文明が滅びたのか機械が闊歩しているのかなと思いながらの遺跡探索はとてもワクワクします。
・日本人から見ても受け入れやすい世界観だと思います。人間集団同士で銃撃戦したりするのは欧米受けを狙ってでしょうか・・・、独創性も高いですが要所要所で流行りを取り入れており万人が楽しめるように工夫されている印象を受けました。
・序盤良いだけに後半ややまとめ方が阿呆臭いのが残念でした。
②美麗なマップグラフィック
・PV見ていると現代のゲームとしては普通に見えますが、世界の端から端までPVクオリティです。美しい景色や謎めいた廃墟が点在しており広いマップも中身がないという事もなくただ目的もなく出歩くだけでも楽しめます。シリーズものではない一作目(?)としてはかなり頑張っている方で期待以上でした。
③そこそこの難易度のアクション
・油断すると敵が主人公をあっさり倒すくらいの難易度はあります。難しすぎる程でもないですが、作業感で戦闘する程でもないです。近接も回避能力が優秀で火力高いので爽快ですし、弓でちくちく格上を倒す事も可能です。口コミで聞いていた程TPSメインという事もなく、レベル相当の敵なら序盤から近接でつっこんで群れを翻弄する事も可能です。スタミナ制限がないので近接は強い。囲まれたところで同時に攻撃してこないAIなのか集団戦になったら即時詰むという程でもないです。
・ただ近接は一種類のみ弓の種類は多数なので、弓が楽しめないと向いていないかもしれません。エイムは無くても隠れて初撃だけゆっくりと弱点に合わせて弱点属性をぶつけ、後は逃げて近接で倒す、罠に誘導する、ステルスで倒すという戦術もアリなので、エイムや反射神経は不得意でも敵は倒せると思います。回避アクション慣れしていないと被弾に苦しむかもしれません。回復薬は補充しやすくそのバランスもよく練られています。良いバランスなので武器種類が増えるともっと楽しめたと思いました。オープンワールドゲーの中ではアクション性能は高い水準だと思います。
④豊富なボリューム
・新規IPとは思えないほどマップも広いですし、サブクエも配置されており、探索しがいがあります。
★短所
①オンラインマルチプレイは出来ない
・モンハンみたいに友人と狩りに行けたら、また楽しみが広がったと思います。事実友人に紹介しても協力が出来ないと聞いて購入を控える人が多いです。またネット対戦なども出来たら面白かったかもしれません。
②衣装・外見カスタマイズが少ない
・最近のRPGの中では外見カスタマイズ要素は少ないと思いました。防具はもう少し豊富でも良かったかもしれません。華があるか、とか萌えるかと聞かれると、そういうゲームではないかなーと答えてしまいます。洋ゲーの中では人物は日本人から見ても抵抗を感じにくいビジュアルだと思います。
③サブクエスト
・そこまで開発に期待してどうする、という感じですが、サブクエは一部ただのおつかいで典型的な物も多く作業感はありました。オープンワールドものなのでこんなものかもしれません。
④素材集め
・剥ぎ取りした素材で強い武器を作れるという要素はそこまで強くもないので、もう少し武器種があって、永続的に収集を楽しめたら神ゲーになれたんじゃないかと感じています。あんまり武器強化が出来過ぎるとアクションというより強化作業ゲーになるのでバランスが難しいのかもしれません。個人的には槍以外にもレイピアや日本刀や斧のような様々なモーションの近接武器が欲しかったです。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
FF15を遊んだので評価レビューしてみます。
一部を除いてやりこみもそこそこ終わったと思います。
日本のAmazonやスレではアンチが優勢ですが、海外ではそこそこで安定してます。いろんなレビューも読みましたが82点付けたIGNさんくらいの評価が妥当だと思いました。
★総合80/100p
①ストーリー1/5p
ストーリーはつまらないです。ムービーは迫力あり悪くなかったので一応1点。オープンワールドなのにGTAとかウィッチャーみたくフィールドで作り込まれたシナリオイベントが無く、自らオープンワールドのシステムを否定する姿勢を見せた事もマイナスの印象でした。
②オープンワールド4/5p
結局フィールドの質はGTAやウィッチャーやエルダースクロールに負けてます。道路脇の柵がジャンプで飛び越えられない等見えない壁が各所にあるのと、自由度皆無の車移動が詰まらないのと、ワープ時のロードが長いのはストレスでした。
③サウンド4/5p
歴代FFの曲が自由に選べたので、満足度が高かったです。
④グラフィック5/5p
ここしか手放しで褒めるところがないですが、景色も御飯も文句なしに最高峰だと思いました。
⑤キャラクター1/5p
ストーリーとも関係しますが、腐向けを露骨に狙った気持ち悪いホスト達御一行という印象は抜けませんでした。
⑥サブクエ2/5p
何もアイディアを感じないお使いクエストしかないです。
⑦アクション性能5/5p
シフト等回避する選択肢が豊富でレベルに関わらずノーダメが狙いやすく、想像以上に奥深いシステムに仕上がっていたと思います。一方でボタン長押しでオート攻撃オート回避してくれるので脳死でも老弱男女問わず誰でも遊べる戦闘になっていると思います。パリィも受付フレーム長く反射神経を必要としません。
⑧ゲームデザイン
ここでは13章とプティウォス遺跡について書いていきたいです。
個人的には鍛冶屋のクエ、特にナグルファル戦は神ゲーと絶賛できるくらい面白かったし、クラストゥルム水道の探索はワクワクして興奮しました。
13章も楽しかったです。隠れろってチュートリアルが出たのに敵の足が異様に早かったり、ダッシュ速度が鈍かったり、バグが多かったり、FFじゃなくてバイオだったり、「え?」と思う事はあったけど、指輪魔法は強いし、パズルダンジョンの探索も楽しかった。批難しているアンチの方々はよっぽどゲームセンスがないか、普段コンシューマのアクションゲームをプレイしない層なんだろうなって思っています。日本ではそういった層が多数派で別に不満もない人々も周りに合わせて文句を言ってしまう空気が出来上がったのは少し残念です。バイオではなくFFのメインシナリオなのでそこを指摘されている以上別に擁護する気もないですが、少なくとも自分は13章は面白かった。ホーリーもタイミングよく使えばM
P消費は少ないし、長押しの必要はない。オルタナは無条件殲滅魔法なんだからデメリットがあって当然のバランス。倒せない敵とか、毒ガスとか、足だけは早い雑魚とか、ストレス発散用の弱い敵とか、倒しても復活する敵とかギミックの種類もそこそこ豊富だったと思う。
「mp消費激しすぎ」って事は無いし「長押しでクリア出来て単調」って事もなく、13章以外のFF全編はアクション苦手でも出来るように作ってるし長押しで攻略しなきゃいいだけで、これはエアプか動画勢の意見だと思います。
「難しすぎ」っておっしゃる方は頭悪くてゲームセンスないのは可哀そうですが、救済パッチで難易度下がるらしいのでもう少し待ってみては?
「FFじゃない」ってまぁ意見は分かるけど、逆にFFって何だ?コマンド式のターン制だったら文句ないの?まぁ、全力で肯定する程いい出来でもないけど、変化が豊富で自分は楽しめました。「ストレスしかない」って人は変化したシステムに瞬時に対応出来ない頭が固い層じゃないかなーと思います。あとは空気読んで合わせてる人が大半。アンチが必死すぎて怖いしね…。
プティウォス遺跡は、クリアした時は達成感ありましたが、オープンワールドで長距離移動用に調整されたシステムで細かい動作を要求するのは理不尽だと思いました。歩きの感度が悪いシステムしか開発出来ずにユーザーを上から目線で試しているスクエニ独特の開発陣の気持ち悪さを感じました。不必要なスタッフの寄せ書きは印刷してくるだけあるな…と。一番腹が立ったのは回転する坂道です。吐き気がしてきて少し目を閉じたら寝落ちしてしまった。本家のマリオだとプレイ中に寝るなんていう経験はありません。身体に負担のかかり非常に不快でした。
FF15は劣化バイオだったり、劣化マリオだったり、劣化GTAだったり、劣化スカイリムだったり…。グラフィックと戦闘システムは良いのですが、他は整合性がなく、結果的に技術はあるのにトップ層がセンスが無かったという印象でした。
何処かのレビューに書かれていた「高級食材を使用して調理に失敗した料理を食べさせられている気分」というのは的確な表現だと思います。
別に、魔法の力を持った王子様が世界を救う力を集める物語でも良いですが、若い青年を主人公にしておいてヒロインと文通しかイベントが無かったのは味気ないし、仲間も主人公に自分の身を犠牲にして世界を救う事を期待しすぎていて友情は感じられなかった。主人公も自己犠牲に納得してないのに結局周りに流されて与えられた役割を演じるだけ。パパとの親子愛の描写も薄かったし、サブイベを強化しやすいオープンワールドなのに何故か周りのキャラクターとシナリオが薄かったという印象でした。
反面、戦闘システムは面白かったです。
回避手段が豊富なので、戦闘中に考える事がけっこう多くて楽しい。
(1)オート回避(2)ジャストガードやパリィ(3)ローリング回避(4)マップシフト(5)シフトブレイク(6)シフト回避(7)ジャンプ回避(8)指輪魔法(9)仲間のコマンドで敵の動きを止めてキャンセル(10)ファントムソード(11)召喚獣
他にも防御手段があったかもしれませんが、とにかく敵の当たり判定から逃れる選択肢が豊富な事は自由度も高く面白かったです。ライブラ多用して弱点ついてとにかく先手でクラッシュを狙うって戦い方も出来ました。
ストーリーはどうでもいいから、景色の綺麗なオープンワールドでアクションRPGをやりたいって人には、オススメ出来る作品だと思います。
戦闘に関してだけはスカイリムやウィッチャーよりもFF15 の方が自分は楽しめました。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
一部を除いてやりこみもそこそこ終わったと思います。
日本のAmazonやスレではアンチが優勢ですが、海外ではそこそこで安定してます。いろんなレビューも読みましたが82点付けたIGNさんくらいの評価が妥当だと思いました。
★総合80/100p
①ストーリー1/5p
ストーリーはつまらないです。ムービーは迫力あり悪くなかったので一応1点。オープンワールドなのにGTAとかウィッチャーみたくフィールドで作り込まれたシナリオイベントが無く、自らオープンワールドのシステムを否定する姿勢を見せた事もマイナスの印象でした。
②オープンワールド4/5p
結局フィールドの質はGTAやウィッチャーやエルダースクロールに負けてます。道路脇の柵がジャンプで飛び越えられない等見えない壁が各所にあるのと、自由度皆無の車移動が詰まらないのと、ワープ時のロードが長いのはストレスでした。
③サウンド4/5p
歴代FFの曲が自由に選べたので、満足度が高かったです。
④グラフィック5/5p
ここしか手放しで褒めるところがないですが、景色も御飯も文句なしに最高峰だと思いました。
⑤キャラクター1/5p
ストーリーとも関係しますが、腐向けを露骨に狙った気持ち悪いホスト達御一行という印象は抜けませんでした。
⑥サブクエ2/5p
何もアイディアを感じないお使いクエストしかないです。
⑦アクション性能5/5p
シフト等回避する選択肢が豊富でレベルに関わらずノーダメが狙いやすく、想像以上に奥深いシステムに仕上がっていたと思います。一方でボタン長押しでオート攻撃オート回避してくれるので脳死でも老弱男女問わず誰でも遊べる戦闘になっていると思います。パリィも受付フレーム長く反射神経を必要としません。
⑧ゲームデザイン
ここでは13章とプティウォス遺跡について書いていきたいです。
個人的には鍛冶屋のクエ、特にナグルファル戦は神ゲーと絶賛できるくらい面白かったし、クラストゥルム水道の探索はワクワクして興奮しました。
13章も楽しかったです。隠れろってチュートリアルが出たのに敵の足が異様に早かったり、ダッシュ速度が鈍かったり、バグが多かったり、FFじゃなくてバイオだったり、「え?」と思う事はあったけど、指輪魔法は強いし、パズルダンジョンの探索も楽しかった。批難しているアンチの方々はよっぽどゲームセンスがないか、普段コンシューマのアクションゲームをプレイしない層なんだろうなって思っています。日本ではそういった層が多数派で別に不満もない人々も周りに合わせて文句を言ってしまう空気が出来上がったのは少し残念です。バイオではなくFFのメインシナリオなのでそこを指摘されている以上別に擁護する気もないですが、少なくとも自分は13章は面白かった。ホーリーもタイミングよく使えばM
P消費は少ないし、長押しの必要はない。オルタナは無条件殲滅魔法なんだからデメリットがあって当然のバランス。倒せない敵とか、毒ガスとか、足だけは早い雑魚とか、ストレス発散用の弱い敵とか、倒しても復活する敵とかギミックの種類もそこそこ豊富だったと思う。
「mp消費激しすぎ」って事は無いし「長押しでクリア出来て単調」って事もなく、13章以外のFF全編はアクション苦手でも出来るように作ってるし長押しで攻略しなきゃいいだけで、これはエアプか動画勢の意見だと思います。
「難しすぎ」っておっしゃる方は頭悪くてゲームセンスないのは可哀そうですが、救済パッチで難易度下がるらしいのでもう少し待ってみては?
「FFじゃない」ってまぁ意見は分かるけど、逆にFFって何だ?コマンド式のターン制だったら文句ないの?まぁ、全力で肯定する程いい出来でもないけど、変化が豊富で自分は楽しめました。「ストレスしかない」って人は変化したシステムに瞬時に対応出来ない頭が固い層じゃないかなーと思います。あとは空気読んで合わせてる人が大半。アンチが必死すぎて怖いしね…。
プティウォス遺跡は、クリアした時は達成感ありましたが、オープンワールドで長距離移動用に調整されたシステムで細かい動作を要求するのは理不尽だと思いました。歩きの感度が悪いシステムしか開発出来ずにユーザーを上から目線で試しているスクエニ独特の開発陣の気持ち悪さを感じました。不必要なスタッフの寄せ書きは印刷してくるだけあるな…と。一番腹が立ったのは回転する坂道です。吐き気がしてきて少し目を閉じたら寝落ちしてしまった。本家のマリオだとプレイ中に寝るなんていう経験はありません。身体に負担のかかり非常に不快でした。
FF15は劣化バイオだったり、劣化マリオだったり、劣化GTAだったり、劣化スカイリムだったり…。グラフィックと戦闘システムは良いのですが、他は整合性がなく、結果的に技術はあるのにトップ層がセンスが無かったという印象でした。
何処かのレビューに書かれていた「高級食材を使用して調理に失敗した料理を食べさせられている気分」というのは的確な表現だと思います。
別に、魔法の力を持った王子様が世界を救う力を集める物語でも良いですが、若い青年を主人公にしておいてヒロインと文通しかイベントが無かったのは味気ないし、仲間も主人公に自分の身を犠牲にして世界を救う事を期待しすぎていて友情は感じられなかった。主人公も自己犠牲に納得してないのに結局周りに流されて与えられた役割を演じるだけ。パパとの親子愛の描写も薄かったし、サブイベを強化しやすいオープンワールドなのに何故か周りのキャラクターとシナリオが薄かったという印象でした。
反面、戦闘システムは面白かったです。
回避手段が豊富なので、戦闘中に考える事がけっこう多くて楽しい。
(1)オート回避(2)ジャストガードやパリィ(3)ローリング回避(4)マップシフト(5)シフトブレイク(6)シフト回避(7)ジャンプ回避(8)指輪魔法(9)仲間のコマンドで敵の動きを止めてキャンセル(10)ファントムソード(11)召喚獣
他にも防御手段があったかもしれませんが、とにかく敵の当たり判定から逃れる選択肢が豊富な事は自由度も高く面白かったです。ライブラ多用して弱点ついてとにかく先手でクラッシュを狙うって戦い方も出来ました。
ストーリーはどうでもいいから、景色の綺麗なオープンワールドでアクションRPGをやりたいって人には、オススメ出来る作品だと思います。
戦闘に関してだけはスカイリムやウィッチャーよりもFF15 の方が自分は楽しめました。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
大衆心理をも描く意欲作
ペルソナ5は今まで自分が遊んだJRPGの中で一番ストーリーに感銘を受けました。
誰が何をしたとか具体的なネタバレはなしに、その理由をレビューしようと思います。
何故面白いと思ったのか、こんなにも続きが気になったのかしばらく考えて、ペルソナ5にはプレイヤー自身が登場している、という事に気がつきました。
街角で学校で、雑踏の中好き勝手な噂話や批評している大衆が存在します。時に権力に媚び、時に理不尽に泣き寝入りして、時に人生の落伍者を見下し安心を得て、他人の痛みを見て見ぬフリをして、周囲に振り回されながら日々を生活しています。
ペルソナを操る怪盗団は様々なボスと異世界で戦いますが、その副産物として大衆の心も魅了し微かな期待を持たせていきます。その名も無き人々こそプレイヤーなのではないでしょうか。
ペルソナなんて実在しないし、権力に逆らうのも無益な事かもしれません。多くのプレイヤーにはむしろ怪盗団こそが荒唐無稽とみえると思います。それを反面教師として現実での処世術を考えるも良し、美学を求め夢を見るも良し、現実の理不尽からの一時的な逃避を楽しむのも良しです。
少なくとも私個人は様々な事を考えてしまいました。学生時代の失敗を振り返ったり、腹たつ上司や客先を思い出し、昔の友人関係をも考え直しました。社会に生き無力ながら必死な大衆を見せつけられて、社会の中で自分はどうしたかったのかと、何が大切だったのか、そういった事を考えさせられました。
たかがゲームでそういった事を考えさせられるのも、ペルソナが日常を描く事をテーマにしているからだと思います。現実は想像もし得ない理不尽が振りかかってきたりして、どうしようもない事もあります。思春期の主人公達は幼い義憤で世の中に怒り立ち上がりますが、無力な一般人はそうもいきません。それでも、怪盗団の美学を支持するのか正義だと思うのか匿名で投票する事くらいには参加出来ます。
私はこのペルソナ5のストーリーは伏線等々非常に練られ、巧妙に作り込まれた名作だと思います。所詮はファンタジーで作り話ですが、世の中を鋭く描こうとしており、挑戦的で素晴らしい作品だと思いました。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
ペルソナ5は今まで自分が遊んだJRPGの中で一番ストーリーに感銘を受けました。
誰が何をしたとか具体的なネタバレはなしに、その理由をレビューしようと思います。
何故面白いと思ったのか、こんなにも続きが気になったのかしばらく考えて、ペルソナ5にはプレイヤー自身が登場している、という事に気がつきました。
街角で学校で、雑踏の中好き勝手な噂話や批評している大衆が存在します。時に権力に媚び、時に理不尽に泣き寝入りして、時に人生の落伍者を見下し安心を得て、他人の痛みを見て見ぬフリをして、周囲に振り回されながら日々を生活しています。
ペルソナを操る怪盗団は様々なボスと異世界で戦いますが、その副産物として大衆の心も魅了し微かな期待を持たせていきます。その名も無き人々こそプレイヤーなのではないでしょうか。
ペルソナなんて実在しないし、権力に逆らうのも無益な事かもしれません。多くのプレイヤーにはむしろ怪盗団こそが荒唐無稽とみえると思います。それを反面教師として現実での処世術を考えるも良し、美学を求め夢を見るも良し、現実の理不尽からの一時的な逃避を楽しむのも良しです。
少なくとも私個人は様々な事を考えてしまいました。学生時代の失敗を振り返ったり、腹たつ上司や客先を思い出し、昔の友人関係をも考え直しました。社会に生き無力ながら必死な大衆を見せつけられて、社会の中で自分はどうしたかったのかと、何が大切だったのか、そういった事を考えさせられました。
たかがゲームでそういった事を考えさせられるのも、ペルソナが日常を描く事をテーマにしているからだと思います。現実は想像もし得ない理不尽が振りかかってきたりして、どうしようもない事もあります。思春期の主人公達は幼い義憤で世の中に怒り立ち上がりますが、無力な一般人はそうもいきません。それでも、怪盗団の美学を支持するのか正義だと思うのか匿名で投票する事くらいには参加出来ます。
私はこのペルソナ5のストーリーは伏線等々非常に練られ、巧妙に作り込まれた名作だと思います。所詮はファンタジーで作り話ですが、世の中を鋭く描こうとしており、挑戦的で素晴らしい作品だと思いました。
★ ダクソ3攻略, ダクソ2攻略, ブラボ攻略, RO支援AB, ゲーム感想, TOP★
ダークソウル3攻略
初心者向けステ振り紹介
*魔法型のススメ
*技量系のススメ
*脳筋のススメ
*上質騎士のススメ
*アンバサのススメ
*素性と初心者向けアドバイス
*ステータス振り上昇値
*序盤おすすめ武器
*キャラメイクのレシピ
*Ver1.04大剣比較
*日記①、②
*魔法型のススメ
*技量系のススメ
*脳筋のススメ
*上質騎士のススメ
*アンバサのススメ
*素性と初心者向けアドバイス
*ステータス振り上昇値
*序盤おすすめ武器
*キャラメイクのレシピ
*Ver1.04大剣比較
*日記①、②
ダークソウル2攻略
*ご意見・足跡板
初心者向けステ振り紹介
超高難易度アクションRPG
会話不要の気楽な協力プレイ
*おすすめ素性やステータス
*アンバサ支援のススメ
*アンバサ育成
*魔法剣士のススメ
*脳筋のススメ
*技量系のススメ
*上質騎士のススメ
*闇術師のススメ
*ニコニコを参照する
ステータス振り考察
*生命・持久・体力・適応
*記憶力
*理力・信仰
*筋力・技量
魔術師での序盤攻略
序盤ボス攻略
*最後の巨人
*竜騎兵
*流罪の執行者
*呪縛者
*古い竜狩り
*虚ろの衛兵
*鐘守のガーゴイル
*忘れられた罪人
最序盤ステージ攻略
*朽ちた巨人の森
DLCステージ攻略
*聖壁の都①
*聖壁の都②
*煙の騎士
*騎士アーロン
SCHOLAR_OF_THE_FIRST_SIN
*1/15調整情報
*4/1調整情報
デモンズソウル
*アンバサ&月光型
ダークソウル無印
*魔法剣士&月光型
次作
*ブラッドボーンPV
*ブラッドボーンα
*イベントに参加しよう!!
初心者向けステ振り紹介
超高難易度アクションRPG
会話不要の気楽な協力プレイ
*おすすめ素性やステータス
*アンバサ支援のススメ
*アンバサ育成
*魔法剣士のススメ
*脳筋のススメ
*技量系のススメ
*上質騎士のススメ
*闇術師のススメ
*ニコニコを参照する
ステータス振り考察
*生命・持久・体力・適応
*記憶力
*理力・信仰
*筋力・技量
魔術師での序盤攻略
序盤ボス攻略
*最後の巨人
*竜騎兵
*流罪の執行者
*呪縛者
*古い竜狩り
*虚ろの衛兵
*鐘守のガーゴイル
*忘れられた罪人
最序盤ステージ攻略
*朽ちた巨人の森
DLCステージ攻略
*聖壁の都①
*聖壁の都②
*煙の騎士
*騎士アーロン
SCHOLAR_OF_THE_FIRST_SIN
*1/15調整情報
*4/1調整情報
デモンズソウル
*アンバサ&月光型
ダークソウル無印
*魔法剣士&月光型
次作
*ブラッドボーンPV
*ブラッドボーンα
*イベントに参加しよう!!
ブラッドボーン攻略・育成
別ブログにしました。
『ブラッドボーン攻略ブログ』
★基本データ
*武器一覧
*武器強化後の攻撃力比較
*武器強化による補正変化表
*カレル文字一覧
*強化素材入手
*過去(素性・生まれ)
*最初の武器選択
*商人
*アプデ・発売前情報など
★育成
*生命&持久特化型
*筋力型(脳筋)
*上質型(筋力と技術)
*技術型
*神秘型(秘儀一覧)
*血質型(銃特化)
『ブラッドボーン攻略ブログ』
★基本データ
*武器一覧
*武器強化後の攻撃力比較
*武器強化による補正変化表
*カレル文字一覧
*強化素材入手
*過去(素性・生まれ)
*最初の武器選択
*商人
*アプデ・発売前情報など
★育成
*生命&持久特化型
*筋力型(脳筋)
*上質型(筋力と技術)
*技術型
*神秘型(秘儀一覧)
*血質型(銃特化)
ブラボ・ステージ攻略
*ヤーナム市街
*聖堂街
*旧市街
*ヘムウィックの墓地街
*隠し街ヤハグル
*禁域の森
*ビルゲンワース
*廃城カインハースト
*隠し街ヤハグル・赤い月
*教室棟・悪夢の辺境
・メンシスの悪夢
*エンディング分岐条件
*聖堂街
*旧市街
*ヘムウィックの墓地街
*隠し街ヤハグル
*禁域の森
*ビルゲンワース
*廃城カインハースト
*隠し街ヤハグル・赤い月
*教室棟・悪夢の辺境
・メンシスの悪夢
*エンディング分岐条件
ラグナログ 支援育成
ぬるゲーマーのすすめ
支援プリ
*狩場別・PT別で支援考察(2007)
*支援プリ育成(2007)
*支援廃プリ育成(トール以後)(2010)
支援アクビ
*ニヨPTで支援ABの育成・ステ(2013)
*支援ABのスキル(2013)
*アコプリ最短転職育成(2013)
支援アクビのソロ
*支援ジュデックスのススメ(2013)
*RR後の低レベル狩場(2013)
支援ジュデックス型育成
*お手ごろ装備(2013)
*ステータス・育成タイプ(2014)
*スキル構成(2014)
*武器火力(2014)
*審判の靴(2014)
サブキャラ育成
*弓手育成(養殖)(2013)
支援プリ
*狩場別・PT別で支援考察(2007)
*支援プリ育成(2007)
*支援廃プリ育成(トール以後)(2010)
支援アクビ
*ニヨPTで支援ABの育成・ステ(2013)
*支援ABのスキル(2013)
*アコプリ最短転職育成(2013)
支援アクビのソロ
*支援ジュデックスのススメ(2013)
*RR後の低レベル狩場(2013)
支援ジュデックス型育成
*お手ごろ装備(2013)
*ステータス・育成タイプ(2014)
*スキル構成(2014)
*武器火力(2014)
*審判の靴(2014)
サブキャラ育成
*弓手育成(養殖)(2013)
ラグナログ 覚醒後の狩場
*ABソロ狩場まとめ(2014)
支援ジュデックス型ソロ
*オーディン神殿2
*名も無き島2F
*ニブルヘイム峡谷
*ニブルヘイム秘境村
*病院2F
PT&ペア
*ごつみのPT
*亀島最下層3F
*監獄
*ビフロストタワー2F
*病院1F
*ニブルヘイム峡谷
支援ジュデックス型ソロ
*オーディン神殿2
*名も無き島2F
*ニブルヘイム峡谷
*ニブルヘイム秘境村
*病院2F
PT&ペア
*ごつみのPT
*亀島最下層3F
*監獄
*ビフロストタワー2F
*病院1F
*ニブルヘイム峡谷
マンガ感想&ネタバレ
★ぼくの地球を守って
(1), (2), (3), (4), (5)
(6), (7), (8), (9), (10), (11)
★ぼくは地球と歌う
1巻, 9話
★東京喰種-トーキョーグール-:Re 1話
(1), (2), (3), (4), (5)
(6), (7), (8), (9), (10), (11)
★ぼくは地球と歌う
1巻, 9話
★東京喰種-トーキョーグール-:Re 1話
ゲーム感想・おすすめ
*メタスコアランキング
上からオススメ順。主観多々
世界観重視,厨二ファンタジー,
美男美女,癒し系,協力ゲーム好き
【個人的な神作品】
*ICO(ADV,PS2等)
*風ノ旅ビト(ADV,PS3)
*Demons&DarkSouls(Act,PS3)
*DarkSouls2(Act.RPG,PS3等)
*Bloodborne(ARPG,PS4)
*ワンダと巨像(ADV,PS2等)
*rain(ADV,PS3)
*428(ADV,PSP等)
*シュタインズゲート(ADV,PS3)
*空の軌跡,零の軌跡(RPG,PC等)
*ジルオール(RPG,PS2等)
*幻想水滸伝1-3(RPG,PS等)
*シャドウハーツ1&2(RPG,PS2)
*月下の夜想曲(Act,PS等)
*Ysシリーズ(ARPG,Vita等)
*Ys8(ARPG,Vita等)
*逆転裁判(ADV,DS等)
*キングダムハーツ(RPG,PS2)
*ラストオブアス(TPS,PS3)
*GTAシリーズ(TPS,PS3,ceroZ)
*ウィッチャー3(RPG,PS4,Z)
*スプラトゥーン(TPS,WiiU)
*華アワセ(乙ゲ,PC)
【個人的な秀作】
*DOOM(FPS,PC)
*FF5(RPG,SF)
*DQ5(RPG,SF)
*モンハン2G(Act,PSP)
*IQ(パズル,PS)
*TRICK&LOGIC(ADV,PSP)
*デビルメイクライ4(Act,PS3)
*ドラゴンズドグマ(RPG,PS3)
*エルダースクロール(RPG,PS3,Z)
*マインクラフト(工作,PS3等)
*アサシンクリード(Act,PS3,Z)
*アンチャーテッド(TPS,PS3)
*零~zero~(ADV,PS2)
*零~濡鴉の巫女~(ADV,WiiU)
*SIREN(Act,PS2等)
*ぐるみん(Act,PSP&PC)
*ダンガンロンパ1&2(ADV,PSP)
*プロジェクトディーバ(音楽,etc)
*龍が如く4(ADV,PS3)
*東方・紅魔城伝説2(Act,PC)
*式神の城(Stg,PS2)
*ペルソナ4(RPG,PS2等)
*大神(RPG,Wii等)
*ニーア・レプリカント(RPG,PS3)
*メタルギアソリッド(Act,PS等)
*2016年発売日表
*2015年E3PV集
上からオススメ順。主観多々
世界観重視,厨二ファンタジー,
美男美女,癒し系,協力ゲーム好き
【個人的な神作品】
*ICO(ADV,PS2等)
*風ノ旅ビト(ADV,PS3)
*Demons&DarkSouls(Act,PS3)
*DarkSouls2(Act.RPG,PS3等)
*Bloodborne(ARPG,PS4)
*ワンダと巨像(ADV,PS2等)
*rain(ADV,PS3)
*428(ADV,PSP等)
*シュタインズゲート(ADV,PS3)
*空の軌跡,零の軌跡(RPG,PC等)
*ジルオール(RPG,PS2等)
*幻想水滸伝1-3(RPG,PS等)
*シャドウハーツ1&2(RPG,PS2)
*月下の夜想曲(Act,PS等)
*Ysシリーズ(ARPG,Vita等)
*Ys8(ARPG,Vita等)
*逆転裁判(ADV,DS等)
*キングダムハーツ(RPG,PS2)
*ラストオブアス(TPS,PS3)
*GTAシリーズ(TPS,PS3,ceroZ)
*ウィッチャー3(RPG,PS4,Z)
*スプラトゥーン(TPS,WiiU)
*華アワセ(乙ゲ,PC)
【個人的な秀作】
*DOOM(FPS,PC)
*FF5(RPG,SF)
*DQ5(RPG,SF)
*モンハン2G(Act,PSP)
*IQ(パズル,PS)
*TRICK&LOGIC(ADV,PSP)
*デビルメイクライ4(Act,PS3)
*ドラゴンズドグマ(RPG,PS3)
*エルダースクロール(RPG,PS3,Z)
*マインクラフト(工作,PS3等)
*アサシンクリード(Act,PS3,Z)
*アンチャーテッド(TPS,PS3)
*零~zero~(ADV,PS2)
*零~濡鴉の巫女~(ADV,WiiU)
*SIREN(Act,PS2等)
*ぐるみん(Act,PSP&PC)
*ダンガンロンパ1&2(ADV,PSP)
*プロジェクトディーバ(音楽,etc)
*龍が如く4(ADV,PS3)
*東方・紅魔城伝説2(Act,PC)
*式神の城(Stg,PS2)
*ペルソナ4(RPG,PS2等)
*大神(RPG,Wii等)
*ニーア・レプリカント(RPG,PS3)
*メタルギアソリッド(Act,PS等)
*2016年発売日表
*2015年E3PV集
ゲーム感想
【個人的な惜作】
*閃の軌跡Ⅱ,②,③感想,④,⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈(RPG,PS3)
*フラジール(ADV,Wii)
*絶対絶望少女(Act,Vita)
*ジルオールゼロ(Act,PS3)
*ブレスオブファイヤ5(RPG,PS2)
*ドラッグドラグーン3(RPG,PS3)
*エスカのアトリエ(RPG,PS3)
*FF13-3R(RPG,PS3)
*テイルズヴェスペリア、②感想(RPG,PS3)
*Tree of Savior(ARPG,ネット)
*ECO(RPG,ネット)
*タルタロス、②、③(ARPG,ネット)
*歴史物(小説・漫画)
独自性、戦闘操作性、快適か
ストーリー、キャラ、デザイン
音楽、画質、難易度で評価
*閃の軌跡Ⅱ,②,③感想,④,⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈(RPG,PS3)
*フラジール(ADV,Wii)
*絶対絶望少女(Act,Vita)
*ジルオールゼロ(Act,PS3)
*ブレスオブファイヤ5(RPG,PS2)
*ドラッグドラグーン3(RPG,PS3)
*エスカのアトリエ(RPG,PS3)
*FF13-3R(RPG,PS3)
*テイルズヴェスペリア、②感想(RPG,PS3)
*Tree of Savior(ARPG,ネット)
*ECO(RPG,ネット)
*タルタロス、②、③(ARPG,ネット)
*歴史物(小説・漫画)
独自性、戦闘操作性、快適か
ストーリー、キャラ、デザイン
音楽、画質、難易度で評価
ゲーム日記
★シャドウバース
冥府エルフ
ロイヤル
★任天堂ゲームの感想
*スプラトゥーンの日記
S以上・96凸ギア立ち回り戦略
おすすめ武器
C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A
マップざっくり考察
★ファルコムゲームの感想
*イースⅧの日記
1, 2, 3, 4, クリア後の感想
*東京ザナドゥの日記
1話, 2話, 3話, 4話, 5話,
幕間, 6話, 7話, 最終話
クリア後の感想
*閃の軌跡Ⅱ
*①,②,③クリア後レヴュー,④,
⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈
*その他
*空の軌跡,零の軌跡
*Ysシリーズ
*ぐるみん
★スクエニのゲームの感想
*いけにえと雪のセツナ
(1), (2), (3), (4), (5)
クリア後の感想
Amazon工作疑惑
★LOL
*初心者向けオススメ動画
*レーンごとオススメ
*アーリ
*アニー
*フォーチュン
*導入ガイド
冥府エルフ
ロイヤル
★任天堂ゲームの感想
*スプラトゥーンの日記
S以上・96凸ギア立ち回り戦略
おすすめ武器
C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A
マップざっくり考察
★ファルコムゲームの感想
*イースⅧの日記
1, 2, 3, 4, クリア後の感想
*東京ザナドゥの日記
1話, 2話, 3話, 4話, 5話,
幕間, 6話, 7話, 最終話
クリア後の感想
*閃の軌跡Ⅱ
*①,②,③クリア後レヴュー,④,
⑤キャラ,⑥,⑦,⑧クリア後の解釈
*その他
*空の軌跡,零の軌跡
*Ysシリーズ
*ぐるみん
★スクエニのゲームの感想
*いけにえと雪のセツナ
(1), (2), (3), (4), (5)
クリア後の感想
Amazon工作疑惑
★LOL
*初心者向けオススメ動画
*レーンごとオススメ
*アーリ
*アニー
*フォーチュン
*導入ガイド
最新記事
(11/14)
(07/21)
(07/06)
(06/21)
(06/09)
(06/05)
(10/04)
(09/17)
(03/26)
(12/01)
(03/13)
(01/14)
(01/12)
(01/05)
(01/05)
支援(・∀・)スキーによる雑記
(*´▽`)_旦ちゃ~
最近はジュデックス…
ソウルシリーズ・フロムゲーに関しては 姉妹で情報収集をしています。
姉:さきちゃ
RPG好き。特に支援職が好き。
好きなキャラは、エアリス。
妹:ヨルタ
モンハン世代。
ICOでゲームにハマる。
反射神経はないけど、 探索ゲー・雰囲気ゲーが好き。


